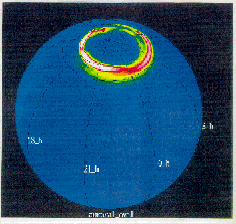
宇宙空間プラズマシミュレーション
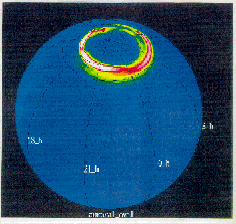
地上ではプラズマ状態で存在するものはそれほど多くないが、宇宙空間では物質はプラズマ状態で存在するのが普通である。従って宇宙空間の物理を一般的に表現するのは電磁流体力学となる。我々が研究対象としている太陽、惑星間空間、磁気圏、電離圏は電磁流体力学で記述される領域の典型である。これらの領域で発生する諸現象の物理を解明するには、電磁流体力学の研究が不可欠となる。しかしながら、トポロジーの複雑な実際の系を取り扱うのは、解析的手法では困難であり、計算物理学が必要となる。
電磁流体方程式は、質量、運動量、磁場、エネルギーの変化を記述する8つの式から成り立つ。数学的には双曲型方程式であり、8×8のフラックスヤコビ行列の固有値が全て実数となる。これらの固有値は系を伝搬する波動の速度に対応する。良く知られているように、流体方程式もやはり双曲型方程式であり、音波とエントロピー波が伝搬する系となっている。この系を離散化して数値的に扱うには、保存系で表現した時の数値フラックスの評価がキーポイントであることが分かっている。最近の数値流体力学はめざましい発展をとげているが、その原動力となっているのは、数値フラックスをリーマン問題の解で与える高精度上流化スキームの発見であり、これらの解法の代表的なものがTVD(全変動逓減)スキームと呼ばれているものである。線形近似では、リーマン問題はフラックスヤコビ行列の対角化と等価であるが、電磁流体方程式においては、アルベン波、速進波、遅進波、エントロピー波が伝搬するので、リーマン問題が複雑になる。しかしながらリーマン問題の解析解は存在し、TVDスキームが構築できる。
我々の扱う系では、太陽面と太陽風、磁気圏と電離圏というように、大きさや性質が大きく異なった領域が結合し、エネルギーのやり取りを行う。従って、数値解析を行う上で、非構造格子を取り扱うことが不可欠である。このため、電磁流体方程式を有限体積形で扱う。数学的には、有限体積形は保存形にガウス積分を行った表示である。電磁流体方程式の空間回転対称性を用い、積分表示のもとでTVDスキームを適用すると、有限体積TVDスキームができる(1)。
最近の計算物理学におけるもう一つの問題は、並列計算である。テラフロップスを目指す次世代スーパーコンピュータは全て並列型に移行する。特に日本のスーパーコンピュータは先陣をきって並列化に移行している。並列型の中でも極限性能を追求するのは、メモリー分散型ベクトルー並列計算機である。しかし、メモリ分散型計算機ではこれまでのノイマン式プログラミングは適用出来ない。並列型計算の効率化は、末端を操作するプログラミングテクニックでなく、数学的構造を含めた計算の大枠を並列化することによって達成される。従って、スキームの構築段階から並列化が考慮されねばならない。以上述べたことを考慮した上で開発されたのが、通信総合研究所宇宙科学グループの並列化有限体積TVDスキームである。このスキームは現在富士通VPP500で稼動しているが、並列化命令を無視すればワークステーションやSMP(対称複数処理)型計算機でも稼動し、下位互換性も有している。さらに我々のスキームでは低ベータ領域での計算精度を確保するため、ポテンシャル磁場が方程式の変数として直接現れな いように方程式を再構築してある。これでも以前としてフラックスヤコビ行列は対角化可能であることが示される。(3)
並列化有限体積TVDスキームによってこれまでに研究を進めた問題は、(1)太陽風−磁気圏−電離圏相互作用、(2)非磁化惑星での太陽風−電離圏相互作用、(3)太陽圏逆噴流ジェットの問題である。以下これらの結果について、その概略を示す。
地球磁場は超音速プラズマ流である太陽風によって圧迫され、磁気圏を形成する。もしも凍結の原理が完全に成立すれば、太陽風は磁気圏プラズマとは混じり合わず、磁気圏の形成は磁場閉じこめ問題となる。この場合、地球磁場を閉じこめるため磁気圏表面に電流が流れることになり、これはチャップマン−フェラーロ電流と呼ばれる。実際の太陽風磁気圏相互作用では、非理想的電磁流体過程によって、太陽風のエネルギー、モメンタムが磁気圏中に流入し、その結果、磁気圏プラズマ対流が励起される。凍結の原理によって、磁気圏プラズマ対流は磁気圏電場と等価であり、それは磁力線に沿って、電離圏に投影される。これは磁気圏での磁場に垂直なプラズマの運動が沿磁力線電流を伴ったアルべン波として電離圏に伝搬し、電離圏対流を励起すると言い替えることも出来る。ここで沿磁力線電流は電離圏電気伝導度によって決定されるから、磁気圏対流は電離圏によってコントロールされることになる。このように、太陽風、磁気圏、電離圏は相互作用系として自己無憧着的に扱う必要がある、(4)。
第1図に太陽風−磁気圏−のシミュレーションによって得られた地球磁気圏磁場を示す。
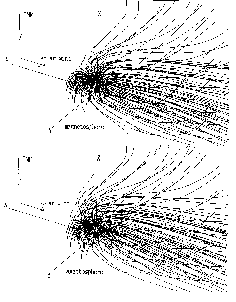
太陽風は太陽コロナが膨張し、星間空間に流失するものであるが、コロナガスは内部エネルギーを運動エネルギーに変換しつつ太陽重力圏を脱出し、超音速流となる。数 学的に言えば、特異点を通過し亜音速解から超音速解に乗り移ることになり、一旦超音速となった解は減速することなく、超音速を保つ。超音速太陽風が減速するのは、超音速銀河風との遭遇による。太陽風の領域は銀河風によって制限され、太陽圏を形成する。従って、太陽圏は超音速流どうしの相互作用によって特徴づけられ、銀河風上流方向では太陽風は逆噴流ジェットを形成する。第2図に、シミュレーションによって得られた太陽圏の三次元形状を示す。
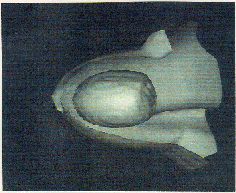
この図に示されているのは、終端衝撃波面(内側)と太陽圏界面(外側)である。超音速太陽風は終端衝撃波を通過して亜音速流となり、終端衝撃波と太陽圏界面との間のヘリオシースには、低速高温プラズマが圧縮された太陽風磁場と共に詰まっている。太陽圏界面の外側には、銀河プラズマが流れていることになる。終端衝撃波の三次元形状は下流側でカットされた特有の形状を示し、砲弾のようになる。これはマッハディスクと呼ばれる構造である。太陽圏で卓越する磁場構造は、太陽自転に伴うトロイダル磁場である。このトロイダル磁場は、ポロイダル電流系によって生成される。ポロイダル電流系は惑星間空間ではほぼ放射状に太陽コロナへと流入(流出)し、太陽赤道面に沿って流出(流入)する。しかしヘリオシース中の強められたトロイダル磁場を支える別種の電流系が存在する。それは太陽コロナを通過せず終端衝撃波面でショートカットされる電流系である。
金星や火星などの非磁化惑星では、電離圏は直接太陽風中に曝露される。よって、地球や木星などの磁化惑星では太陽風の動圧が磁気圧によって支えられるのに対し、非磁化惑星では太陽風の動圧は電離圏の低温プラズマによって支えられる(2)。この問題では、太陽風プラズマと電離圏プラズマを区別し、電離圏プラズマの生成消滅に関わる光化学を取り扱うため、2成分反応プラズマ系のシミュレーションが必要となる。そのため、質量の変化を記述する連続の方程式を2つ立て、9成分電磁流体方程式を扱う必要がある。このような拡張を行った9×9のフラックスヤコビ行列は依然対格化可能であり、TVDスキームが構築できる。第3図に、シミュレーションによって得られた、全プラズマ密度分布(上パネル)及び電離圏プラズマ密度分布(下パネル)を示す。
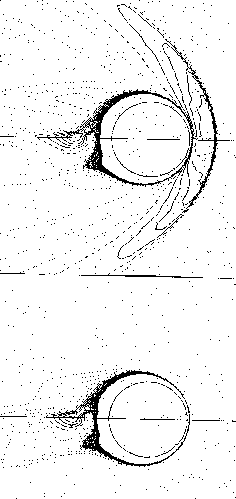
ここで各パネルの上反面はIMFと直角の子午面、下半分はIMFを含む赤道面を表す。第3図上のパネルから、昼間側でボーショック、イオノポーズが形成されているのが分かる。ここでイオノポーズとは、太陽風プラズマが電離圏プラズマに接している面である。イオノポーズが形成されるため、非磁化惑星の電離圏は地球電離圏と異なり、トップサイドがカットされた分布を示す。イオノポーズより低高度側の領域は、重力場で補足された低音高密度プラズマで満たされている。第3図の上下パネルの比較から、ボーショック背後のシース領域には電離圏プラズマは存在しないことが分かる。イオノポーズ高度は日没線に近づくに従って高くなり、夜側ではその存在ははっきりしなくなる。非磁化惑星の周りにはIMFが絡み付き、磁気圏尾に似た構造が形成されるが、 第3図から、電離圏プラズマが一部磁気圏尾に流れ出しているのが分かる。
第4図に、夜側から見た電離圏プラズマ密度等値面の三次元形状を示す。
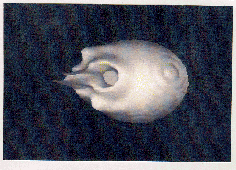
夜間電離圏の複雑な構造が見て取れる。
参考文献(1)Tanaka, T., Comput. Fluid Dyn. J., 1, 14, 1992.
(2)Tanaka, T., J. Geophys. Res., 98, 17251, 1993.
(3)Tanaka, T., J. Comput. Phys., 111, 382, 1994.
(4)Tanaka, T., J. Geophys. Res., 100, 12057, 1995.