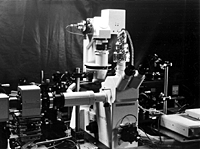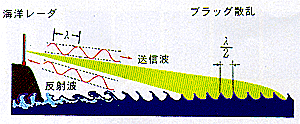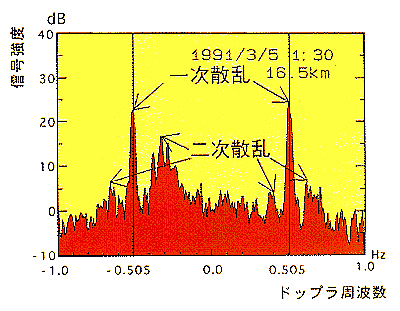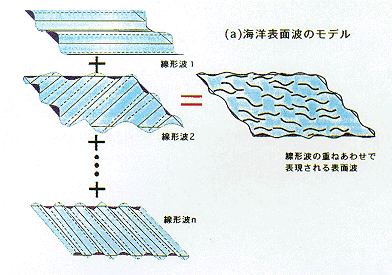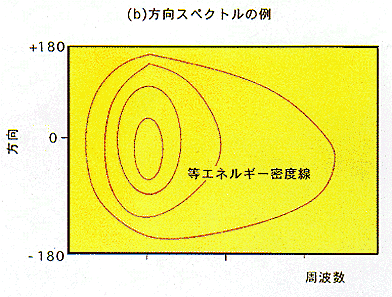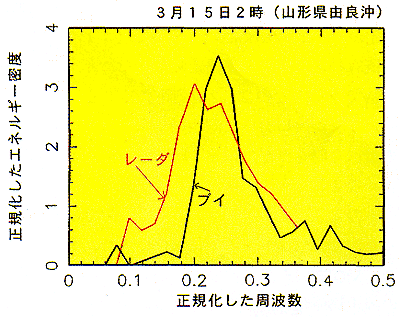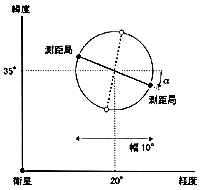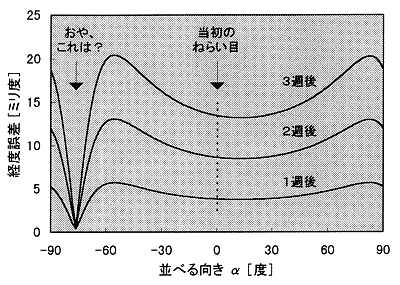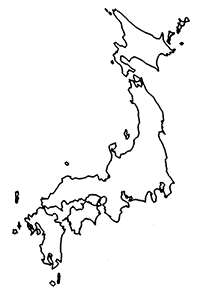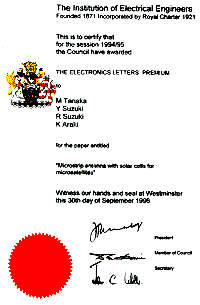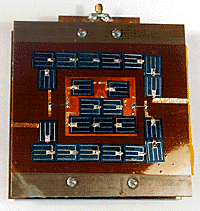マイクロ波帯における高速移動通信の研究
総合通信部 高速移動通信研究室長
長谷 良裕
1.はじめに
最近の携帯電話やPHSの爆発的な普及(平成8年10月には合わせて2千万台を突破)に見られるように、移動通信の進展はめざましいものがある。この勢いで加入者が増え続ければ、21世紀には従来の有線加入電話の台数(現在約6千万台)を凌駕し、通常の音声電話サービスは大半が無線の移動通信にシフトするかもしれない。
成熟した有線電話サービスがマルチメディア対応の高度な機能を目指すように、現在は音声通信のみの機能が中心の移動通信も、将来的には本格的なマルチメディア対応のサービスを提供出来ることが望まれる。高度なサービスを提供するには高速・広帯域の通信が必須であり、現在の割り当て周波数ではスペクトルが不足する。そのため、狭帯域化・高能率化の研究と平行して新たな周波数帯でのシステムの検討も必要である。2GHz帯において2Mbps程度までの伝送速度を目標とした第3世代の移動通信であるFPLMTS(Future Public Land Mobile Telecommunication Systems)の標準化が進められているが、さらなる高速化を目指した第4世代としては、3GHz以上のマイクロ波帯の使用が考えられる。
総合通信部高速移動通信研究室では、第4世代の移動通信システムを想定し、マイクロ波帯での高速移動通信の要素技術の研究開発を行っているので、その研究計画及び研究状況を紹介する。
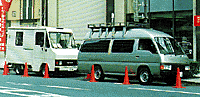
2.システムの目標と研究項目
動画像で現行テレビ放送並の品質を確保しようとすると、Mbpsオーダーの情報速度が必要となってくる。そこで、最高の伝送速度として10Mbpsを目標とし(ちなみに、現在のPHSの無線伝送速度は384kbps)、さらに、電子メールの様な低速データや音声、動画像までの様々な情報源に一元的に対応できる高速のマルチメディア移動通信システムを3〜10GHzのマイクロ波帯で実現することを想定したシステム基礎技術の研究開発を行う。これらの目標は、第4世代の移動通信となるFPLMTSフェーズ2としても想定されているものである。
システム全体について開発を行うのは、単独の研究所の能力を超えている。当研究室では、システムの最終目標を想定しつつ、その実現に必要な基礎的な要素技術の開発やデータ収集に重点を置いて研究を進めている。具体的には、以下に述べる、マイクロ波伝搬、高速伝送方式、統合伝送プロトコルの3点である。
まず第1に、マイクロ波帯は移動通信にとって未知の周波数であり、伝搬特性に関するデータがほとんどない。周波数が高くなるにつれて伝搬損失が大きくなるほか、回折効果が少なくなり、最大ドップラー周波数も比例して大きくなるため、伝搬環境は厳しくなるが、隣接セルからの干渉は少なくなることが予想される。セルサイズや配置を決めるための基礎データとして、伝搬特性の測定は欠かすことができない。また、高速伝送ではマルチパス伝搬による周波数選択性フェージングに伴うシンボル間干渉の問題が重要であるが、この対策及びその評価のためには伝搬の遅延特性と各種変調方式での誤り特性の関係を十分に把握する必要があ る。
次に、高速伝送方式では先に述べたシンボル間干渉による誤り発生が品質劣化の支配的要因となると考えられるので、フェージング対策技術が最も重要な技術課題となる。対策技術としては、反射波を受けないようにするアダプティブアレーアンテナ、伝搬路の特性を補正する適応等化器、低速の信号を束ねて送る並列伝送等の技術が考えられる。いずれの技術も重要な研究課題ではあるが、これらのうち、アダプティブアレーアンテナはサイズの問題があり、また、適応等化器は高速動作での回路規模に問題がある。そこで、本プロジェクトでは、他の技術動向も見ながら並列伝送の研究から取りかかることとした。
本格的なマルチメディアを移動通信を実現するためには、従来の固定の伝送速度を持つ回線交換方式では限界がある。有線でのATMに見られるような高速パケット交換の手法も取り込む必要がある。そして有線ATM網とシームレスに接続するため、データ/音声/画像のどの情報源にも一元的に対応できる統合伝送プロトコルの開発が急務である。また、無線では誤りや衝突によるパケット廃棄のために再送手順も含めたプロトコルを考える必要がある。
3.個別の研究課題
(1)マイクロ波伝搬
伝搬関係では、現在、3.35 GHz、5.20 GHz、8.45 GHzの3波で伝搬損失の測定を、主として東京の都心部で行っている。マイクロセルでのシステムを想定しているので、測定では、送信アンテナ高は数m程度と周りのビル高よりも低くとり、送信点から数100mの範囲内で測定を行っている。その結果、3.35 GHzと8.45 GHzとでは、見通し外での分布がかなり異なること等がわかった。
今後は、50Mcpsの拡散信号による高精度の遅延プロファイルの測定と各種変調方式での誤り発生特性の測定を中心に進めていく。現在、そのための装置を整備中で、この冬以降本格的な測定を開始する。誤り発生特性は、変調速度も変化させて測定する予定で、ある伝搬状況下でのフェージング対策なしの場合の臨界伝送速度が測定できる。

(2)高速伝送
高速伝送技術については、先にも述べたように、選択性フェージング対策技術として、まず、符号分割並列伝送方式の研究に取り組んでいる。用いる符号は直流バイアスを加えて相関点以外での相関係数を完全に0としたM系列符号を巡回させたものに、さらにガード区間を加えた符号を用いる。これにより、符号を効率的に使用すると共に、遅延波との直交性を保持でき、ガード区間長以内の遅延波からの干渉雑音を除去できる。1シンボル長以下の遅延波に対しては、RAKE受信を適用する。さらに、ガード区間長を遅延プロファイルによって適応的に可変にすることにより、伝搬状況に応じた適応可変容量伝送も可能である。
この方式の並列伝送装置は、計算機シミュレーションによって性能が評価され、高速で移動する車載局に対しても十分な性能が得られることがわかっている。現在、装置を試作しており、シミュレーション結果を野外実験で実証する予定である。
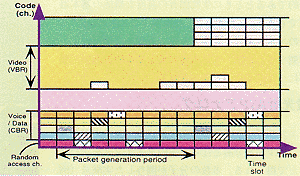
(3)統合伝送プロトコル
各種マルチメディア情報源に対応するためには、情報速度の大小だけでなく、即時性を要求するかどうかの分類も重要である。即時性の要求される情報(音声や動画像等)に対しては回線のコネクションを確立する通信が、要求されない情報に対しては、コネク ションレス通信が適している。また、高速の情報に対しては、特定のチャネルを時間的なスロットの区分なしに独占的に割り当てるのが効率的であるのに対し、低速の情報では、チャネルをスロットに分割して割り当てるのが効率的である。このような通信を行うための柔軟でかつ全ての情報源に対して一元的な取り扱いができる統合伝送プロトコルをR-ISMA(Reserved Idle Signal Multiple Access)という方式をベースに開発する。
移動通信では、伝搬路で発生する誤りに対する再送手順等も考える必要があるが、まず、第1段階として、誤りがほとんど発生しない安定した通信路である構内無線高速LANで、この新しいプロトコルの特性評価を行う予定でいる。そのための、伝送プロトコルを開発し、現在、その性能評価のための装置を試作中である。
4.おわりに
通信総研におけるマイクロ波帯高速移動通信技術の研究プロジェクトについて、その研究計画と現在の進行状況を述べた。これは、第4世代を想定した移動通信の基盤技術開発に関する研究である。この研究は、2000年頃までに要素技術の開発とその実証実験を行う計画である。
このプロジェクトを担当する高速移動通信研究室は、平成6年7月に発足した若い研究室である。現在、職員5名、特別研究員1名、研修生5名、事務アルバイト1名で担当している。(研究室のホームページ:http://largo.crl.go.jp)
この方法は全反射において低屈折率側の媒質に局在するエバネッセント光を利用した超低背景光の蛍光分子励起法である。台形石英ブロックをカバーグラス上にスペーサーを挟んで固定し、ブロックとカバーグラスの間を実験槽として利用する。蛍光性ATPアナログの励起にはArレーザーを用い、ブロック下面で全反射が起こるよう入射角を調整し、照射する。
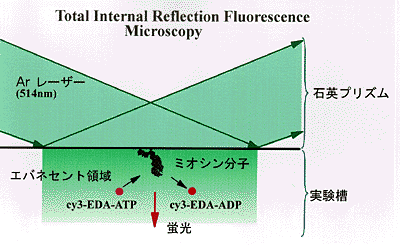
カバーグラス上の石英ブロックにArレーザーを照射し、ブロック下面で全反射させる。ミオシンはブロック下面に付着しており、これに結合した蛍光性ATPアナログはエバネセント光によって励起され蛍光を発する。
ブロック下面にはミオシン繊維が付着しており、そこに数nM程度の蛍光ATPアナログを潅流すると一本一本のミオシン繊維が蛍光像として観察される。蛍光性ATPアナログは、ミオシンによる加水分解過程において数十秒間、ミオシン上に結合する。ミオシン繊維上のミオシン濃度は実験時のATPアナログ濃度に比べて高いため、ATPアナログを結合したミオシン繊維は蛍光像として観察されるのである。次に、ミオシン繊維に平均1分子以下のATPアナログが結合すると推定される濃度までATPアナログ濃度を下げる。この条件下でミオシン繊維上に明滅する幾つかの蛍光スポットが観察された。
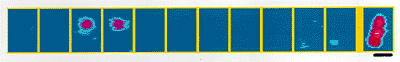
図3: 50pM蛍光性ATPアナログ存在下でミオシン繊維上に現われて消えて行く蛍光スポット。
3秒間隔で記録した同一視野像。右端は高濃度の蛍光性ATPアナログ存在下で確認したミオシン繊維。ミオシン繊維の位置にスポットが現われ、しばらく光りつづけているのがわかる。スケールバーは1μm。
ミオシンによる加水分解を受ける間、ATPアナログはミオシン上に留まるため蛍光スポットとして観察されると考えられる。したがって蛍光スポットの平均寿命は加水分解速度定数の逆数となる。蛍光スポット寿命のヒストグラムは指数分布を示し平均寿命は10秒程度、長いものでは50秒を超えるスポットも観察された。統計的解析から、観察された スポットは蛍光性ATPアナログ1分子に対応するものであることが、また、スポットの平均寿命の測定から蛍光性ATPアナログ1分子の加水分解過程を観察していることがそれぞれ示された。
単一分子計測の展望
ATP一分子の可視化はアクチュエーター(ミオシン)への入力過程を観察するものである。一方、出力である力や仕事を一分子レベルで測定する事はレーザー光による光ピンセットの利用で可能となる。この技術の組合わせにより、極めて近い将来に単一ミオシン分子による力発生とATP加水分解が同時に計測される様になり、エネルギー変換機構の解明という大きな目標に迫る事ができるであろう。また、ここで紹介した単一蛍光分子の可視化技術は、酵素と基質の相互作用を分子レベルで直接観察できるので、筋肉におけるエネルギー変換の研究のみならず細胞内情報伝達機構や物質輸送機構などの広い研究領域での応用が期待される。
(尚、本稿で紹介したTIRF顕微鏡は9月9日付け、日本経済新聞で報道された。)