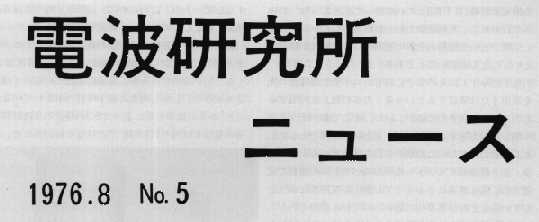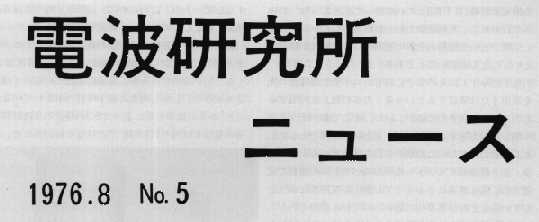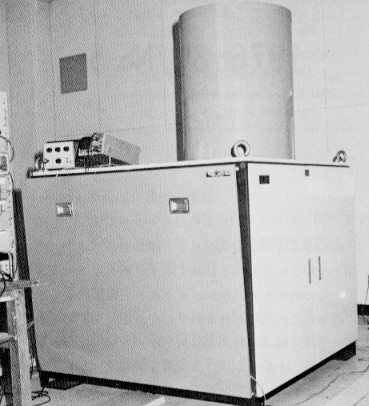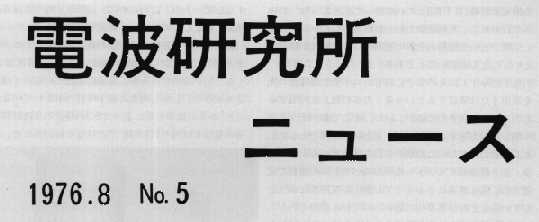
時間・周波数標準について
佐 分 利 義 和 (周波数標準部)
あらゆるものに変化もなく、運動もないとすれば、時
間とか時というものを認識できず、あるいは時間そのも
のがないのかも知れない。しかし、実際には多くの事象
に囲まれて古代から社会科学、自然科学を問わずその論
理の基底には常に時間とは何かという疑問を持ち続けて
きている。といったような難解な問題ではなく、当所の
担当する物理、技術分野での時間、周波数標準の確立と
いう具体的なことについて少しふれてみたい。
科学技術が精密化し、その規模が全世界的に、さらに
宇宙へと空間的にも拡大してくると、各種の物理量の標
準の高精度化がますます必要となる。時間の単位、すな
わち“秒”が物理量の基本単位の一つであることから、
あらゆる測定に不可欠であることも言うまでもない。こ
れらのことは米国の宇宙開発の諸段階に注目すれば多く
の例をみることができる。たとえば火星へのバイキング
1号の7億キロメートルの軌道と追跡技術の精度などは
極めてよい例であろう。
無線通信実用化の初期、混信をさけるため無線局の周
波数規制を目的として世界的に周波数標準の確立が叫ば
れたのが、当所標準の発端でもある。その後、原子周波
数標準の出現までは、水晶発振器および時計の安定度向
上、これを供給するための標準電波の確立などが主な研
究内容であった。当時は天文観測によって得られる地球
の自転周期が時間標準であったから、これを基準にして
水晶時計を較正する、いわゆる絶対測定がなされていた。
このことから分るように水晶時計は時間を精密に細分し
たり、天文データのバラツキを平均化、外挿するなどそ
の安定度が利用されたもので、それ自体で標準となりう
る性質はもたない。この時代の水晶発振器には長期の安
定度が特に要求された理由がここにあるわけであるが、
現在原子時計に組込まれるものには短期安定度が要求さ
れているのと対比的である。
時の流れを認識するために、古くから天体の動き、周
期性に注目し、暦をつくり、時刻を決め、時間標準を導
出してきた。代表的なものとして、地球の自転周期を基
にした世界時(UT、自転時とも呼ぶ)と公転にもとづ
く暦表時(ET)とがあるが、原子時計による原子時
(AT)の出現によって時間標準、すなわち秒の定義の座か
らは精度の悪さ(4桁以上悪い)を理由にはずされてい
る。しかしながら、UTとくにUT1とよばれるものは
地球の自転角度を直接示すものであり、地上から天体あ
るいは人工衛星を観測する場合には必要な量である。一
方ETはATとの比較によって天体力学と量子力学とい
う異なる理論から得られる時間の差異、もしあるとすれ
ば理論に含まれる物理常数の経年変化といったようなこ
とに結びつくのかなど学問的な重要さを含んでいる。こ
のような意味から、これらの量を原子時という一様な時
間スケールの上にたって、新しい技術(レーザ、宇宙
電波など)を用いて精密測定することが始められている。
原子時計の刻む原子時という時間標準が1967年より国
際的な秒の定義として採用され、1971年には時刻標準と
して国際原子時(TAI)、また各国での標準時として用い
る協定世界時(UTC)、これに伴って“うるう秒”の導
入が行われた。天体運動といった巨大なものから、一転
して原子という極微の世界の周期性に時間標準が移った
ということも面白いことである。
原子(分子)はその原子に固有かつ不変な周波数の光
を放出または吸収するという量子力学の教えを利用する
ものであり、世界中で誰が、いつ、どこで動かそうと全
く同じ進み方をする時計ができるという原理であるから、
水晶時計にはなかった標準の性格を備えているわけであ
る。長さ標準がクリプトン原子のスペクトルの波長で定
義され、電圧標準にジョセフソン素子が採用されようと
しているなど原子標準化の進められている理由であろう。
このような原理の利用は相当古くから考えられていた
ようであるが、実用化研究の開始はマイクロ波技術の発
達した第二次大戦後である。その精度は1950年頃は10^8
台であり、マイクロ波分光学、量子エレクトロニクスの
進歩とともに、その後の25年余で約5桁の精度向上を果
たし、現在では正確さ1×10^-13(10兆分の1の不確さ)
程度に達している。当所を含む日本での研究も割に早い
時機に進められ、たとえば昭和27年度電波技術審議会諮
問第1号として原子制御周波数標準が取り上げられアン
モニア分子の吸収方式についての答申がなされている。
当所ではこれに引続きアンモニア・メーザ方式の開発、
実用化によって秒の定義の改訂以前から周波数標準の確
立と標準電波の規正に利用しており、その後、ルビジュ
ーム原子あるいは水素メーザ、最近では新方式によるセ
シウム原子ビームの実験へと進めてきている。
このように10^13またはそれ以上の精度となると、現行
方式の原子時計でも種々の技術的困難さをかかえている
が、これに加えて時計自体におこる相対論効果など物理
現象に対する微小な補正を現実に考慮する必要がでてき
ている。特殊相対論での2次ドップラ効果によるシフト
については、原子スペクトル観測の際の原子の速度分布
を詳細に調べて補正をしたり、時計を飛行機で運搬する
場合に地上に静止している時計との差異が問題となって
いる。空間的に分布している時計同志の比較などになる
と一般相対論による効果、すなわち、重力ポテンシャル
や加速度によるシフトを考慮して補正しなければ、座標
全体として矛盾のない時系(座標時)を構成できなくな
る。秒の定義文には空間座標の記述はないが、これは任
意の地点での物理標準としての固有時が示されれば、物
理測定には十分であるという考え方である。しかしなが
ら、国際原子時をつくる場合のように、世界各地に分散
する時計の動きを合成するためには空間的な基準を規定
する必要がある。このために、国際原子時では海洋の水
準面に静止した時計という規定を入れてある。
地表付近にある時計は地球の重力ポテンシャルの影響
をうけて、これがないとした時の周波数より7×10^-10低
くなっている筈であるが、共通にずれているので確かめ
ようがない。しかし現実に原子時計のおかれているジオ
イド*からの高さの差によって2つの時計の歩度は異なり、
その量は1㎞当り1.1×10^-13だけ進む時計となる。地球
上の時計はこのほかに太陽その他の天体のポテンシャル場
のなかを地球の自転および公転運動とともに移動してい
るので、これらに対する考察もなされているが日変化、
年変化は共通に受けるので地球上の時計相互の差には影
響がほぼないとされている。
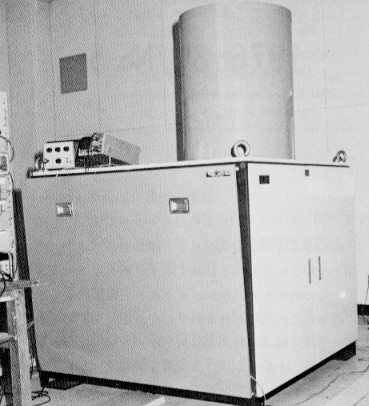
本所の水素メーザ原子時計
このような時計そのものに現われる相対論効果を実験
的に検証しようという試みがあり、飛行機で原子時計を
運搬して地表に静止している時計との差を求めることや、
水素メーザをロケットで打上げて周波数変化を測定する
ことなどが、すでに米国で実施されたり、計画されたり
している。この種の実験が可能であるのは、他の物理標
準に比して4桁以上も高精度であるということに加えて、
ビート法あるいは時計による微小差の積算が可能である
という高分解能の測定法の特徴にあると思われる。
標準の供給が電波を仲介にして可能であり、これによ
って遠隔地にある2つの標準時計の精密比較も可能にな
るという特殊性もある。標準供給の手段としては古くか
ら知られている短波標準電波(日本でのJJY)が簡易
かつ広域サービスの報時用として利用者が多いが電離層
による劣化が大きい。長波標準電波(日本でのJG2AS、
40kHz)は高精度周波数校正用として有効である。この
ほかにテレビ放送でのカラー副搬送波及び同期信号が原
子標準によって安定化されれば、伝送網が広帯域かつ安
定なため高精度の時刻および周波数供給の手段に利用で
きる。現在、NHKおよびNETテレビがルビジュウム発
振器を用いる時間帯があり、この場合の副搬送波は周波
数基準として全国的に利用できるので、当所でもこれを
測定してその偏差を公表している。
多くの利用者に、より高精度、高安定に広域サービス
を行うためにはやはり衛星の利用が望ましい。衛星によ
る時刻伝送方式には、移動衛星と静止衛星、一方向伝送
(受信のみ)と二方向伝送(送受信)、使用する周波数帯、
時刻パルス変調方式などの組合せによって種々の方法が
考えられる。遠隔地間の時刻比較精度の実験として、当
所では静止衛星ATS-1によるマイクロ波、2-wayモー
ドかつ周波数拡散多元接続(SSRA)方式によるパルス
伝送により日米間の時計比較を実施した。この結果、比
較精度約1ナノ秒(10億分の1秒)確度約10ナノ秒とい
う高精度を示し得たと同時に、回転座標系で生ずる光伝
搬の方向依存性という古くから知られている現象を最新
の技術で示し得た。
原子標準器の正確さおよび安定度が向上したというこ
とは、単に各国の時間、時刻標準の一致度がよく、物理
計測に役立つのみでなく、広範な地域での時計同期、特
に独立同期技術の各種技術への導入の端緒となっている。
世界的規模での電波航法(とくにオメガ)、人工衛星のト
ラッキング、超長基線干渉計(VLBI)などは原子時計
の利用によって実用化された例であり、このほか最近では
高速ディジタル通信網の同期確立のために利用しようと
いう検討も始められており、通信、放送分野での今後の
利用が期待される。
以上、時間、周波数標準のごく一部しか触れ得なかっ
たが、本分野の動向をいささかでも理解していただけた
とすれば幸いである。
(注釈)
* 地球の等重力ポテンシャル面のうち、海洋上において平均海面に一致するもの。
太陽地球関物理学(STP)国際シンポジウムに
出席して
恩 藤 忠 典 (電波部)
科学技術庁国際研究集会派遣員として、昭和51年6月
7日から18日の間、米国コロラド州ボルダーで行われた
太陽地球関物理学国際シンポジウムに出席した。太陽地
球間物理学国際シンポジウムは、1966年ベルグラード、
1970年レニングラード、1974年サンパウロで行われた。
今回のシンポジウムは、宇宙空間研究委員会
(COSPAR)、太陽地球間物理学特別委員会(SCOSTEP)、上
層大気物理学及び地磁気の国際連合(IAGA/IUGG)、米
国地球物理学連合(AGU)によって共催された。シンポ
ジウムの会場は、ボルダー市南部にあるフェアビュー高
校の講堂で行われ、200余の論文がパラレルセッションな
しで読まれた。会議の実行委員会は、NOAA(国立海洋
大気局)、NCAR(国立大気研究所)、コロラド大学、デ
ンバー大学の人々によって構成されていたようである。
宿舎はコロラド大学のウイリアムズ・ビレッジ寮等があ
てられ、会場と宿舎との間はスクールバスで往復した。
又宿舎から数マイルの所に、CRPL以来有名なRadioビ
ルディングがあり、現在はNOAA、ITS(通信科学研究
所)、NBS(国立標準局)が共同使用している。この建物
の玄関から程遠くない2階の一室に、NOAA環境科学研
究所(ERL)内の宇宙環境研究所(SEL)の宇宙環境サ
ービスセンターがあり、太陽 地球間の宇宙環境をモニ
ターするSELDADSが置かれていた。この装置は、SMS
/GOES、ITOS、TIROS-N、SOLRAD-Ⅱ等の衛星で観
測した太陽X線、高エネルギー粒子、プラズマ、磁場等
のデータ、世界各地で観測した、太陽面諸現象、オーロ
ラ、地磁気、電離層吸収、f0F2等のデータの変化を、実
時間で同時にブラウン管に写し出し、又それらのデータ
のハードコピーをすぐ取れるもので、これを用いて時々
刻々変化する太陽 地球間の宇宙環境をモニターし、そ
の結果を世界各地に知らせるサービスを行っている。又
Radioビルディングでは、6月9日~11日の間
ISIS Working Group Meeting が開かれ、私も顔を出して、
米国やカナダの関係者と旧交を温めた。6月8日の夕方、
コロラド大学を卒業したグレンミラーを記念するコロラ
ド大学構内のメモリアルセンターで、歓迎会が開かれた。
NOAA環境科学研究所長のW. N. Hess博士及
び環境科学研究所所属の宇宙環境研究所長の
D. J. Williams博士の歓迎の辞があり、夜更け
まで楽しい一時を過した。さて今回の私の出
張目的は、私自身の論文“磁気圏嵐開始時の
VLF-LF電波バースト”を発表することと、
このシンポジウムの各セッションに出席して
世界のこの方面の研究現況を知ることにあっ
た。シンポジウムの内容は、大別して、太陽
面現象、太陽大気及びコロナの動力学、太陽
風、高エネルギー粒子等の惑星間空間伝搬、
プラズマ内の境界層、衝撃波、及びエネルギ
ー輸送過程、地球の磁気圏-電離層-大気系
の動力学、太陽系の磁場、惑星磁気圏-電離
層系の動力学、太陽と地球大気環境との関係
等に関する、近来にない大きなスケールのシンポジウム
であった。それもその筈で、このシンポジウムのプログ
ラム委員長のD. J. Williams(42才)は、現在ホルダーに
あるNOAA/ERL/SEL(宇宙環境研究所)の所長をして
おり、もう一人のデンバー大学教授のJ. G. Roedererと
共に、1970年以前は、メリランド州グリーンベルトにあ
るNASAゴダード宇宙飛行センターに所属して、精力的
に地球磁気圏の研究に取り組んでいた。又Williams氏は
、1968年9月に米国ワシントンD.C.で行われた磁気圏
物理学の国際シンポジウムでも、プログラム委員長をし
ており、早くから米国の宇宙空間科学の中心的人物であ
った。今回のホルダーシンポジウムの主役達は、1968年
の磁気圏シンポジウムで活躍した若い研究者達であった、
と言っても過言ではない。しかし1968年当時と比べて変
ったことは、米国の若い秀れた研究者のAxford博士(カ
リフォルニア大)、Vasyliunas博士(MIT)及びイタリアの
Schindler博士が、西ドイツの有名なマックスプランク
研究所に所属していたことである。Vasyliunas博士(36
才)は、ドイツ語の亀の子文字(昔の字体)で書いたス
ライドをうつして、会場内の爆笑を誘っていた。今回の
ような大規模なSTPシンポジウムの一つとして、私がま
だ大学院の学生だった1961年に、京都・岡崎の京都会館
で行われた、地球嵐のシンポジウムがある。この時に活
躍したトロント大のHines教授、ライス大のDessler教
授、シカゴ大のParker教授等も、今回のシンポジウム
に出席していたが、年のせいか専ら聴き手にまわっ
て昔のような鋭い質問は全くしなかった。又シンポ
ジウムの内容も、1961年に盛んだった、太陽面現象と
電離層現象との関係、特に太陽宇宙線、X線が電離層
に起す異常電離、その短波伝搬への影響等に関する研究
発表がほとんどなかった。1957年に始った人工衛星によ
る観測によって、太陽地球間物理学が全く書き変えられ
てしまったことを痛感した。1961年のシンポジウムで、
著名な地磁気学者の故Sydney Chapman教授が、世界各地
の地磁気変化のデータを用いて求めた、2次元の電離層
電流系について議論した時、ノーベル賞を貰ったAlfven
教授が「なぜ3次元電離層電流系を考えないのか?」と
しつこく質問した。Chapman教授は「いやこれはただ地
上の地磁気変化の世界分布を、電離層の2次元等価電流
系として表現しているだけだ。」と答えられた様に記憶し
ている。今回のシンポジウムで、3軸制御のTRIAD衛星
で観測した、極光帯を通る地球磁力線に沿って、流入、
流出する電流系の全貌が、ジョンホプキンス大学の
Potemra博士によって発表され、15年前にAlfven教授が気に
していた3次元の電離層-磁気圏電流系が、常に極光帯
に沿って存在することが明らかになった。又太陽活動静
穏時の回帰性地磁気嵐の源として想定されていたM領域
に対応する“コロナの穴”が、Skylab. のX線、極短紫外線
による太陽面写真から発見されたとの発表があった。コ
ロナの穴は単極性の磁力線の束からなり、周辺に比べて
磁場が弱いため、高速の太陽プラズマ流が吹出し、回帰
性地磁気嵐を起すことが、確認された。又太陽静穏時に
は、太陽黒点が極小の時に、太陽プラズマ流速が極大で
あったことも報告された。アイオワ大のFrank教授が発
表した、磁気圏尾部のずっと後方で観測された、高速で
動く、磁場の弱い高温稀薄プラズマ塊(磁気圏の火玉)は
オーロラ嵐の源として大論争を巻起した。1980年代のス
ぺースシャトル及びInternational Sun Earth Explorer
によって、太陽地球間物理学は、大きく塗り変えられる
であろう。我々もこれらの新しい計画に、参加して行き
たいものである。週末に訪れたアスペンの山峡の白樺に
囲まれた、マロン湖畔の静かなたたずまいは印象的だっ
た。又4280mのエバンス山頂上からの、白雪を頂いたロ
ッキーの山波は実に雄大だった。今年は米国建国200年
であると共に、コロラド州創立100周年でもあった。快
晴の朝、ロッキーのふもとの静かな町ホルダーを後にした。

太陽-地球間宇宙環境モニター装置(NOAA・宇宙環境サービスセンター)
郵政省の「宇宙開発計画」に関する要望事項について
毎年6月から8月にかけて、各省庁の「宇宙開発計画
に関する要望事項」が宇宙開発委員会において審議され、
当年度の宇宙開発計画の大筋が明らかにされてきている。
今年も6月上旬に、郵政省の要望事項が策定され、宇宙
開発委員会及びその下部組織の計画部会或は技術部会に
おいて審議されてきており、来年3月には、宇宙開発計
画(昭和51年決定)が正式に決定されるはずである。郵
政省の要望事項のうち、当研究所が直接関係している事
項を参考資料として示し、主な衛星計画について簡単に
解説する。
1 実験用静止通信衛星Ⅱ型(Experimental Communications Satellite-Ⅱ)
ECS-Ⅱ計画は、我が国の将来の通信需要及びその多
様化に対処するため、実験用中容量静止通信衛星CS及
びECS計画の延長としてミリ波衛星通信システムの開発
を行うとともに、衛星データの効率的取得、衛星間中継
等を可能とするデータ中継衛星システムの開発を行おう
とするものであり、三軸安定方式の静止衛星を想定して
いる。
今日、国際通信回線及び諸外国で実用化され始めてい
る国内通信回線の大半がマイクロ波帯の周波数を利用し
ているが、この周波数帯か地上の通信回線に広く使用さ
れ混雑を極める一方であることから、将来の通信需要の
増大に対処するため、より高い周波数帯の開発が世界的
なすう勢である。我が国は、CS計画による準ミリ波30
/20GHz帯の利用技術の開発に続き、ECS計画によりミ
リ波利用技術の開発のため35/32GHzを用いて基礎的な
実験を行うこととしている。しかるに、この計画のスタ
ート時点から今日に至るまでの間におけるミリ波電力増
幅素子技術の進歩により、ミリ波帯で本来の固定衛星業
務に分配された50/40GHz帯による実験も現実的なもの
となってきた。このためECS-Ⅱ計画では、ECS計画の
成果を踏まえて、50/40GHz帯において、衛星搭載用自
動追尾マルチビームミリ波アンテナ及び衛星搭載用ミリ
波送受信機等のミリ波衛星通信システムの研究を行おう
とするものである。
他方、地球を周回する移動衛星と地上とを結ぶ通信回
線に、中継用の静止衛星を導入すると、衛星によるデー
タ取得及び衛星に対する管制を極めて効率的に行うこと
ができる。移動衛星に対する1ヵ所の地球局のデータ取
得可能範囲は、せいぜい10%程度である。従って、デー
タ取得効率を上げるためテープレコーダを搭載している
が、信頼性、非実時間性及び記憶容量等に問題がある。
これらの理由から、静止軌道上にデータ中継衛星を配置
して、移動軌道上のユーザ衛星と地球局との間に通信回
線を設定すれば、たとえば高度1,000㎞の衛星に対するデ
ータ取得可能範囲は68%に増大する。データ中継衛星2
個を1ヵ所の地球局の東西両側に配置すると、データ取
得可能範囲はほぼ100%に達することになる。すなわち、
地上の1ヵ所において移動衛星の全周回のデータを実時
間で連続的に取得することができ、運用管制を行うこと
もできる。我が国においては、将来各種の衛星打上げが
予想され、これら移動衛星を有効に利用するためのデー
タ中継衛星の必要性は極めて大きい。このためデータ中
継衛星システムの開発を行ない、昭和57年度打上げ予定
の電波観測衛星をユーザ衛星とみたて、低速データ伝送
実験を行う予定である。
2 電波観測衛星(Radio Monitoring Satellite)
RMS計画は、電離層観測衛星ISSの開発の成果等に基
づき、電離層観測の一層の充実化を図るとともに、無線
通信に影響を与える宇宙空間諸現象の観測・監視及び電
波によるリモートセンシング(遠隔探査)技術を応用し
て地球周辺の電波環境の観測を行おうとするものであり、
三軸安定方式の高度700~1,000㎞,傾斜角70°~80°の軌道
を周回する衛星を想定している。
現在、有効な通信手段のないところで広く使用されて
いる短波通信の有効利用については、電離層観測を通じ
短波通信の伝搬に関する予報警報システムを構成すると
ともに衛星の導入により短期予報及び警報システムを確
立し、真に実用性のあるシステムの完成を目ざしている。
一方、宇宙通信の発展に合わせて、地上-宇宙間の通信
回線設計に寄与するため、宇宙環境のモニタリングを行
い、短波のみならず全周波数帯の適切な利用を図り、そ
のための指標を設定する必要がある。とりわけ、将来の
電波利用上の重要問題と考えられるアクティブ・リモー
トセンシングの実用に当っては、宇宙空間におけるモニ
タリングシステムがその前提となる。
具体的な観測内容は、(1)電離層観測装置による電離層
の臨界周波数等の測定、(2)ISSの電波雑音観測を拡張
したVLF、HF、VHF、UHF帯(50Hz~2850MHz)に
おけるラジオメータによる電離層の上側の電磁波スペク
トラムの観測及びマイクロ波ラジオメータ(10.6、15.35、
22.2GHz)による地球表面、地球大気に関係するリモート
センシング、(3)上記VHF、UHF帯ラジオメータ或は
宇宙環境測定器による太陽活動に伴う宇宙諸現象の監視
等である。
当面、RMS搭載ミッション機器の一つであるマイク
ロ波ラジオメータの開発を始めることとし、輝度温度の
測定から、地球環境・資源の情報、特に海洋波浪状況や
海洋汚染の調査等が可能となる技術の開発を行うもので
ある。
当研究所における今年度の衛星計画は、上述のように
通信(ECS-Ⅱ)と計測(RMS)とを主体とした2つの衛星
計画にまとめられており、前者はN改Iロケットを、後
者はNロケットを打上げロケットとした重量を想定して
いる。言うまでもなく、RMSは従来改良型電離層観測
衛星で考えていたミッション機器に、リモートセンシン
グ関係機器を加えたものである。今年8月の宇宙開発委
員会第6回計画部会において、各省庁の要望した衛星計
画は次の4段階に区分けすることとされた。(Ⅰ)開発段
階、(Ⅱ)開発研究段階、(Ⅲ)研究段階、(Ⅳ)先行的研究
段階。この区分に従って、ECS-Ⅱ及びRMSは(Ⅲ)の研
究段階と認定された。
今年の「宇宙開発計画(昭和50年度決定)」の見直しにお
いて、当研究所の最大の関心事は、今年4月不具合の生
じたISS(うめ)の予備機(ISS-2)の早期打上げを決め
てもらうことであり、郵政省の要望事項の中にも昭和52
年度打上げが強く要望されている。ISS-2のデータを
短波の有効利用、或は内外の研究活動に資することを担
当機関として、強く望むものである。
(企画部第一課)
(参考資料) 宇宙開発計画に関する要望事項(郵政省)
- 1 実用通信・放送衛星構想(省略)
- 2 実験用通信衛星
- (1) 実験用静止通信衛星Ⅱ型(ECS-Ⅱ)
- 開発中のCS、ECSのあとを受けて、将来におけるミリ波の衛星通信における利用を考慮し、固定衛星用周波数として分配され
ている50/40GHz帯における衛星通信システムの開発を行うとともに、衛星データの効率的取得、衛星間中継等を可能とするデータ
中継衛星通信システムの開発を行うため、昭和58年度に実験用静止通信衛星Ⅱ型(ECS-Ⅱ)を打ち上げることとし、このための
システム及びミッション機器の研究を進める。
- (2) 移動業務用通信実験衛星(省略)
- 3 電離層観測衛星
- ISS(うめ)の不具合の原因を早急に究明し、ISS予備衛星(ISS-2)を可能な限り早期に打ち上げる。また、電離層観
測を継続するためISS型の衛星(ISS-3)をISS予備衛星に引き続き打ち上げることとする。なお、ISS-3について
は、ISSのミッション機器の一部を改良することとし、このための研究を行う。
- 4 電波観測衛星
- 電離層観測衛星の開発の成果等に基づき、電離層観測の一層の充実化を図ると共に、無線通信に影響を与える宇宙空間諸現象の観
測、通信じょう乱源の監視及び電波によるリモートセンシング技術を応用しての宇宙及び地球周辺の電波環境の観測を行うことを目
的とした衛星を昭和57年度に打ち上げることとし、所要のシステム及びミッション機器の研究を進める。
- 5 その他
- (1) スペースシャトルの利用についての調査研究(省略)
- (2) 米国スペースラブ計画への参加
- 米国NASAのスペースラブによる「大気圏雲の物理学的研究」に参加し研究を行う。
- (3) 新しい宇宙利用分野の調査研究(省略)
- (4) 電波によるアクティブ・リモートセンシングの調査研究
- 将来、電波によるアクティブ・リモートセンシングの実用が期待されるのでこれに関する調査研究を行う。
短 信
第18次南極越冬隊員
6月22日の南極観測統合推進本部総会において第18次日
本南極地域観測隊(夏隊・越冬隊)の隊員が決定された。
本所からは、西山昇(電離層部門)及び坂本純一(超高層
部門)の両氏が越冬隊に参加する。同観測隊の出発は本
年11月25日の予定である。
南極観測本部・本部員指名
7月28日付で、本部長に岩井登電波部長、副本部長に前
田力雄電波予報研究室長が指名され、それぞれの前任者
糟谷績、新野賢爾両氏の指名は解除された。
富士山ラジオメータ撤収
電波部電波気象研究室では、気象研究所との
共同研究による「富士山計画(通称)」の終了
に伴い、富士山頂のラジオメータ及び山麓
(御殿場)のサントラッカー等の施設を7月27
日に撤収した。なお、同計画は科学技術庁特
別研究促進調整費による「ミリ波の減衰と降
雨構造との関連に関する総合研究」として昭
和48年度に着手されたものである。
湿性大気汚染調査観測に協力
通信機器部物性応用研究室では、環境庁の協
力依頼を受けて栃木県南部における湿性大気
汚染調査観測に参加し、ライダ(レーザ・レ
ーダ)によるエアロゾルの高度分布及び雲底
高度の観測を6月26日から7月8日にわたり実施した。
CS・BS用主局庁舎にアンテナ設置
CS・BS用主局となる建造中の実験庁舎に7月23日直
径13mのアンテナが設置された。CSの準ミリ波用、
BSの14/12GHz用は共に同じ形式の物で、庁舎の左右・
3階建物の屋上に据付けられた。

据え付け終了したCS用(中央)BS用アンテナ(右)
(左は地上に設置のCSマイクロ波用アンテナ 北側から撮影)