

電 波 部
はじめに
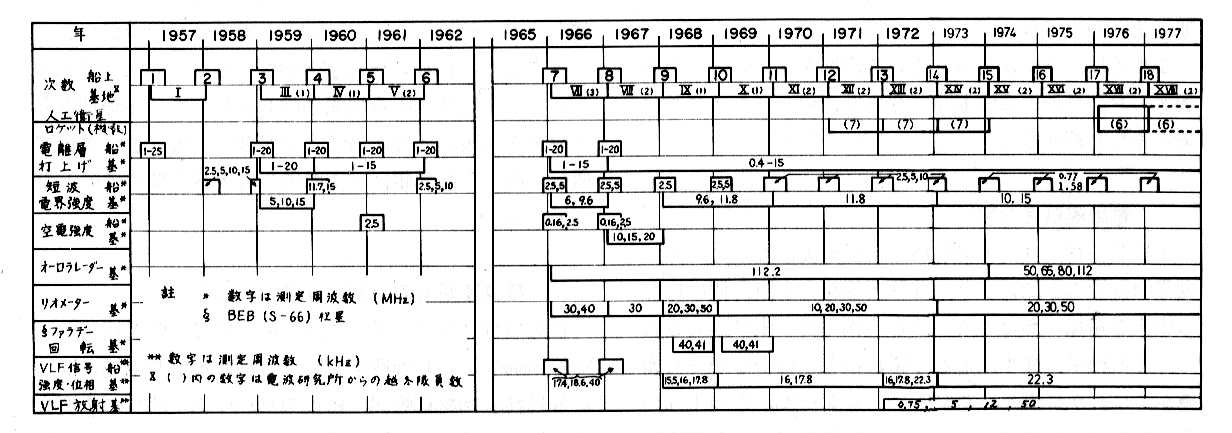
表 日本南極地域観測隊電波研究所関係観測
(1)船上観測
<電離層観測>東京と昭和基地を往復する南極観測船は,
北緯35°から南緯69°におよぶ広大な海域を航行する移
動観測所であり,他部門の大気光,宇宙線と並んで,電
離層打上げ観測,短波と中波の電界強度測定,空電強度
測定を行った。
周波数が変化するパルス電波を打上げて電離層からの
反射を測定する,いわゆる電離層観測の目的は,電離層
の地理的分布,特にF2層の赤道異常と呼ばれる現象
(磁気赤道上で電子密度が減少し,その南北約10°の緯
度上で増加し,その結果双峰型の緯度分布となる)の確
認と発生機構の究明であった。合計7回の往復で測定さ
れた緯度分布は,陸上の電離層観測所のデータを統計し
て得られたものよりはるかに精細であったばかりでなく,
太陽活動による差も明瞭に検出された。この観測に付随
して発見された特異な海上散乱現象は,海洋波浪と対流
圏大気との相乗効果と解釈され,海洋開発に関連して最
近注目されている,電波による海洋波浪のリモートセン
シングのさきがけとなった。
<短波・中波電界強度測定>電波の強さが距離と共に減
少する傾向は,電離層内で受ける吸収,反射回数,大地
の条件等に支配される。従ってこの距離特性を測ること
が,伝搬機構を解明する手がかりになるのであるが,現
実にはさほど簡単に測れるわけではない。船舶を用いた
移動測定は,距離特性を測定するための有効な手法の一
つであり,本項目の目的もそこにある。
短波電界強度測定の結果によれば,夜間にD領域が消
滅しても,昼間の約1/100の密度で残存するE領域の電
子が電波に吸収を与え,その結果特に短波帯の下限近く
では,電界強度が大きく低下する。南極船上観測で発見
されたこの夜間吸収は,国際的にも認められるところと
なり,CCIR(国際無線通信諮問委員会)の電界強度
計算法に取り入れられている。短波電界強度測定は太陽
活動の1周期を越え,充分実用に役立つ成果もあがった
ので,第15次観測から中波測定に切りかえて,国際的な
中波放送の技術基準に資するよう,観測と研究を継続し
ている。以上のようにこの項目は,研究観測としては最
も息の長い項目となった。
(2)基地定常観測
<電離層観測>昭和基地での電離層観測は,超高層物理
関係の項目の中でも,最も基本的かつ重要な観測項目の
一つであり,定常観測として第3次観測以来引続いて実
施されている。その観測結果は誰でも容易に利用できる
よう,電離層状態を表わす約10のパラメータに変換され,
印刷配布されている。昭和基地の電離層データが,直接
又は間接に極地方の超高層物理学の進展に寄与している
ことは疑いないところであるが,ただこの方法の難点は,
D領域の異常電離による吸収を受け易い周波数帯(0.4~
15MHz)を用いているため,最も情報の欲しい極域じょ
う乱時に,全然反射波のないいわゆるブラックアウトの
状態に陥ってしまうことである。
<リオメータ観測>この欠点を補うために登場したのが,
VHF帯の銀河電波を受信して,僅かな吸収量の変化から
じょう乱(D領域異常電離)の程度を知るリオメータ法
である。この項目は再開後の第7次観測から追加され,
第9次観測からは定常観測としての整備が行われ,以後
3周波数で観測が継続されている。
<オーロラレーダ観測>もう一つの定常観測項目は,
VHPレーダによるオーロラ観測である。極地の空を彩
るオーロラは,光の現象であるが,電波によっても,天
候,昼夜の別に左右されることなくその存在を知ること
ができる。このオーロラレーダ観測は,北極圏ではすで
にIGY以前から行われていた。しかし南極圏では前例は
なく,我が国としても南極観測発足当初から,初名乗り
をあげようと張切っていたものである。こうして56MHz
のオーロラレーダは実際に製作され,第2次観測(1957年)
に東京を船出したのであるが,残念なことに遂に昭和基
地の土を踏むことはできなかった。詳細は割愛して,こ
の幻のレーダの遺志をつぎ,初めて昭和基地から112MHz
のオーロラ探測の電波が発射されたのは,第7次観測隊
の時(1966年)である。その後第15次観測から,オーロ
ラからの反射の周波数特性を測るため, 4周波を順次発
射できるオーロラレーダ2号機が運用を開始した。これ
までの観測から,オーロラ反射の日変化,季節変化,出
現の方位等の諸特性が次第に明らかにされてきたが,今
後更に反射領域の移動に焦点を絞りながら,ロケット,
人工衛星との立体的観測を行うため,来るべき第19次観
測からドップラ測定装置を付加する予定である。
(3)基地研究観測
<短波電界強度測定>昭和基地における短波電界強度測
定は,電離層観測や外国基地及び日本との通信連絡を支
援する意味で欠かせないばかりでなく,極地帯及びオー
ロラ地帯を経由する短波通信回線の設計と運用にとって
も重要なので,定常観測に準じて行ってきている。一般
に中・低緯度の短波通信では,F層が主役を演ずるが,
高緯度通信ではスポラディックE層を介する伝搬モード
が主になること,また短波の高周波側では地球裏廻り伝
搬路の寄与も見逃せないこと等が,一連の解析から判明
した。
<空電雑音・電波放射の観測>無線通信に障害を与え,
また回線設計に際して考慮しなければならない要素の一
つに雑音がある。電波雑音の中で外来雑音について考え
ると,VLFからHF帯にかけて最も卓越しているのは,
雷を起源とする空電雑音である。空電は熱帯地方で最も
強勢であり,それが電離層伝搬した結果として高緯度で
受信される時には,強度は極めて小さくなる。このよう
に昭和基地では空電は少い代りに,雪嵐の際に発生する
沈降雑音とか,電離層内部又はより上方の空間に起源を
もつ雑音成分が存在し,それらが時には非常に強くなる。
実際に通信及び観測に妨害を与えるのは,前者の沈降雑
音であるが,一方後者の電離層内部で発生する雑音は,
次にのべるオーロラの発光(電離圏のじょう乱)と関連
して非常に興味深い。
すなわち第3次観測の際に,オーロラに向けたパラボ
ラアンテナに3000MHzの受信機を接続したところ,オー
ロラ活動とよく対応する電波雑音を検出した。このマイ
クロ波帯の雑音は,オーロラ発光部に存在する高密度の
電子の振動の現われと解釈される(電通大芳野氏の研究)。
その後第8次(1967年)観測の時に,HF帯(10,15,
20MHz)で電波雑音の観測を行ったところ,オーロラに
伴う電波吸収の異常増加(リオメータ)並びに地磁気変
動が起った時,それらによく対応した雑音強度の増加を
検出した。ここで非常に興味があるのは,雑音の異常増
加の開始時刻が,他の関連現象より平均的に1時間程度
先行することである。この事実は,入射粒子流のエネル
ギー分布と関連して,一連の極圏超高層現象を解く重要
な鍵を握っているように思われる。
磁気嵐時に発生するVLF帯の電波放射も,上述のオー
ロラ雑音と一貫した現象であり,近時特に力を入れて実
施している項目である。
それにしても,実際には音もなく夜空を一面に彩るオ
ーロラが,よく調べてみたらザーザーと雑音を出し,そ
の上10~70秒間程度の周期の音波も出しているという事
実は,私にとって大へん嬉しい感じがする。というのは,
現に乱舞するオーロラを見ていると音が聞えてくるよう
な気がするからであり,また音もなく光るのは人魂とか
幽霊とか現世のものでない証拠であって,オーロラは厳
然たる科学的事実であるからでもある。

昭和基地のオーロラと林立するアンテナ群
<ロケット観測>超高層物理学は,戦後のロケットの登
場によって大きく進展した。従来の各種の地上観測に併
せて,このロケット観測がもし昭和基地に実現したらと
いう夢は,恐らく南極関係者の多くが当初から心に抱い
ていたに違いない。しかしこれが現実となるためには,
南極という厳しい環境下での発射を含む日本のロケット
技術,人員の制約,輸送の問題等が解決されなければな
らなかった。そして遂に第11次隊の手により,1970年2
月に昭和基地から初めてロケットが打上げられ,第12次
隊からは本格的なロケット観測が開始された。この一連
のロケット計画は第14次観測(1973年)まで続けられ,
合計22機のロケットが打上げられた。IMS(国際磁気圏
観測計画)の1976年から1978年にかけては,それぞれ7,
7,6機のロケットが打上げられる予定である。
ロケットには通常多くのミッション機器が同時に搭載
される。今まで打上げられたロケットの中16機が電離
層に直接関係があり,電子密度と温度,イオン密度,イ
オン組成等の分布をE領域の上部約130㎞に至る高度
範囲にわたって測定した。このうち夜間に測定された電
子密度の高度分布を図に示す。図中の点線(中緯度夜
間の平均的な電子密度分布)と比較して分るように,最
大の電離源である太陽がない時でも,中緯度の約100倍
の電離が維持されていることになり,その電離源(侵入
粒子による電離又は上部からの輸送)の究明が大きな課
題である。ロケット実験の中には,オーロラの中に直接
ロケットを打込み,電子密度の激しいゆらぎがオーロラ
の発光と密接に関連していることを検出した例がいくつ
かある。
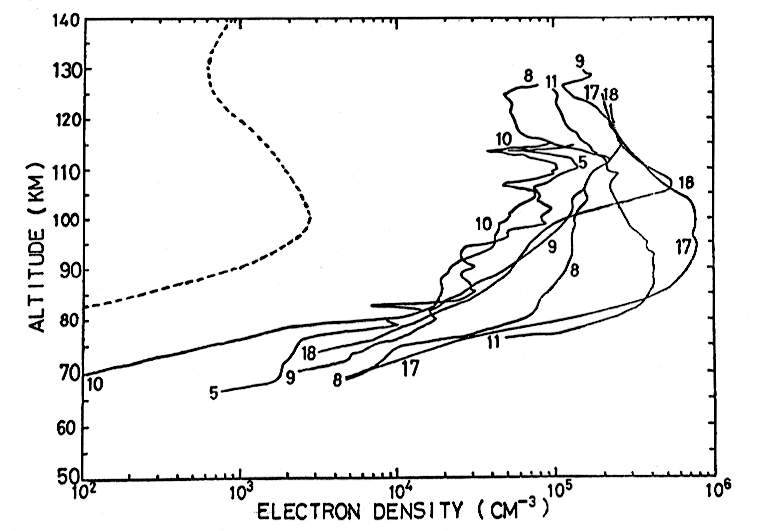
図 昭和基地上空の電子密度分布
実線: ロケット測定(数字はロケット番号)
点線: 中緯度夜間の平均的分布
更に第17次観測から開始した人工衛星電波のテレメト
リ(昭和基地上空を通過する人工衛星により行われる電
離層のトップサイドサウンディング及びVLF放射の観
測)のデータが持ち帰られ,上述の地上及びロケット観
測データと共に多元的に解析される時,未だ例を見ない
ユニークな電離圏研究が花開くことになるであろう。
<低周波電離層観測>極地方で特に重要な下部電離層を
重点的に観測するため,50~2150kHzを発射できる特殊
観測機による実験が,第13次観測の際に試験的に行わ
れた。このように低い周波数では,電力を有効に発射す
るための,ディメンションの大きいアンテナが必要にな
る。短期間ではあったが,高さ360mの崖から展張した
底辺500mのデルタアンテナ,並びに雪面上に張った
半波長ダブレット(全長約750m)を用いて実験を行
い,将来の研究に資する有効なデータを得ることができ
た。
むすび
前掲の表に示した項目のうち,目下解析中のもの(VLF
伝搬),予期した結果の得られなかったもの(ファラデ
回転)等については説明を割愛した。大変皮相的な紹介
に終ったが,本文を通して,当所が南極観測に参加して
以来の20年の歩みを幾分なりとも理解して預けたら幸で
ある。
思いつきの域を出ないが,南極で実施することが望ま
しいと思われる新しい研究テーマを挙げてみる。
(1) すでに一部実施していることであるが,ミリ波から
VLFに及ぶ周波数帯にわたり,電離圏内部から発
生する電磁放射を,発生場所も含めて多面的にとら
える。
(2) ISレーダ(非干渉性散乱レーダ)を設置して,電
離圏全域にわたる測定を行う。
(3) FM-CW方式サウンダを設置して,ISレーダと共
に,特に探測技術に乏しい下部電離層の解明につと
める。
最後に隊員の補充について一言のべる。冒頭に当所か
らの参加者は延べ40人と書いたが,大ざっぱにいって
前半の10年は文部省への隊員の推せんに何の苦労もな
かった。元気な若者が多かったのである。しかし後半に
なって,若者は昔より増えたにもかかわらず,隊員の補
充は可成り困難になってきた。その原因はいろいろある
だろう。しかし私には,端的にいって若者に夢がなくな
ってきたことが真因と思われてならない。南極は確かに
未知の大陸ではなくなってきた。それでも
まだ南極は,公害と過度の情報に打ちひ
しがれている多くの現代人には,想像も
つかない別世界なのである。長い人生の
うちのたった一年,大自然の神秘に触れ,
心の洗濯をしてこようという若者が何故
殺到しないのだろうか。私に申込お断り
の嬉しい悲鳴をあげさせてもらいたいも
のである。
(電波部長 若 井 登)
周 波 数 標 準 部
現在小金井市緑町の当所周波数標準部より発射されて いる短波標準電波JJYは,本年末より電電公社名崎送 信所から送信されることとなり,世界初の無人化標準電 波局の運用が始まることになる。
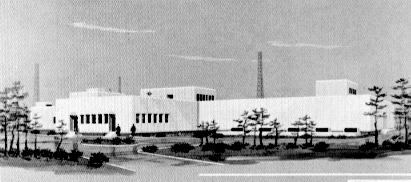
電電公社名崎無線送信所局舎 (写真は電電公社提供)
(正面右側が電波研究所標準周波数局入口)
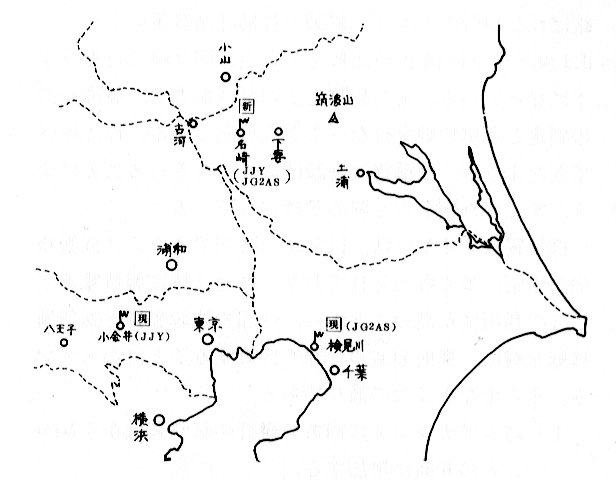
標準電波 新・現送信所の位置
名崎標準局および本所
におかれる主要装置は,す
べて二重化されていて,故障
発生の際には自動的に現用切
替が行われる。特に時刻に関
するものは三重化され,相互
の時刻差(マイクロ秒程度の)
モニタや,後述の計測用計算
機によって,誤った時刻信号
が送信されることのないよう
に切替方式が構成されている。
また停電対策として,名崎標
準局で無停電化されているの
はセシウム原子時計のみであ
るが,すべての標準信号の位
相は,この原子時計の秒パル
スの位相に同期して再起動す
るようになっている。「分」
とそれ以上の時刻情報は,本
所より常時送られるのでいつで
も再現することが可能である。
次に,最も重要な名崎の標準器の周波数と時刻の絶対
値の維持であるが,ここで使用されるセシウムビーム型
原子標準器は,3年間以上の長期にわたり5×10^-12以上
の周波数確度と安定度を持っている。したがって周波数
としては問題ないが,時刻としてはこれでも年間約100
マイクロ秒のずれを生じ得るので無視できない。この他,
発生する確率は非常に小さいが,原子時計自身の故障も
考慮しておかねばならないので,常に本所実用標準主時
計との時刻比較が必要である。しかし,上述の有線回線
を用いてマイクロ秒精度の時刻比較を行うことは不可能
であるから,本システムでは,すでによく知られている
テレビ信号の同期パルス仲介方法を用い,データ回線で
結ばれた両所のミニコン制御の自動計測装置によって,
0.1マイクロ秒精度の比較を一定の時間々隔で行なうよ
うになっている。また故障発生の割込信号で,故障時計
の判定と現用切替を行なうことも可能である。以上述べ
てきたように,標準電波施設は全く一新されることにな
り,すでに外国からも関心が持たれている。
標準電波JJYには,以前から時刻アナウンス回数増
加の希望が多く寄せられており,最近は特に報時電波と
しての利用度が高いことから,今回の施設整備と送信所
移転を機に,発射形式の一部を変更することになってい
る。その主な点は次の通りである。
1) 時刻アナウンスの回数を現行の毎時2回から10分
ごとの6回に増加する。
2) 1000Hzによる変調の有無を現行10分ごとから5分
ごととし,上記1)と合わせて5分ごとの時刻判
断を可能とする。
3) 停波時間を変更し,外国標準電波(BPV)との
重複をさけ,利用効率を高める。
4) 8MHzは現在の500Wから2kWに増力する。
なお,分・秒信号については現行どおりとし,変更を行
わない。
またJG2AS(40kHz)についても,「分」予告のため
毎分59秒に100ミリ秒のマークを挿入するほか,発射時
間の延長についても検討中である。
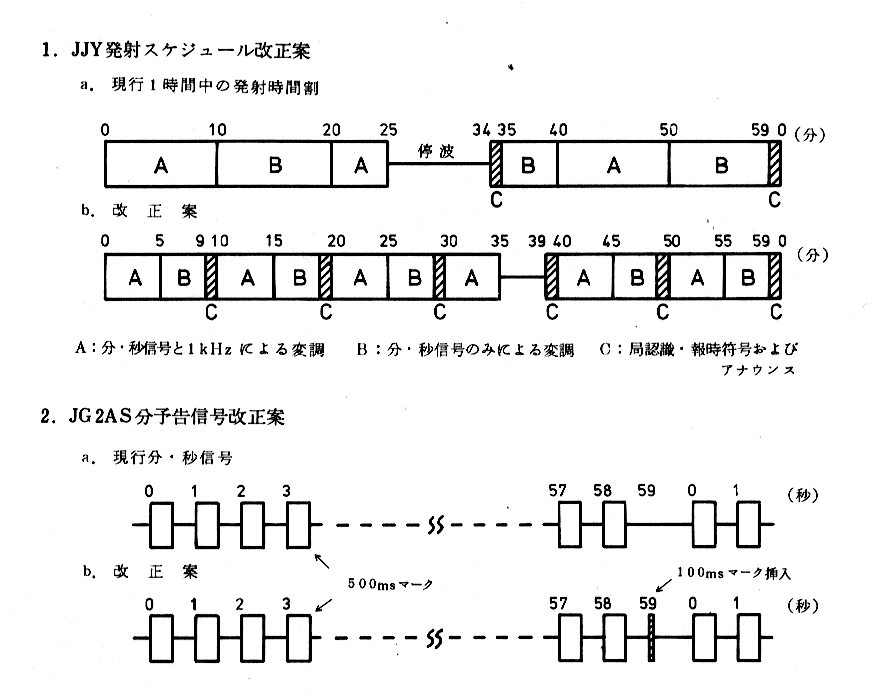
図 標準電波発射スケジュールの改正
送信所移転による電界強度分布の変化については,関
東以遠では,JJY,JG2ASともに改善はみとめられ
ても,悪化することはほとんどないと思われる。しかし
東京都内やその周辺地城では,電波到来方向の変化は致
し方ないとしても,地表波が強いJG2ASを別として,
ある程度の電界強度低下が予想される。また新送信アン
テナが,2.5MHzではλ/4の垂直接地型,10,15MHzで
はλ/2の垂直ダイポールでいずれも偏波面は現在と変ら
ない。しかし,5,8MHzについてはλ/2の水平ダイポ
ールとなって偏波面も変るので,近距離では受信アンテ
ナの再検討も必要となろう。都内では従来から雑音の問
題もあるので,周波数較正にはこれを機会に一層長波標
準電波の普及をはかりたい。また将来はVHF,UHF
帯の利用などによる周波数及び時刻の標準供給を考える
必要もあろう。
(標準電波課 主任研究官 小林 三郎)
五十嵐 隆,有賀 規(通信機器部)
はじめに
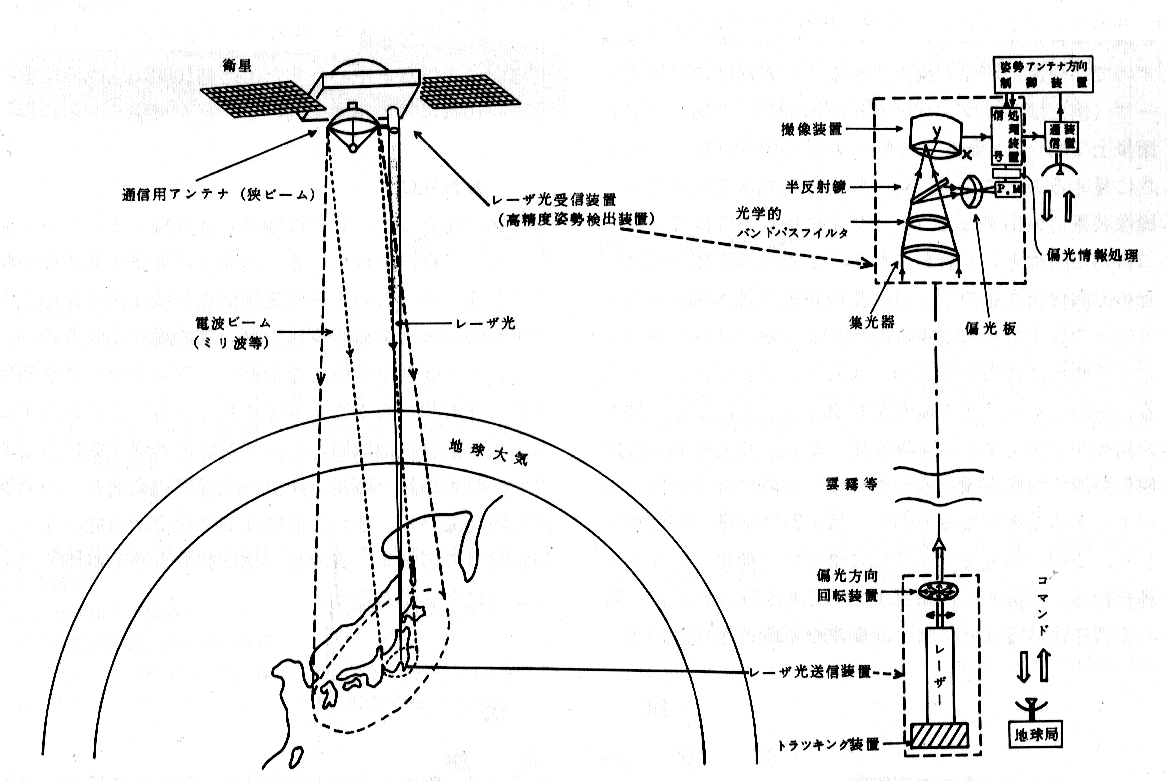
図 レーザを用いた衛星アンテナの高精度方向制御システム図
レーザを利用した姿勢決定システム
地球上のある点に衛星アンテナの方向を高精度で向け
ておく目的のためには上述のセンサを利用するのは適当
でないので,レーザを利用して姿勢を決定しアンテナの
方向制御に役立たせるシステムが新しく考案された。シ
ステムの概略を図に示した。直線偏光したレーザ光を地
球局から送信し,これを衛星で検出し,姿勢を決定する
方式である。衛星上でレーザ光の送信点を見ると星と同
じように点となって見える。光学的バンドパスフィルタ
を通せば背景光が除去されてレーザの光の波長のみを通
すので,昼夜の別なく検出できる。5W程度の可視光レ
ーザ(例えばアルゴンレーザ)が送信された場合は静止
衛星上で約-1.5等星(火星と金星の中間程度)の明る
さに見えることになる。レーザ光を集光器で収束させ,
撮像装置で検出すると,レーザ光送信点の像は点となり
二次元の座標として表わされる。この点の座標から送信
点の方向が決まるので,逆に受信装置の基準軸と送信点
方向とのなす角を決定することができる。これでロール,
ピッチ両角に相当する二つの回転角が決まったことにな
る。さらにレーザ光の偏光を利用することによって残り
の回転角を決定する。直線偏光したレーザ光を偏光方向
回転装置で偏光方向を回転させると同時に偏光方向が地
球上のある基準となる方向に一致した時基準パルスを出
して,このパルスをレーザ光に乗せて(簡単なパルス変
調を行う)送信する。衛星上で偏光板を通った光は一種
の変調を受けることになり,簡単な正弦波となるのでこ
の正弦波と基準パルスの位相差から,衛星と地球局を結
ぶ方向の周りの回転角(ヨー角に相当する)を決定するこ
とができる。伝搬時には大気の擾乱によって強度が変化
するので、これらの影響を等価的に取り除く方法も考えら
れているが,ここではこのような詳細については省略する。
このようにして,この方式では一点からの電磁波の送
信によって姿勢の三要素を決定し,一意的に姿勢を決定
することができる。一意的に姿勢を決めることは大きな
意味をもっている。例えば最も精度のよいスター・ドラ
ッカーの場合でも,ある目的とする星の方向へ光学的ア
ンテナを精度良く向けることができるが,その星の光を
もとに,その星の周りの,指定された任意の方向へ向け
ることは不可能である。これは姿勢が一意的に決定され
ていない(ヨー角が不定)からである。これに対し,こ
の方式ではレーザ光送信点の周りの任意の点にアンテナ
を向けることが可能である。この方式は種々の軌道衛星
に適用できるが,いつも地球の同じ面と向い合っている
静止軌道衛星には最適と思われる。
この方式による姿勢決定精度は,ロール,ピッチ角に
ついてはスター・センサと原理的には同じである。ただ
地球大気の影響を受ける分だけ悪くなるが,それでも10^-4
ラジアン(約4万㎞離れた静止衛星の場合,地球上で4
㎞となる)以内の精度を得るのは容易である。ヨー角決
定の精度は約10^-2ラジアン(地球上,送信点から100㎞
離れた点で1㎞,1000㎞離れた点で10㎞)が見込まれて
いる。従って静止衛星上でのアンテナの方向の制御は,
地球上の送信点を中心とした半径約1000㎞以内の任意の
点に約10㎞以内の精度で向けることが可能である。
おわりに
実験に先立って,雲の影響等も計算機シミュレーショ
ンによって検討されている。地球上の風景が見えない状
態でも狭いビームのレーザ光送信点の像は消えないこと
が確かめられ(ある程度以上厚い雲の場合,現在のレー
ザ出力では受信不可能となるが),ランドマークを利用
するより有利であることも示されている。このシステム
は,また衛星-地球間のレーザ通信の基礎実験にもなる
ので,将来衛星-衛星,衛星-地球間の光通信への発展
性も備えている。さらに高精度姿勢決定が可能になれば,
静止軌道での気象,資源等の地球観測も高分解能で行え
るようになるであろう。
VLBI国内基礎実験
鹿島支所第二宇宙通信研究室では,1月27日から2月
5日まで,電電公社横須賀電気通信研究所の協力を得て,
VLBI(超長基線電波干渉計)国内基礎実験を行った。その
目的は同基礎実験システムの確立,静止衛星(ATS-1号
及びインテルサットⅣ号)の測距及び鹿島と横須賀間の
基線長を10m以下の精度で決定することである。
特殊ラジオメータの絶対較正
電波部電波気象研究室では,1月24,25日,本所から
北北西2.3㎞の地点で,金属球を吊したバルーンを揚げ,
2号館屋上に設置した特殊ラジオメータの較正実験を行
った。
沖縄電波観測所新庁舎落成式
当所沖縄電波観測所の移転については前月(第10号)
に紹介したが,その後の諸施設整備完了に伴い,2月2
日に地元官公署代表をはじめ60余名の参列を得て落成式
が挙行された。同所は太平洋を望む海抜140mの丘にあ
り,敷地面積6,600㎡,2階建庁舎延面積596㎡,アンテ
ナ鉄塔高35mである(写真)。

ヘリコプターによるETS-Ⅱ用のアンテナ
特性測定
衛星研究部通信衛星研究室及び鹿島支所第一宇宙通信
研究室では,技術試験衛星Ⅱ型(ETS-Ⅱ)によるミリ
波等の伝搬実験を行うために鹿島支所に建設済みの直径
10mパラボラアンテナの特性測定を1月12,13日,ヘ
リコプターを用いて行った。ヘリコプターにはビーコン
発振器・アンテナ等の機器を搭載し,鹿島地上局から南
方約30㎞,高度1.5㎞の空中に静止させて較正塔に見たて,
同10mφアンテナの放射特性を測定した。
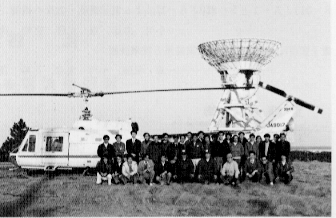
実験を行ったアンテナ(後方)、ヘリコプターと参加者
南極関係文部大臣表彰
1月29日南極地域観測統合推進本部主催により,南極
地域観測20周年記念式典が行われ,当所電波部の大瀬正
美主任研究官が,多年にわたり南極観測に尽力したこと
に対し,功労者として文部大臣から表彰された。