

電 波 部
はじめに

9B型イオノゾンデ
イオノグラム
一種のパルスレーダであるイオノゾンデの一般的運用
では鉛直投射だけではなく斜方投射も可能である。いず
れの場合でも得られる情報は基本的に電波の位相と振幅
の変動,つまり電波の通路長(あるいは伝搬時間)と減衰
量(あるいは電界強度)である。パルス電波の掃引周波数
を横軸に,見かけ伝搬距離を縦軸にとった周波数-見か
け距離の関係を表した記録図がイオノグラムである。
図1は国分寺において得られた1979年4月28日9時45分
のイオノグラムである。F2層の正常波,異常波モード
が1回及び2回反射トレースに現われている。E層トレ
ースは正常波1回反射のみである。またEs層はhタイプ
であり,正常波,異常波の1回及び2回反射がみられる。
イオノグラム作成には周波数掃引に同期して伝搬所要
時間(見かけ距離)をブラウン管に表示し,それを時々刻
々周波数に対応させて記録する方式とメモリースコープ
に周波数と時間の関係を表示し,それをコマどりする方
式とがある。記録媒体としては写真フィルムや磁気テー
プが使用されている。こうした資料形式は使用目的や管
理方法の如何によって選択されるべきである。短期予報
などの実行には即日(即時)的なデータ利用が前提になる
から磁気テープが便利であるし,長期予報に対しではか
えって写真フィルム等のハードコピーが有利であろう。
現行では写真フィルムを基本とし,イオノファックスあ
るいは磁気テープを補助的に用いている。この形式はま
たデータ処理のあり方を著しく規制することになる。と
くにコンピュータを利用する自動処理に対しては入力媒
体の形式が事の成否を半ば決定してしまう。イオノゾン
デ運用からイオノグラム処理までを体系的に維持するた
めトータルシステムの半自動化あるいは全自動化をたえ
ず推進させてきたが,その方向づけは電離層観測の目的
がその時々に明確でなければ意味のないことである。
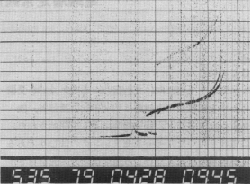
図1 イオノグラム(国分寺:1979年4月28日)
電離圏の観視(モニター)
電離圏は天然あるいは人為の電波が交錯する場であり,
電波の発生源や伝搬媒質の分布に応じて時間的,場所的
に変動している。媒質の分布状態は電離層定時観測によ
って把握され,発生源の分布状態もしくは伝搬状況は電
波監視によって掌握されるべきであろう。実務としての
可能,不可能は別としても,通信,放送におけるリアル
タイムの交信規制が必要と思われる。その場合の規制原因は
自然電波(空電雑音,宇宙雑音など)であり,規制対象は
人工電波(位置,時刻などの通報電波)である。こうした
電波の活動は電磁環境の様相を示唆するものである。電
離圏の観測は電離層の構造及び機能について行うべきで
ある。したがって電離層に関する特性値マップとしては
電子密度,電子温度あるいは地球磁場,空電雑音などの
マップを用意すべきである。ふつうのイオノゾンデの場
合,観測量は伝搬経路に分布する物理量(電子密度,地球
磁場など)の積分として与えられるが,非干渉散乱レーダ
によれば微分的観測が可能になる。また従来の電離層観
測は静的な方法(観測が対象に影響を及ぼさない)であ
るが動的な方法(観測が対象に変化を起こしうる)によ
れば対象領域をさらに拡大することができる。電離圏の
物理機能を示す伝搬パラメータにはF2,F1,E,D層や
Es層に関するものがある。図2は南極昭和基地で観測
された1976年12月の電離層の見かけ高さ及び突き抜け周
波数の月中央値の日変化を表わしている。中低緯度におけ
る変化とは異なって,E層が夜間に,またEs層が1日中
出現している。夏季の特徴として日中のF層に層の分裂
が見られる。
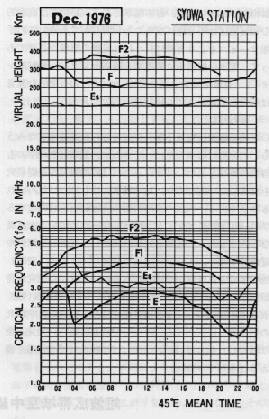
図2 みかけの高さ及び突き抜け周波数の月中央値の日変化(南極
昭和基地,1976年12月)
電波伝搬の予報
通信及び放送を効率的に維持することがソフトウェア
技術としての電波予報に課せられた役割である。そのた
めに電離層観測の成果が十分に利用される。電波情報の
あり方,つまり予報業務におけるソースデータの種類や
処理及びオブジェクトデータの特性や用途などがサービ
ス形態を決めることになる。すなわち,ある時刻,回線
におけるある周波数帯電波の伝搬状態がどうであるかを
ある論理に従って予測することになる。実際上は長期予
報(予測期間は1か月以上)と短期予報(予測期間はおよ
そ1週間以下)の別がある。ふつう予報の有効性を保持す
るためには予測期間の長いものほど前もって発令しなけ
れば意味がない。一方,世界的予報あるいは地域的予報
(短波に対しては1ホップ領域10^7㎞^2の範囲)の使い分け
が問題になる。電離層によって何等かの影響を受ける
電波(電離層を回折あるいは透過する)はその周波数帯
(VLF~VHF帯)によって異なる予報を必要とする。例え
ば,船舶通信の不能,衛星通信電波の減衰,テレビ電波
の混信,航法電波の乱れなどはそれぞれの伝搬特性によ
って障害の質や量を異にする。したがって一般的に予報
は時刻別,回線別,周波数別,方式別に発令されること
が望ましいが,その一部分の要望しか満たしえないのが
現状である。電波予報が存在意義を持ちうるのは現実の
通信・放送システムのハードウェアが技術的あるいは経
済的に満足すべきものでないからであって,それが統計
的に予測される事態に適応しきれない部分を補強しうる
からである。電離層回線(HF帯)の予報は経済面でなお
意義があるし,また衛星回線(VHF帯)では技術面で,ま
だ意味がある。実際の業務として行われている短波回線
の長期予報は3か月先における1か月間の平均的な伝搬
状態を予測するものであり,通信可
能な時間帯や周波数帯をそれぞれ特
定の時刻や周波数に関して指示する
ものである。図3は1979年7月に
おける東京-昭和基地回線の予報で
ある。この回線には東京における回
線方位が南西向き205°の表廻り(大
圏距離14,000㎞,図中(a))と北東向
き25°の裏廻り(大圏距離26,000㎞,
図中(b))が利用される。同図におけ
る太線はMUF(最高使用周波数),細
線は送信出力が番号順に10W,100W,
1kW,10kWのLUF(最低使用周波数)
である。通信可能な時間帯は太線が
細線より上方にある場合で,その2
線間の周波数が使用可能になる。送
信出力が1kWの場合,日本標準時刻7~15時では直接的
な短波通信は不可能になることが明らかである。この予
報サービスをより有効に行うには組織の整備が必要であ
って,電波伝搬情報に関連する観測センター,資料セン
ター,通報センター及び予測センターの有機的な運営
は将来の予報システム維持に不可欠であろう。
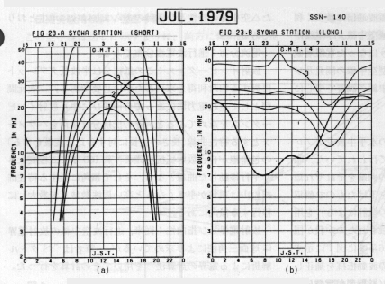
図3 1979年7月の東京-昭和基地回線の予報
おわりに
電離層観測は電波予報(短波回線の設計運用を含みう
る)の分野に応用を見出してきたが,電離層物理学にも
当然の寄与を果たしてきた。これは応用研究が基礎研究
を育成した一例であり,地球科学にはしばしば認められ
る事柄である。天然の資源利用や災害防止を目的とする
フィールドサイエンスがラボラトリーサイエンスとは異
なる点でもある。電離層通信に関連して電離層物理学や
電離層予報が,また宇宙通信に関連しては宇宙(空間)
物理学や宇宙予報が想定されうるが,そうした研究業務
が実際に活動するか否かは技術的,経済的状況に強く
依存するであろう。実利用と疎遠になった地球科学研究
の例は過去に求めうる。そうした時期に新しい知見を余
り増やしこそしないが,かえって学問としての体系を備
えることができた。
人間社会は環境,食糧,人口,エネルギーのエコロジ
カルな流れの中で外界と均衡を保っているように見える。
この観点からもう一度電離層観測をふり返ってみる時,
その実用価値を追求することはまだしも,その評価を急
ぐことは危険であろう。地球科学としてみれば,高々30
年間の歴史はその有意性を表現するには十分といえない。
電離層は単に通信,放送のメディアとしてではなく,電
波によるリモートセンシングやリモートコマンディングの
自然実験室としての新しい役割を持ちうるであろう。ま
た学問としてよりむしろ技術としてのレーダシステムを
開発することが各方面における期待に応えることになろ
う。電離層観測から電波予報への道は一つの明るい街道
であったかもしれない。別の街道へ移行するバイパスを
発見するためには,よく言われるように,フィロソフィ
ーの確立が電離層研究に恐らく必要であろう。とくに資
源や災害が天与のものから人為を帯びたものに変わる時
代では従来のエネルギー論的自然観は必らずしも万能で
はない。将来はエントロピーを同じ位に重視する自然観
が求められなくてはなるまい。
(電波予報研究室長 前田 力雄)
井 上 良 助
はじめに
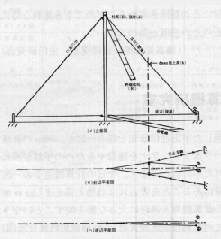
図1 電離層観測用Δ型空中線概観図
伝搬実験用傾斜V型空中線
この空中線は図2に示すように,前方に傾斜させた進
行波V型空中線で,昭和29年頃筆者により伝搬実験用簡
易空中線として開発されたものである。その大要を次に
示す。
電流分布:進行波電流分布である。
放射インピーダンス:本空中線の放射インピーダンス
を計算する場合は三次元問題における“相互放射インピ
ーダンスの一般式”を必要とする。それを逆起電力法に
よって求めると複素指数積分関数(これは実数部が複素
余弦積分関数及び虚数部が複素正弦積分関数に分けられ
る)と減衰指数関数(分母に変数をもち,指数部が負号
である)を含む四つの項からなる相当複雑な式である。
当時適当な計算機がなく計算することができなかった。
複素正弦及び余弦積分関数:この積分関数の値は図式
並びに数値積分及び級数展開などによって概略が計算さ
れているが,筆者は複素積分を検討の上,級数展開式に
ついて昭和45年頃詳細な数値解析を試みた。その結果変
数の実数部による減衰正弦波的な最大点にそれぞれ鞍部
点をもち,それが虚数部の増大と共に双曲線的に大きく
なることが明らかにされている。
放射電界及び指向性:前述の計算法によってその放射
電界を求めてみると,傾斜により指向性が下向きになり,
素子電流の垂直成分のため傾斜角(α)が30°を超える
と指向性の高角度側に拡がりを持つようになる。その度
合は傾斜につれて大きくなる。
利得:放射抵抗を600オームとして相対利得を求めて
みると傾斜角(α)12~17°,交角(β)60~65°におい
て最大利得はほぼ6dB程度で△空中線に比べてやや小
さい値を示している。
設計:それらの特性から近距離用(周波数4~15MHz,
傾斜角12.5°,交角55°,柱高約16m)及び遠距離用(夜間
波に対し,周波
数4~9MHz,
傾斜角17°,交角
65°,柱高約58m
及び昼間波に対
し,周波数8~
23MHz,傾斜角
12.5°,交角65°,
柱高約18m)の
ものが設計され
ている。なお,
斜辺は複線によ
る波動抵抗の補
正が施してある。
この空中線は柱が一本で足りる簡便さから伝搬実験用
の外,国内連絡用としてKDD及び天文台などに利用さ
れている。
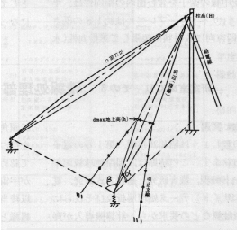
図2 伝搬実験用傾斜V型空中線概観図
電測並びに電波監視用対数周期型空中線
この空中線は始めTVの受信に用いられており,その
帯域特性は極めて広い。電測用の垂直偏波対数周期型空
中線が平磯支所に建設されたのは昭和44年である。その
後,無線局の増大に伴い電波監視用空中線においても広
帯域特性が要求されるようになり近畿電波監理局(岩岡)
に同様な対数周期型空中線を建てて運用に入っている。
対数周期型空中線は不等長の半波長ダブレット空中線
を不等間隔に垂直面内に一定の条件に従って排列してお
のおのに給電した縦型空中線列である。そして最長及び
最短素子できまる周波数帯域内において,測定周波数に
共振する素子を中心に放射に寄与する一つの活動素子群
(長さによって導波,共振及び反射動作を行う)が形作ら
れ,測定周波数が変わるにつれて,帯域内を移動して極
めて広い帯域特性をもつものである。この調査は平磯支
所の依頼により行われ,次のような放射特性をもつこと
が明らかにされた。
電流分布:これを厳密に解くのは極めて困難である。
荒い近似として単一正弦波分布が考えられるが,実測値
に近い二項分布,更に近似度の高い三項分布(連立積分方
程式を代数方程式に直して解く)などが求められている。
入力アドミッタンス:帯域内のコンダクタンスは約200
±40(ミリモー),サセプタンスは約0~50(ミリモー)程
度で帯域外特に高域において大きな変動が見受けられる。
放射電界及び指向性:前述の電流分布による各素子の
電界を位相を考慮して合成すれば放射電界を求めること
ができる。その一例として10素子八木・宇田空中線に比
べて12素子の本空中線の素子を含む面内の指向性は,半
値幅で約2.3倍広く,サイドローブレベルは約1/6の低さ
である。実際には四方向に放射状に架張して無指向性(水
平面内)として使用されている。
利得:放射抵抗が計算されていないので正確な相対利
得は求められていないが,モデル及び本空中線の実測パ
ターンから近似的に推定して15素子で約10dB以上の利
得が得られている。
設計:一応資料による設計はできるが,なお,垂直偏
波対数周期型空中線の基本的な放射特性の解析と共に最
適設計に対する検討の余地が少なくない。
おわりに
以上述べた本広帯域空中線の開発並びに調査において
感じた点などを付け加えて本稿の補足としたい。
△空中線について,素子の交点における相互放射イン
ピーダンスは始め離しておいて計算し,その導体の半径
まで近付けた極限として求めること及び複線による補正
式は各導体が独立にあったものとして求めたものでテー
パー整合の考えから近似的に用いられることは注意を要
するところである。なお,放射特性の広帯域化及び指向
性の尖鋭化などが強く期待されている。
傾斜V型空中線において,複素正弦及び余弦積分関数
を調べているとき,昭和26~27年頃日本において計算
(Numerical Computation Bureauにおいて)した本積
分関数の一部がソビエト連邦の関数目録書に載っており
統計数理研究所の書庫の片隅からようやく見付けること
ができた。我が国の計算(手廻し計算機による)もさる
ことながら,日本で探すのに困難なものに対するソビエ
ト連邦の綿密な調査には少なからず驚いた。この積分関
数は複素変数のため計算量が多く,有料計算は経費上,
真空管式(UNIVAC-60,簡易保険局所有)及びリレー
式(富士通,池田氏)は計算速度の上から計算はできな
かった。しかし,現在は放射特性の計算のサブルーチン
として容易にその数値を求めることのできる便利な時代
になったものとの感概が極めて深い。
(調査部国際技術研究室 主任研究官)
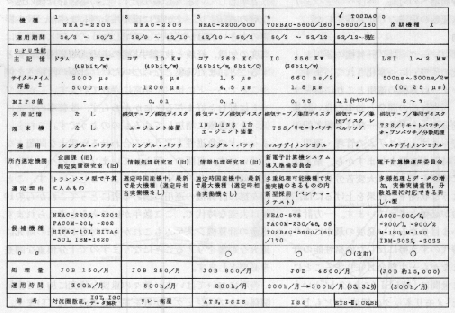
表 電波研究所電子計算機導入経過
昭和48年度からは我が国初の実用衛星ISSの計画へ向
け,新しい計算機導入の仕事がスタートし計算機研はそ
の中核となりました。この計画は,ISSの1周回約1メ
ガバイトの大量データを遅滞なく処理し,電離層世界地
図,雷雑音世界分布など種々の解析を行いかつ衛星の運
用計画(軌道計算も含む)も立てる約20万ステップにおよ
ぶ大型ソフトウェアを実行し,さらに一般科学技術計算
は勿論続行できるこ
とが前提でした。こ
のため情報処理部の
他,新電子計算機導
入委員会という形で
広く各部,支所の協
力を求めました。こ
のシステムは昭和49
年度工事,50年3月
稼動を開始していま
す。新システムは本
格的で定評のある
OS機能を持ったもの
でしたが,ユーザー
の利用し易い端末整
備は開発的な仕事と
して急速な計算機周
辺の発達を先取りし
ながら進められ,51
年末にはTSS(全支所・観測所を含む)端末,遠隔集中処
理端末及び異種計算機間高速データ伝送処理網(CCC)
が完成し,ISS打上げに万全な態勢が整いました。CCC
には音声研究室にあるPDP11/45システムも接続されてい
ます。ISS「うめ」は不幸にして本格的利用に至らず不具
合となり,計画は2年後にずれることになりました。「う
め」は計算機システムヘの貴重な教訓として外注ソフトの
運用並びにその改訂の難しさを教えてくれました。一方
新システムのTSS端末利用が徐々に盛んになる中で,漢
字システムの開発が開始され52年度でほぼ実用化でき,
53年度末にプロジェクト項目を終結しました。漢字入出
力の広範な試用と漢字システムを導入すべしとする潜在
力が大いに期待されるところです。また分散処理のため
のネットワークの調査が開始されましたが,52年度以降
別の構想の下に情報処理研究室で発展しています。また
42年度のところで述べたプロジェクトの(2)が(1)に統合さ
れたのもこの時期です。
この間に研究室長も第2代北条尚志氏(44年10月~50
年7月),第3代柴田久氏(50年7月~52年7月)と代わ
りました。その後計算機システムは52年度に処理速度向
上,能力増強のためハードウェア,ソフトウェアの増設
及び改訂が実施され,現用の形となりました。改善実施
後のシステムの稼動分析によって,将来の利用増への対
応を考え,優先度適用実験による有効利用を計ること,
またISS-bの打上げ成功,ETS-Ⅱからのデータ解析な
どによる計算機稼動時間増への対処,外注ソフトウェア
への対応から夜間無人運転の促進などが急務でした。
現状と今後の方向
当研究室の現在のプロジェクトは,「計算機の運用およ
び計算機使用の能率化の研究」に一本化されています。
細目には研究所のセンター計算機の運用どこれに附帯す
る様々な仕事の他に,利用技術の開発と効率の良い計算
機の利用のための稼動分析がありその一部は月報年報の
形で利用者に周知しています。システムの管理・運用・
指導には相当な人手と時間を必要としますから,室員は
研究者としての仕事に時間を割くのに大変苦労します。
長期にわたってこのような状況下で成果を上げるには,
他の部門と異質な努力が必要と考えています。一方計算
機を取り巻く情勢はいま目まぐるしい発展の最中にあり,
一寸の油断のため,時代のすう勢に反した価格性能の計
算機システムを苦心しながら一生懸命お守りすることに
なりかねません。いま世間に「超LSIインパクト」という
言葉が盛んです。また「メモリネックの解消」などもよく
聞かれます。いまこれらの持つ意味を真剣に考える時に
来ています。
電波研究所の計算機システムには主記憶装置として約
1メガバイトが実装されていますが,利用者が痛感し運
用者が困っていますように十分なものではありません。
CPUについても同じです。現在,メモリの集積度は年々
2倍の上昇,プロセッサのそれは2年で2倍の向上を続
けていますが,この傾向から見ますと1980年初頭にはメ
モリについては256キロビット/チップ,プロセッサでは
語長32ビット/チップが開発されると予測されます。開発
時期は問題があるにしても解決は意外に早いので1985年
過ぎには実用機が現われるでしょう。これは米国での予測
を基にしていますが,我が国も強力な国策に支えられほ
とんど遅れなしに開発が進んでいますから必ず実現する
と考えられています。現時点におきましてもメモリを例
にとれば,現用のメモリが占有している空間7m^3に少な
くとも20倍に近いメモリが収容できるようになっていま
すから,1985年を過ぎる頃には,メーンフレーム(CPU,
メモリ,I/O)は僅か数チップの超LSIとなってわれわれ
の前に現れるでしょう。こうなればいまの能力を持つ計
算機は周辺装置を除いてパーソナルコンピュータ(PC)
様となり,値段も30万円位になるかも知れません。
まさに大きなインパクトで,この様な事態ではセンタ
ー計算機の性格も大きく変わり,各部門毎に持つ高性能
なPCを色々な形で結んでデータセンター,科学用超高
速計算機センタ,大量入出力センタ的なものになるだろ
うと予想している人もあります。この場合計算機の色々
な形のネットワークが更に重要性を増しますが,最も影
響の大きいのはソフトウェアでしょう。ソフトの開発は
高度の知識,経験と技芸的才能のある人の集団を必要と
すること,また具象とならないだけに評価の困難さを伴
うことでハードに比べて非常に遅れています。しかもソ
フトは好むと好まざるとにかかわらず,改善率の非常に
低いまま急激に増加してくるもののようです。これをい
まハードの急進性とどうかみ合わせるか重大な問題とな
っています。打開の一策としていまソフトのハード化が
進む傾向があり一部実用化されようとしています。こと
程左様に計算機の運用に携わる者にとってこれからの10
年は大変な時代で,ここ数年が山であると考えられます。
当所の計算機システムもこれからの対応が将来の研究に
重大な影響を与えることになりますので十分慎重な調査
を必要とします。
当所においてはいま,数々の重要な研究に加えて衛星
関係の大プロジェクトが軒を並べて進められています。
これには種々の形の大型ソフトの開発と運用が付きもの
のようで,これらの実働する現状では現用電子計算機は
導入当時の予測をはるかに上回る需要を持っています。
この傾向は今後も続き昭和56年度にはセンターバッチ処
理換算で処理量は年間1万5千件以上にもなると予想さ
れます。ちなみに1日当たり8時間稼動するとして1分
に1ジョブの処理を必要とすることになります。これは現
在のシステムで実行可能な数字ではありません。計算機
の能力の増強とともに分散処理思想の導入が必要とされ
ます。数ある端末と運用形態に対する考え方,また研究
所の諸所に種々の計画の下に設置されている中小とり交
ぜて25機に及ぶ計算機の去就等,システムを貴重な研究
への資源として見る時,10年先の将来の構想を含めて高
いレベルでの判断が必須な時機にきていると考えられます。
これらを総合的に把握し,適正な運用,整備計画の方
針を決めるため昨年7月1日に電子計算機運用委員会が
発足し活動しています。この委員会は,運用とソフトの
諸問題を第1分科会で,将来システムを含むハードの諸
問題を第2分科会で審議しており,既に現用機の運用方
針,外注ソフトに対する指針,現用機整備及び次期シス
テム構想とシステム更新時期についての上申を終わりま
した。これらの基本調査,関連事務は計算機研究室の担
当となっています。
計算機研究室には長い間蓄積された経験豊かな技術が
あります。その技術を生かせる調査項目として衛星搭載
用計算機の調査を今年から始めます。一見異質ですが将
来システム構想へ必ずフィードバックできるものと期待
しています。またシステムの更新は目前に追った大きな
仕事で,今までの経験と技術調査成果をもって全力で当
たらねばなりません。しかしながら計算機は研究所全体
の共用システムですから総合力が是非とも必要です。衛
星計画関係部門への配慮,現在情報処理部他部門と協力
して進められている総務部関係業務へのEDP導入,鹿島
支所での現システムと新しい計画への対処,図書関連
業務の近代化策,各研究室の測定自動化の動向注視,支
所・観測所も含めた電波部関係のデータ処理解析の動向,
スケールの大きい科学技術計算など多様なニーズヘの有
効なシステムが望まれます。研究所各部門からの相変わ
らぬ支援と協力をお願いする次第です。
複雑多岐にわたる研究室の仕事を手堅くしかも手際よく
処理し,新しいシステムの調査研究に余念なく奮闘を続
け,素人室長を何とか勤めさせて下さる室員は次の7人
の人々です。
有馬安春主任研究官,中村嘉彦主任研究官,奥田哲也
主任研究官,高部政雄技官,加藤久雄技官,淡河貴美
子事務官,吉村康江事務官
(計算機研究室長 原田 喜久男)