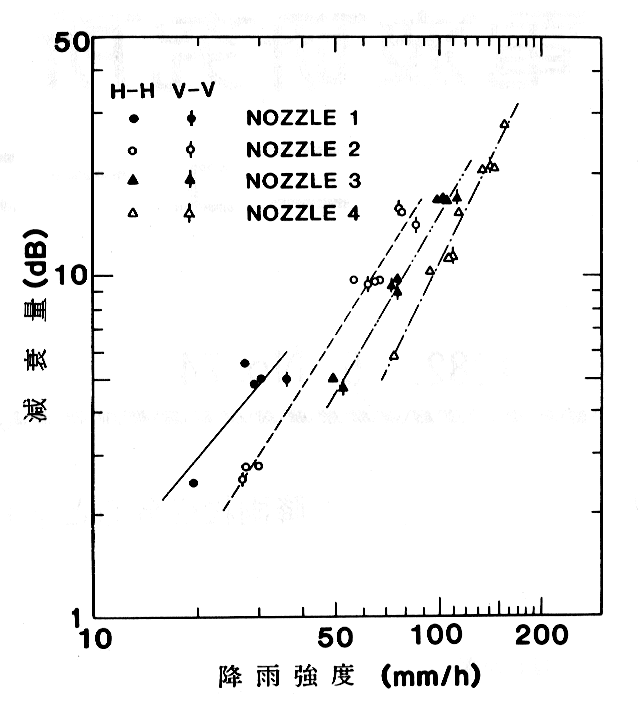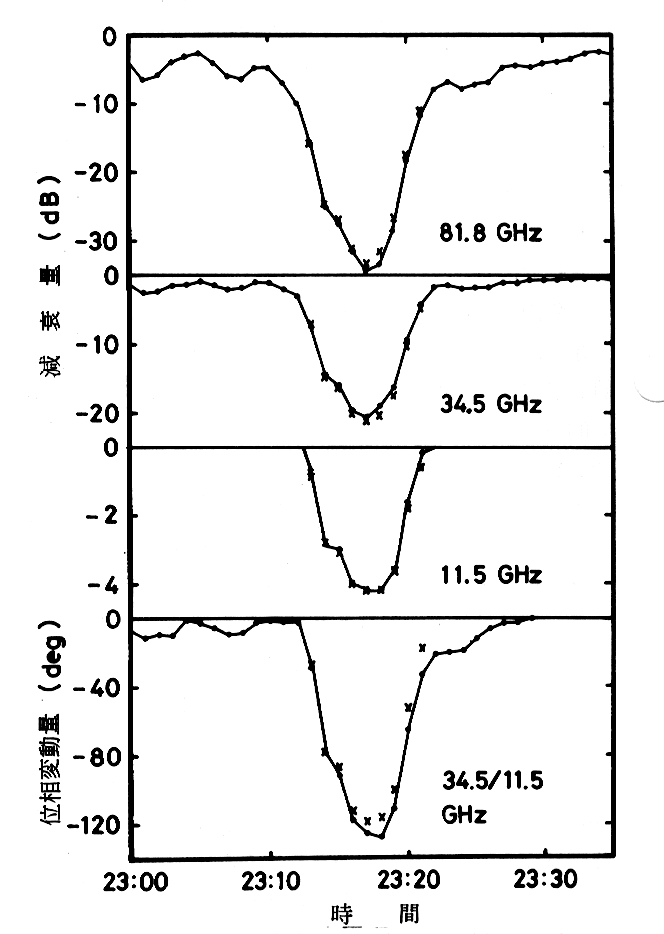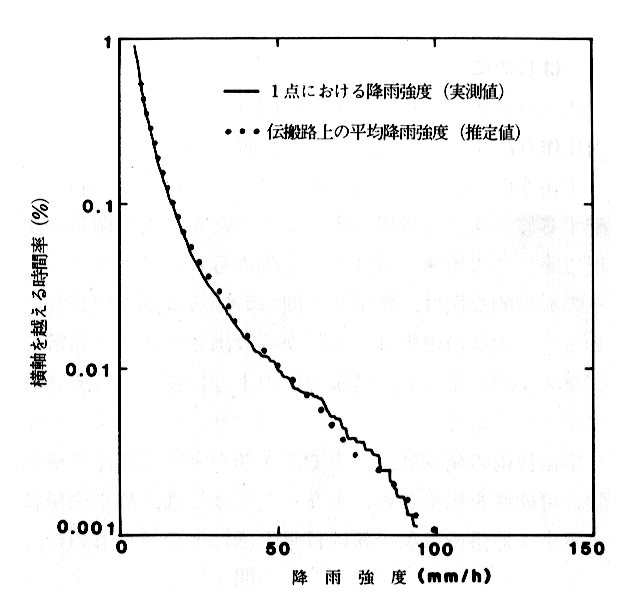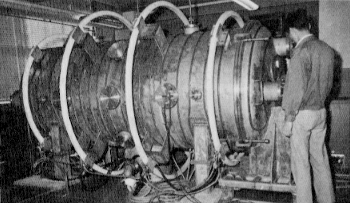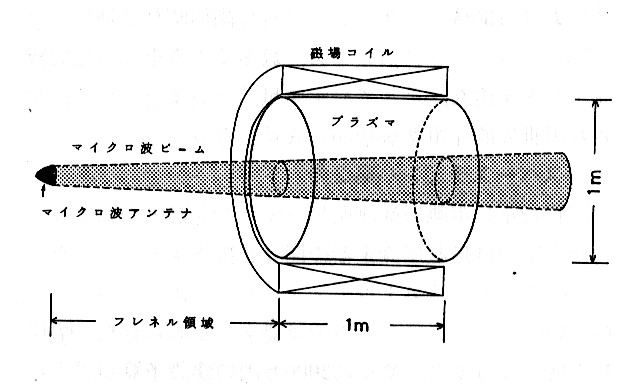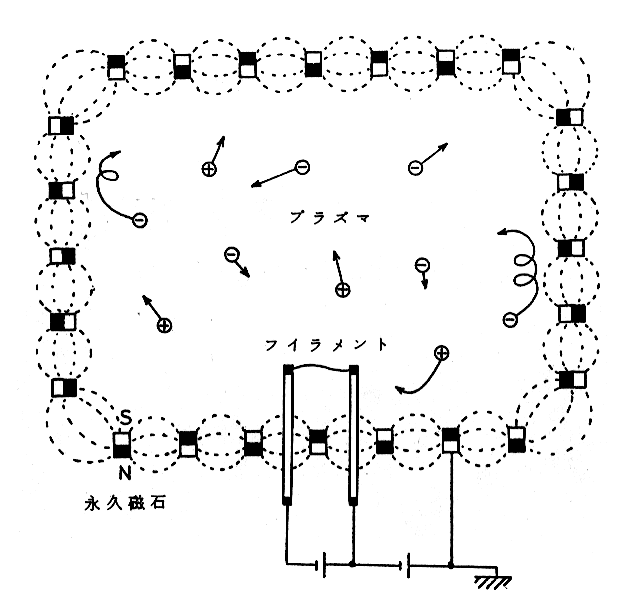降雨粒径分布とミリ波帯降雨減衰推定法
電 波 部
はしがき
電波部超高周波伝搬研究室では,ミリ波帯電波利用の
開発の一環として,ミリ波帯電波の大気伝搬特性の解明,
特に降雨減衰特性の解明のため,昭和54年以降ミリ波セ
ンチ波帯電波を用いて伝搬実験を実施している。これま
で多数の新しいデータを蓄積してきたが,これらのデー
タを用いて伝搬路上の平均降雨粒径分布を導出する手法
を提案し,これを用いてミリ波帯全域にわたって降雨減
衰を精度良く推定する方法を開発したので,それらの概
要を紹介する。
降雨の一様性と降雨減衰推定
単一雨滴による電波の散乱・吸収の様子は,複雑な計
算を必要とするものの,雨滴の形状,大きさなどの幾何
学的性質と誘電率などの電気的性質を与えると,特定の
周波数に対して,正確に計算することができる。この内,
降雨中を伝搬する電波の減衰や位相変動に関係する量を
前方散乱振幅と呼んでいる。実際の伝搬路における降雨
では,単位体積当り特定の大きさの雨滴が何個あるかと
いう,雨滴粒径の空間分布及びそれらの時間変動が不明
であるため,個々の粒径の雨滴に関する前方散乱振幅が
わかっていても,容易に電波の減衰や位相変動を計算で
きない。このため,しばしば伝搬路上で一様に雨が降っ
ていると仮定し,平均的な雨滴粒径分布即ち
Marshall and Palmer分布とかJoss et al.分布などを使って,
降雨減衰などを計算している。しかし,実際の通信回線
の設計においては,しばしば伝搬路全域にわたって雨域
の一様性を仮定することができない。
センチ波帯の電波を用いた通信回線では,その伝搬距
離は数㎞乃至十数㎞と長いので,この間で雨域が一
様であると考え難い。このため各種の雨域モデルが提出
され,それに応じた降雨減衰推定法が提案され,実用上
一応満足すべきものが得られている。因に,昨年行われ
たCCIR最終会議SG5会議においても,長年の懸案であ
った降雨減衰推定法に一応の決着が付けられCCIR法が
確立された。いずれも降雨強度分布が与えられれば,降
雨減衰がわかるような形式になっている。
他方,ミリ波帯の電波は,降雨によって著しく減衰を
受けるので,これに即して通信回線を維持しようとする
と,伝搬距離を短くせざるを得ない。このためミリ波通
信回線の伝搬距離は,通常数㎞以下と考えられ, この
程度のスケールでは,雨域構造は一様と考えられる。と
ころがミリ波帯では,電波の波長がセンチ波に比べて短
かいので,降雨強度には大きな寄与をしないような細か
い雨滴まで寄与し,降雨強度による降雨減衰の推定が難
しくなる。従って,降雨減衰の推定には,降雨強度と共
に降雨粒径分布を把握する必要がある。従来から使われ
て来たMarshall and Palmer分布やJoss et al. 分布
では,降雨減衰推定誤差が大きくなるので,この周波数
帯に相応しい降雨粒径分布を求めなければならない。
以下の記述では,ミリ波の降雨減衰を考えるため,降
雨の一様性を仮定して議論することにする。従って,降
雨粒径分布がわかれば降雨の落下速度分布を仮定すると
降雨強度がわかるのでミリ波除雨減衰推定法の確立は,
降雨粒径分布推定法の確立に還元される。
ミリ波降雨減衰の粒径分布依存性
ミリ波帯降雨減衰の粒径分布依存性を実証するために,
筑波学園都市にある国立防災科学技術センタの大型降
雨実験施設を用いて141GHz帯(波長2.1㎜)電波の伝
搬実験を行った。図1は,各種の模擬降雨による電波
の減衰例を示す。伝搬距離は72mであり,伝搬路下に設置
された4台の水滴計数型の雨量計を用いて降雨強度を測
定した。この降雨実験施設は,地上から約16mの位置に
4種類の口径の異なるノズルを備えており,粒径分布の
異なった模擬降雨を作ることができる。図からわかるよ
うにノズルが異なると同一降雨強度(即ち同一の単位時
間当り降水量)においても,ミリ波電波の減衰量に著し
い差が出ており,ノズル番号が小さい程(即ち,細かい
粒径の水滴が多い程)減衰量が大きくなっている。例え
ば,70㎜/hの降雨強度において, ノズル2とノズル4
では,それぞれ約12dB及び5dBの減衰が生じており,
両者の減衰比はdB値で2.4倍となっている。このように,
ミリ波除雨減衰は,降雨強度のみならず,降雨粒径分布
によって著しく変わることがわかる。なお,図のH-H,
V-Vは送受信電波の偏波状態を示し,偏波による差は
ほとんど現われていない。これは,この模擬降雨の粒径
分布が自然界に存在する降雨と異なり,水滴形状が球形
に近い細かい雨滴の非常に多いものであったこと,及び
使用周波数が高かったことが原因と考えられる。
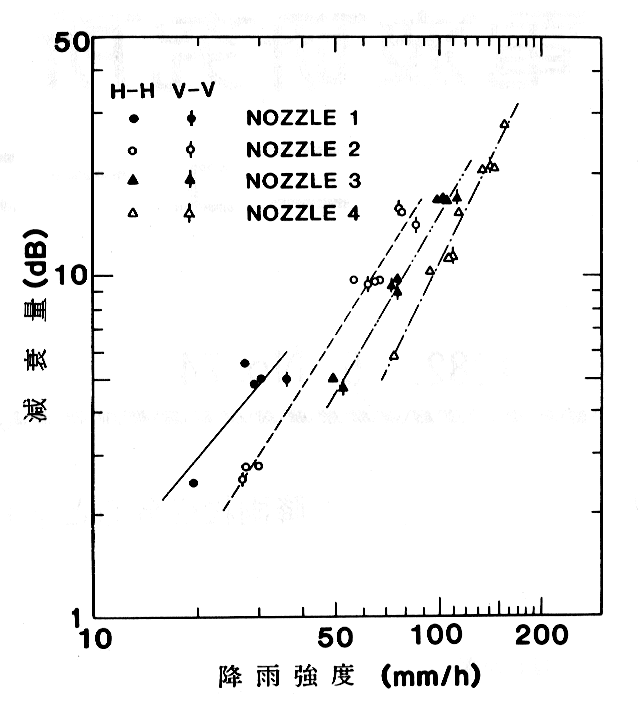
図1 模擬降雨による141GHzの減衰特性
降雨による位相変動
㈱日立製作所中央研究所,当所間の伝搬実験システ
ム(距離1.3㎞)においては,4種類の電波(1.7,11.5,
34.5,81.8GHz)を同時に送受信しているので,1波を
用いたときよりも格段に豊富な情報が得られ,降雨の電
波への影響を容易に評価することができる。また,この
システムにおいては,4波相互間において,コヒーレン
スが保たれているため,降雨などの伝搬路上の媒質の影
響で生ずる位相変動を,2波の間の位相差として測定で
きる特徴がある。
図2は1979年8月3日に,この実験システムを用い
て測定した降雨時(最大降雨強度90㎜/h)におけるミ
リ波帯及びセンチ波帯電波の振幅及び位相の変動例であ
る。測定周波数81.8,34.5,11.5GHzにおける最大降雨
減衰量は,それぞれ35,20,4dBに達している。また,
同図最下段は,降雨による34.5GHz及び11.5GHzの周波
数間位相差を34.5GHzの波長で計数した値を示し,最大
120度の変化がある。実験室規模で,水滴による電波の
位相変動を測定した例は報告されているが,多数の雨滴
が伝搬路上に分布する野外の実際の伝搬路で,降雨によ
る位相差変動が測定されたのは,この測定が最初である
と思われる。
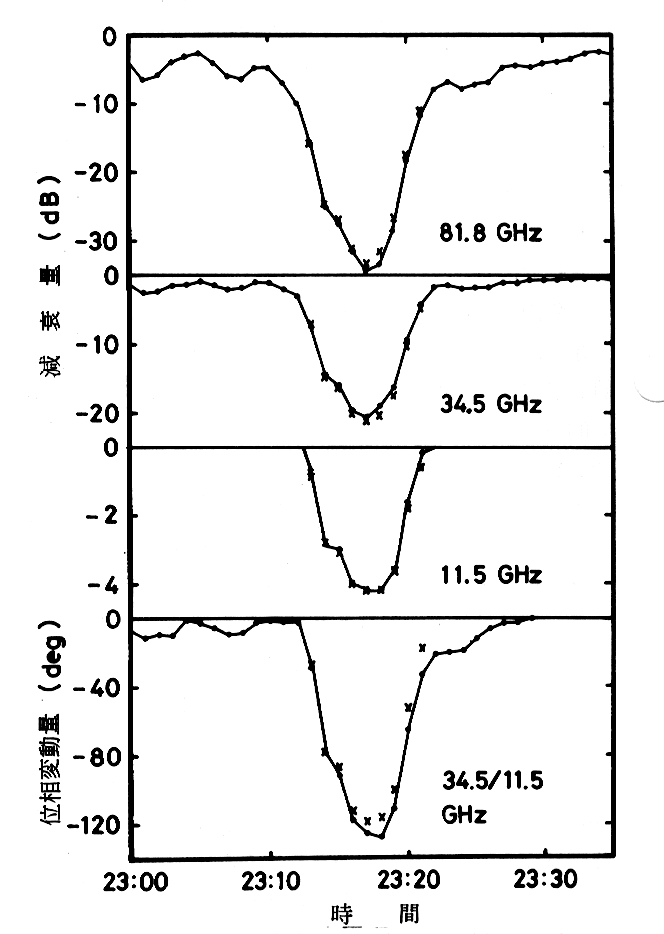
図2 降雨による各種電波の変動例、×印は推定値
余談になるが,最近,地震予知などへの応用でVLBI
(超長基線干渉計)システムが脚光を浴びている。VLBI
システムでは,伝搬路長の変動分の評価が重要であり,
晴天時における変動要因である水蒸気などの評価をラジ
オメ-タを用いて行っている。降雨時には, このラジオ
メータ法は,伝搬路長の変動分評価に対して無力に近い。
このため,現用のVLBIシステムでは,降雨時の運用を
断念せざるを得ない。しかしながら,上述のように,互いに
コヒーレントで適当な2波を選び,降雨による位相変動
を測れば,降雨時においても,VLBIシステムを運用で
きる可能性がある。
伝搬路上の平均降雨粒径分布を用いる
降雨域表周波数スケーリング法
先に述べたように,伝搬路上の雨の粒径分布がわかれ
ば,ミリ波帯電波の降雨による減衰や位相変動は容易に
計算できる。しかし,この逆は必ずしも容易ではない。
即ち,降雨中を伝搬したために生ずるミリ波電波の減衰
や位相変動から,伝搬路上の雨の粒径分布を算出するこ
とは難しい。これは数学的には,積分方程式を解くこと
に対応し,逆散乱問題の一種である。しかし,伝搬路上
の降雨粒径分布も,多数の電波を用いて測定した結果を
用い,かつ適当な仮定を置くと求めることができる。当
研究室では, 図2に示すような3波の減衰量あるいは
これに周波数間の位相差を用いて,伝搬路上の平均的な
降雨粒径分布を推定する方法を提案し,その有効性を確
かめている。この場合,実用的には,降雨粒径分布を雨
滴直径に関する指数関数と仮定して差支えないことがわ
かっている。図2の×印は,四つの測定量から決めた
伝搬路上の平均的な降雨粒径分布を基にして,それぞれ
の周波数における降雨減衰及び周波数間位相差を再生し
たものである。測定値(・印)からのずれは,この推定
法の精度を表わすものと考えられる。この方法は,10~
100GHz帯の任意の周波数における降雨減衰及び位相差
を算出する場合にも全く同様に適用できる。この場合に
おいても,同程度の推定精度が期待される。このように,
既知の降雨減衰量から,他の周波数における降雨減衰量
を推定することを周波数スケーリングと呼んでいる。以
上は,瞬時の測定値について,伝搬路上の平均的な降雨
粒径分布を用いる周波数スケーリング法について述べた
ものであるが,この方法は累積分布のような統計量に対
しても適用することができる。
このようにして,同一伝搬路における降雨減衰の推定
は,伝搬路上の降雨粒径分布を介して非常に正確に行う
ことができるようになった。換言すれば,ミリ波帯及び
センチ波帯電波に影響を与える降雨の特徴を,降雨減衰
の解析から,伝搬路上の平均降雨粒径分布N(D)という
物理量によって正確に把握できたことになる。また,ミ
リ波帯電波を通信に用いる場合,降雨時にも運用する必
要があることから,伝搬距離は数㎞以内に限定される。
この程度の距離において,降雨はほぼ一様と考えられる
ので,伝搬路上の平均降雨粒径分布N(D)を介する降雨
減衰周波数スケーリング法は,ミリ波帯電波の降雨減衰
推定法として有効であると考えられる。即ち,当所に
おいて取得した年間の降雨減衰累積分布などの統計量
からN(D)を決めると,このN(D)は降雨強度の関数と
して表わされているので,降雨強度さえ与えれば,東京
近傍の降雨気候に類似のところ,即ちほぼ日本全国にお
いて,適用できると考えられる。このN(D)を用いて,
ほぼ日本全国において,30~100GHzの周波数帯にわたる
精度良い降雨減衰推定ができる。
図3は,昭和54年度1年間のデータの解析結果を降
雨強度の累積分布として示したものである。実線は,受
信地点に置いた雨量計で測定した降雨強度を示す。点線
は,1.3㎞の伝搬路における三つの電波(11.5,34.5,
81.8GHz)の降雨減衰から,伝搬路上の平均降雨粒径分
布を導出し,これを基にして求めた,伝搬路上の平均的
な降雨強度を示す。両者は,広い範囲にわたって非常に
よい一致を示している。これは,粒径分布推定法の妥当
性を示すとともに,1.3㎞程度における平均的な降雨強度
は,1点における降雨強度測定で代表でき,このスケー
ルでは降雨が統計的に一様であると考えてよいことを示
している。
また,最近の解析によると,降雨が空間的に一様であ
ると仮定すれば,ミリ波帯の適当な1波(例えば80GHz
帯の1波)の降雨減衰と降雨強度の測定値から,容易に
伝搬路上の平均降雨粒径分布を導出できることがわかっ
ている。
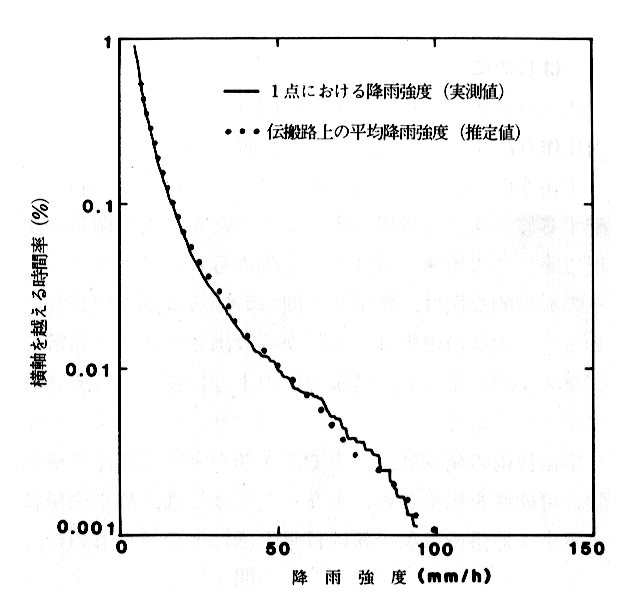
図3 降雨強度の累積分布
あとがき
同一伝搬路において多数の周波数を用いて降雨減衰を
測定し,そのデータ解析から,伝搬路上の平均的な降雨
粒径分布を求めること,また,より簡便な方法として1
波の降雨強度測定から同様の降雨粒径分布を求め得るこ
とについて述べた。ミリ波通信回線などの降雨減衰予
測の場合には,伝搬距離が数㎞以下と比較的短かいこ
とから,上述の分布を年間統計などの意味で求めておけ
ば,ほぼ日本全国におけるミリ波帯(30~100GHz)降
雨減衰推定が容易に行えると考えられる。現在,ミリ波
帯の四つの大気の窓でそれぞれ1波ずつ選び(50,82,
141,246GHz),東京経済大学,当所間の810mの伝搬路に
おける伝搬実験を準備している。このシステムによる測
定結果を用いて,伝搬路上の平均降雨粒径分布を求めれ
ば,ミリ波帯全域(30~300GHz)にわたる降雨減衰の推
定が可能となる。また,このデータは,数㎞以内の伝搬
路であれば,ほぼ日本全国におけるミリ波帯降雨減衰推
定にそのまま使えるものと期待されている。
降雨減衰から降雨粒径分布を求めることは,数学的に
はFredholm型第一種の積分方程式を解くことと等価で
あり,同様のことは,各種リモートセンシングによるデ
ータ解析において,しばしば見られる。一般にこの方程
式の解は一意的に決まらないので,場合に応じた指導原
理を導入し物理的に無理のない解を求めることになる。
降雨粒径分布の場合は,粒径に関する指数型関数を仮定
することで一応の成功をみている。
(超高周波伝搬研究室長 古濱洋治)
スペースチェンバを使った研究の歩みと将来
-電離層・宇宙環境を実験室内で調べる-
衛星計測部
はじめに
スペースチェンバは,宇宙空間(スペース)を実験室
内に作り出すことを目的とする装置である。
宇宙空間は,ほんの20~30年前までは真空と静寂が支
配する悠久無限の世界にすぎなかったが,人工衛星の出
現以来,このイメージは大きく改められることになった。
その典型的な例は,惑星間空間における太陽風の発見で
あろう。地球の磁場は,太陽から放出されるこの希薄な
プラズマ流によって,彗星の尾のように長く吹き流され
ていたのである。
宇宙技術の発達は,一方で,人類が宇宙に進出する無
限の可能性を拓くことにもなった。今では,静止街星に
よる宇宙通信や気象予報は日常生活に欠かせぬものにな
っているが,スペースシャトルの開発により,将来,宇
宙に大規模な居住空間を建設することも夢ではない。
かくの如く,もはや宇宙は学問研究の対象としてのみ
ならず,実生活の隅々にまで深く関り合ってきている。
今本格的な宇宙の実用化時代の入口にあって,宇宙空間
の電磁環境,及び,そこに生起する様々な現象の因果関
係を正しく理解することは大切なことである。正にこの
目的のために,スペースチェンバが必要とされる所以で
ある。
当所に初めてのスペースチェンバが設置されたのは21
年前に遡るが,現在,その役割は第2号スペースチェン
バに引き継がれている。本文では,当所のスペースチェ
ンバによる電離層,宇宙空間研究のあゆみをふりかえる
と共に,現在とり組んでいる研究課題についての紹介を
行いたい。
スペースチェンバ以前
国際地球観測年(昭和32~33年)後まもなく,ロケッ
トによって直接電離層のプラズマを観測する計画が立て
られた。どのように測定するか,測定器をどう開発する
か,またそれに必要なしかも測定対象に適した素姓のよ
いプラズマをいかにして安定に作るかが最初の課題であ
った。
最初に試みたのは放電実験に使われていた真空管タイ
プに準じた硝子製のプラズマ放電管の製作,実験であっ
た。電離層の電子密度は10^6el/㎝^3程度なので,従来の放
電管の密度に比べて遥かに低密度である。このためまず
容積を大きくし,放電電極からのプラズマの拡散方式を
用いた。直径30㎝のフラスコを硝子業者に細工をして貰
って,両端に放電々極をとりつけ,中央に可動プローブ
を挿入したものを製作した。
それを実験室において排気装置にとりつけ,必要な処
理を施しプラズマ放電管として完成させる。この製作工
程は大変危険が多く,急いでもまる1週間はかかり,か
つ分留りも悪い。完成して,実際に実験を行うと,最良
のコンディションは長くて1週間であり,あとは劣化し
不安定になってしまう。
さて処理過程に七つの危険な段階がある。まず硝子放
電管を酸素ガスバーナで排気装置に接合させる。硬質
硝子で融点は高く,素人細工には大変難しい。首尾よく
接合できると,排気開始であるが,最初の間は排気ガス
が室内に充満して息苦しくなる。しかる後今度は硝子球
を400℃~500℃までべーキング処理を行う。この時間
は長ければ長い程良い。次に電極の脱ガスのため高周波
ボンバーダを使い,電極部分を赤熱させる。次いで水銀
を入れる作業である。水銀イオンのプラズマを作るため
である。このとき排気口の途中にトラップがあり,液体
窒素を頻繁に補給する手作業がある。最後にヒータを
活性化させて,いよいよ高真空のまま硝子球を封じ切る
のである。これが大変難しく細心の注意と技術が必要と
される。ここで失敗すれば総て水泡に帰し,高価な放電
管は無になる。
首尾よく封じ切りが成功しても,製作過程の僅かの違
いによって,プラズマの発生状態は非常に異なり,実験
がうまくいくものと,まるで使いものにならない場合が
あり,何回も泣かされたものである。
スペースチェンバ第1号
如何にして確実安全に安定なプラズマを作るかが最大
の課題であった。排気系,処理過程,電極構造,使用ガ
スをいろいろ検討し,何回も試行錯誤を重ねた。この間
に排気装置を延べ6台,電気炉を計3台も試作した。
さて真空技術の急速な発達によって,大型の高真空容
器が出来るようになったので,昭和35年に内径1.2m,平
行部の長さ1mという,当時としては大型の装置を作るこ
とを決定した。電離層E層の中性密度は約10^-4Torrであ
り,分子の平均自由行程は約10㎝であるので,チェンバ
のサイズは最小限のものであった。
完成したのは昭和36年8月で,主な諸元は次の通りで
ある。材質:非磁性体sus-28,排気系:2インチおよび
6インチ油拡散ポンプ,導入端子:矩形(25cm×13㎝
1個,10㎝×7㎝ 2個)および6インチ丸窓2個,・放電用
電極端子:高圧および低圧用各4個,可動電極:軸,径
方向2個,外周加熱ヒータ:30kW,到達真空度:3時間
250℃ベーキング後2×10^-6Torr,タンク漏洩量:1×
10^-7l Torr/s以下,タンクを2時間放置して3×10^-5Torr
以下,停電断水時の保護機能付加。
この時迄に得られた実験成果をまとめると,ロケット
搭載用ラングミュアプローブ,レゾナンスプローブ,イ
オンプローブ(ファラデーカップ)の開発があり,それ
らは秋田実験場における14機のロケット,鹿児島県内之
浦における30機のロケット,さらに南極昭和基地におけ
る25機のロケットに搭載され,数多くの貴重な電離層観
測データを得た。そして科学衛星「たいよう」にも搭載
され汎世界的な電離層観測に成功した。
スペースチェンバ第2号
昭和42年に電離層観測衛星(ISS)開発計画が始まり,
当研究室では搭載用測定器の開発を担当することになっ
たが,この頃には第1号チェンバも旧式化していたので,
新しいスペースチェンバの予算要求が始められた。昭和
48年度になってようやく約2000万円の建設予算が認めら
れ,昭和49年6月に第2号チェンバが納入された。
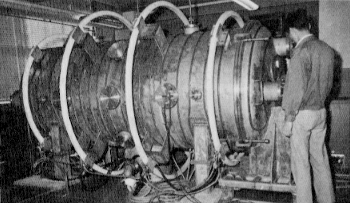
スペースチェンバ
このチェンバは,図1のように,直径1.2m,長さ約
3.2mの円筒形で,厚さ5㎜のスンレス鋼で作られて
いる。外壁には4本の円環コイルが取り付けられており,
これらに最大300Aの電流を流すことにより,中心軸上に
50ガウスまでの均一な磁場をかけることができる。チェ
ンバの排気系は,22インチの油拡散ポンプを主体とし
て,8時間以内にチェンバ内の真空度を10^-7Torr台に
する能力がある。排気装置は,チェンバ直下にピット
を掘って,すべてその中に収納された。この装置を使用
してISS-bに搭載したプラズマ測定器の試験,較正実験
も行われた。
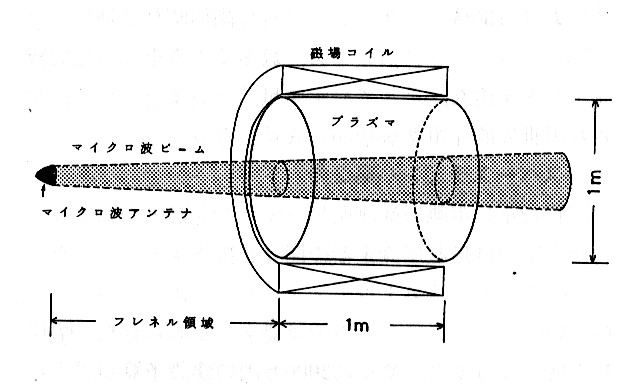
図1 大電力マイクロ波ビーム実験
これからの研究課題
最近の宇宙技術の発達は目ざましいが,宇宙と地上を
結ぶ通信には,伝搬路上の電離層と大気の影響を受けに
くいマイクロ波帯の周波数の電波が多く使用されている。
しかし,この周波数帯の電波ですら,電離層が擾乱す
ると位相や振幅に変動を受け,受信電波にシンチレーシ
ョンが生ずることはよく知られている。たとえば,電波
リモートセンシングの先端技術である合成開口レーダは,
やはりマイクロ波帯の電波を使用し,地上からの散乱波
の精密な位相合成によって昼夜,天候によらず光学写真
に匹敵する高分解能の映像が得られる画期的なレーダで
あるが,電離層擾乱が画質に与える影響に関しては不明
であり,解明すべき問題である。また,将来のエネルギ
ー源として検討されている太陽発電衛星(SPS)構想に
よれば,宇宙で発電された電力はマイクロ波ビームによ
って地上へ送電されることになっている。この場合,電
離層プラズマは大電力マイクロ波によって著しく加熱さ
れ,屈折率の不均一を生じてビームの変形や分裂をひき
起す可能性がある。さらに,電波の異常散乱や電離層擾
乱の発生によって周囲の電磁環境に影響を及ぼすかも知
れない。このように,マイクロ波を使った新しい宇宙技
術と電離層との間には,それぞれ解決すべき問題がある。
これらの諸現象を実験室内に模擬的に再現させることが
できれば,現象の解明と関連技術の開発に役立つであろ
う。
電離層中のマイクロ波伝搬の模擬実験
マイクロ波が電離層中を伝わる間の位相や振幅の変動
を実験室内に再現させることを考えてみる。一般に,電
波がプラズマ中を伝搬する間のプラズマによる位相の遅
れ分は,伝搬路中の全電子数に比例し,電波の周波数に
反比例する。観測によれば,電離層の垂直柱状電子密度
は10^16~10^18個/㎡程度なので,実験室内の長さ1mのプ
ラズマ柱によって同じだけの位相遅れを起させるために
は,電子密度10^10~10^12個/cm^3の均一なプラズマを発生
させれば良いことになる。さらに,高エネルギーマイク
ロ波と電離層プラズマとの相互作用のシミュレーション
を行うには,プラズマの加熱や熱拡散などが電離層と同
様の機構で生ずる必要がある。図1は,我々の実験装
置の概念図である。プラズマの外周の磁場コイルは,プ
ラズマの径方向への拡散を制御するためのものである。
このプラズマに十分波長の短かい電波をビーム状に入射
することによって,プラズマ容器の壁面の影響を軽減す
るとともに,ビームの変形の様子を詳しく調べることが
できる。
マルチポールプラズマ
上述の実験のためには,電子密度10^10~10^12個/㎝^3で
空間的に十分均一なプラズマが必要であるが,マルチポ
ール方式のプラズマが正にこれらの要求にかなうものと
期待される。この方式は,1972年にUCLAで開発された
もので,その特徴は,図2のように,プラズマ発生容
器を金属壁面のかわりに,永久磁石を格子状に並べた磁
気籠構造にしたことである。永久磁石の極性は,図の様
に,隣り同士の格子が逆向きになるように配置されてい
るので,格子間の磁力線は互いに結合して閉じ,磁極上
にのみカスプを生ずる形となる。このようにすると,フ
ィラメントから放出される熱電子は磁場に捕えられて容
器から外へ逃げられず,まれにカスプに吸収される以外
は,再び容器内に反射される。そのため,熱電子の容器
内での滞在時間が非常に延び,低いガス圧でも電離効率
が高くなるので,高密度のプラズマが発生できる。ガス
圧が低いと熱電子と中性ガスとの衝突距離が長くなるた
め,熱電子が容器全体に行きわたり,発生するプラズマ
の密度分布の均一性も良くなる。
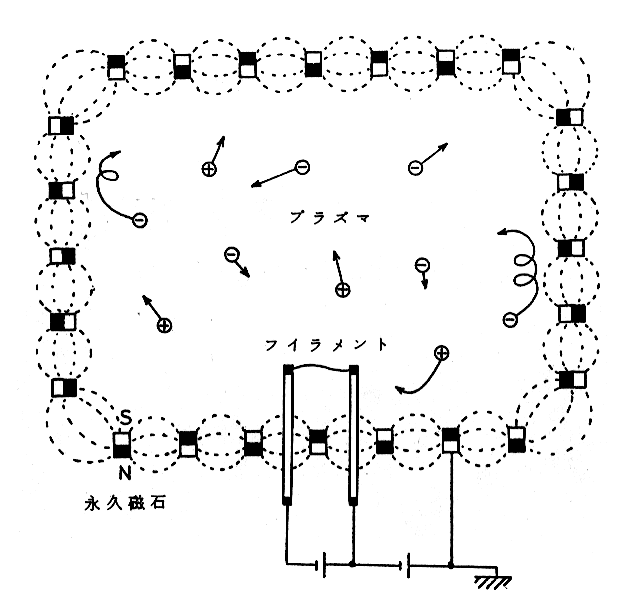
図2 マルチポール型プラズマ源
今回製作したマルチポールプラズマ容器は,断面が一
辺60㎝の正方形で長さ120㎝の直方体をしており,これ
をスペースチェンバの中に入れて使用する。容器の中に
は直径0.2㎜,長さ10㎝程度のタングステン線を数本取
り付け,熱陰極放電によりプラズマを発生させた。初期
的な実験によれば,数Aの放電電流で電子密度10^10個/㎝^3
台,電子温度2~3万度の非常に均一なプラズマが得ら
れた。電子密度は,放電電流を増やすことによってさら
に上昇すると思われる。一応満足すべきプラズマが得ら
れたので,今後はマイクロ波ビーム系の製作を行い,目
的の実験を行う予定である。
おわりに
宇宙環境を理解するには,地上観測,飛しょう体観測
および理論的考察が必須であることは当然であるが,完
壁な観測を期するには宇宙はあまりにも広大である。そ
れ故宇宙を実験室内にシミュレートして,実験的に解明
することが必要になってくる。
観測で新しいデータを取得して理解,体系化すること
が自然科学の基本的な手順であり,この意味においても
宇宙研究においてのスペースチェンバ実験はその一助と
なるものである。
今後ともスペースチェンバの中には「金の卵」が存在
し,育つであろうことを念願している。
平磯支所長 宮崎 茂
第二衛星計測研究室 主任研究官 森 弘隆
短 信
栗原前所長,補充選挙でIFRB委員に選出
スイスのジュネーブで開催されたITUの第37回管理理
事会でIFRB委員の補充選挙が4月20日に行われ,我が
国から立候補していた栗原芳高前所長が委員として選出
された。
IFRB(国際周波数登録委員会)はITUに設置された機
関で,世界の5地域(南北アメリカ,西ヨーロッパ,東
ヨーロッパ,アフリカ及びアジア・大洋州)から1名づ
つ選出された5人の委員で構成されている。アジア・大
洋州の代表としては,我が国から藤木栄氏が選任されて
いたが,同氏が任期中に辞任したため今回補充選挙が行
われた。従って栗原新委員の任期は,残された今年末ま
でで,11月に次期委員の選挙が実施される。
CSを利用したディジタル紙面電送の実験実施
本実験は,CS応用実験として郵政省が日本電信電話公
社及び日本新聞協会の協力を得て,報道用各種情報の伝
送実験の一環として行ったもので,ディジタル化された
紙面電送情報を衛星回線を用いて伝送する場合の技術的
問題点を把握することを目的として2通りの実験を実施
したが,双方とも良好な品質の紙面電送を行えることを
確認した。
なお,昨年2月に実施した実験では,データ,写真及
びファクシミリの伝送実験並びにアナログ紙面電送実験
を行い,期待どおりの実験結果が得られている。
今回行った実験の概要は次のとおりである。
1. FDM(Frequency Division Multiplex:周波数分割
多重)回線実験(4月12日~15日)
実験は,朝日新聞東京本社駐車場に設置した電電公社
の準ミリ波車載局(アンテナ直径2.7m,出力100W)を用
いて衛星折返しの準ミリ波帯(上り回線30GHz帯,下り
回線20GHz帯)の衛星回線を設定して行った。準ミリ波
車載局は,電話132回線の伝送が可能であるが,紙面電
送実験には,このうち12回線分の帯域を使用した。回線
の基本特性を測定したところ,ビット誤り率は10^-9以下
であり,良好であることが確認された。
2. PSK(Phase Shift Keying:ディジタル位相変調
回線実験(4月19日~23日)
同じく朝日新聞東京本社駐車場に設置した郵政省電波
研究所の車載化した第2SCPC局(アンテナ直径1m,
出力17W)からCSを経由して鹿島支所のCS主局(アン
テナ直径13m)に伝送し,そこで再生中継された信号を
衛星経由で第2SCPC局及び朝日新聞大阪本社に設置し
た受信局(アンテナ直径2m相当)で受信した。使用周
波数帯としては,FDM回線実験と同じ準ミリ波帯を用
いた。
回線の基本特性では,CS主局から第2SCPC局及び受
信局への回線は,誤り訂正を行うことによってビット誤
り率がともに10^-9以下となり,良好であることが確認さ
れた。
これは紙面を17~18枚電送して1つの誤りが発生する
くらいの回線品質である。
CSを利用した実験さらに延長可能
実験用中容量静止通信衛星(CS:さくら)は,昭和53
年5月15日から現在まで基本実験及び各種応用実験に利
用されている。CSの搭載中継器(準ミリ波帯4台,マイ
クロ波帯2台)は,打上げ以来4年有余を経過した現在
も正常に動作している。しかし宇宙開発事業団において
CSの残存燃料の予測を行ったところ,これまでどおり衛
星の軌道及び姿勢制御を続けると最悪の場合には,昭和
57年夏ごろに残存燃料が無くなることが明らかとなった。
このため関係者で協議の結果昭和57年3月以降,もっと
も燃料を消費する南北軌道制御を中止することとなった。
これによりCSは今後数年間にわたって運用可能の見通
しが得られた。
当所では昭和58年度以降もCSを有効に利用するとと
もに,衛星特性の長期経年変化を測定し,また南北軌道
制御を中止したため軌道傾斜角が大きくなったときの衛
星の運用,利用技術の関発等を進める計画である。
電離層観測衛星(ISS-b)及び実験用中容量静止通信衛星(CS)の協定更新
当所と宇宙開発事業団(NASDA)との間で締結してい
るISS-bに関する管理運用業務及び実施に関する協定は,
有効期限が本年3月31日までであったが,引き続き同衛
星の管理運用業務を実施して,その有効利用を図るため
有効期限を昭和58年3月31日とする協定を当所とNASDA
との間で57年3月23日締結した。また,CSに関して郵政
省とNASDAとの間で締結している管理・運用業務の分
担及び実施に関する協定も有効期限が本年3月31日まで
であったが,引き続きその有効利用を図るため有効期限
を昭和58年3月31日とする協定を郵政省とNASDAの間
で締結した。これに伴い当所とNASDAの間で締結して
いるCSに係る運用計画書及び覚書も同協定に準じ自動
的に延長することとなった。
第22次南極観測隊帰国
第22次越冬隊34名は3月21日15時20分,JAL462便(北
極経由)で成田空港に帰国した。一方,観測船「ふじ」は
1か月遅れて4月20日晴海埠頭に入港し,観測記録を持
ち帰った。当所から参加した栗原隊員は電離層定常観測
3項目の他,研究観測としてオメガ電波測定,散乱波通
信実験等を実施した。
夏季建設期は晴天に恵まれ,情報処理棟を建設し,計
算機,計測器等をセットしてデータ収録を行った。また
基地の人工雑音からのがれるため,西オングル島に無人
のテレメータ基地を建設し,超高層関係のセンサを移
設して短期間に設置,調整を完了した。4月1日から連
続観測を開始した。また人工衛星テレメータは順調であ
った。9月5日,昭和基地開設以来2番目というブリザ
ードに襲われ,電離層観測用30mデルタアンテナ柱が倒
壊したが,予備アンテナに切替え観測には支障なかった。
逓信記念日表彰について
4月20日の第49回逓信記念日に際し,当所関係では
大臣表彰として事業優績者2名,又所長表彰として事業
優績で2団体が表彰された。
1 大臣表彰
通信機器部通信系研究室 室長 角川靖夫
〃 研究官 塚田藤夫
多年にわたり陸上移動通信における周波数有効利用
技術の研究・開発に尽力しFM通信方式の狭帯域化の
技術基準を確立するなど大きく貢献した。
2 所長表彰
情報処理部計算機研究室
当所の研究業務に必要な大型計算機システムを導入
するとともに効率的な運用態勢を確立し研究業務の推
進に貢献した。
沖縄電波観測所
沖縄本土復帰以来幾多の困難を克服して電離層定常
観測業務を確立するとともに国際磁気圏観測計画・放
送衛星計画などにも参加し亜熱帯地域の特徴を生かし
た電波研究の進展に貢献した。
ISEE客員共同研究プログラムへの参加決定
ISEE(国際太陽地球間観測衛星)計画は,NASAと
ESAとが共同で進めているもので,高エネルギー粒子,
プラズマ,静電磁場及び電磁波を媒介とした太陽からの
エネルギーの地球磁気圏,電離圏への流入過程を解明す
ることを目的としている。ISEE-1,-2号は1977年
10月22日に遠地点約138,000㎞,近地点約280㎞,軌道傾
斜角28.7°の軌道に間隔をおいて打上げられた。又ISEE
-3号は地球中心から地球半径の約230倍の前方にある
秤動点附近のハロー軌道に1978年8月12日に打上げられ,
地球磁場の外で太陽からの粒子,波動,プラズマを直接
観測している。特にISEE-1,-2号は観測データか
ら時間的変化と空間的変化を分離するために同一軌道上
で離して運用されている。NASAはISEEデータを世界
の研究者に公開して研究成果を更に上げるために,1981
年6月に全世界に「ISEE客員共同研究プログラム」へ
の参加を公募した。電波研究所からも無線通信障害,衛
星異常帯電等を起す磁気嵐,オーロラ嵐の発生過程を明
らかにし,その発生を予報,警報する技術を向上させる
ために,1981年8月にこのプログラムへ応募した。その
結果NASA国際部国際企画プログラム長から,1982年3
月20日付の電波研究所長宛の手紙で,電波研究所の提案
が採用され,宇宙空間研究室の思藤忠典がISEE客員
共同研究プログラムの客員研究者に指名されたこと,又
その共同研究者として宇宙空間研究室渡辺成昭,中村義
勝,衛星データ解析研究室相京和弘,第二衛星計測研究
室森弘隆,超高層研究室小川忠彦が指名きれたことが通
知された。更にISEEデータの解析項目,時期に関して
は,NASAゴダード宇宙飛行センタにあるISEEワー
キング・グループの決定に従うこと,所要経費は各担当
側が負担すること等の約定事項が述べられており,1982
年4月19日に電波研究所長からこれに同意する旨の手紙
がNASA国際部へ返信され,電波研究所の関連部門の
「ISEE客員共同研究プログラム」への参加が決定された。
間このプログラムの米国側の代表者はISISプログラムの
初代委員長であった,電波研究所になじみ深い,NASA
本部のE. R. シュマーリング博士である。
7月1日うるう秒を実施
今年のうるう秒調整も昨年同様7月1日,日本時間9
時0分の直前に実施することになった。
現在世界各国で常用されている標準時はUTC(協定世
界時)に基づいている。このUTCは原子振動で定義さ
れた秒間隔で時を刻むと同時に,地球の自転角の尺度で
ある世界時(UT1)の近似値も表わしている。UTCとUT
1の差を0.9秒以内に保つ国際内申し合せに従い,UTC
の1秒ステップ調整(うるう秒調整)を行っている。UT1
のおくれは,1972年から1979年頃まではほぼ年1秒であ
ったため,毎年1月1日に調整していた。1980年頃より
年約0.8秒に減少したので,1年もしくは,1年半の調
整が必要になり,昨年は1年半後の7月1日,今年は1
年後の7月1日に実施される。この傾向が続くと,次の
うるう秒調整は1年半後の1984年1月1日となることも
予想される。
研究施設一般公開の御実内
昨年と同様,当所の研究施設を一般に公開いたします。
御多忙中とは存じますが,多数御来所くださるよう御案
内申し上げます。
公開日時 昭和57年7月30日 10時~16時
公開場所 本所,支所(鹿島,平磯)及び電波観測所
(稚内,秋田,犬吠,山川,沖縄)