 |
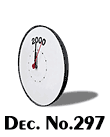 |
 |
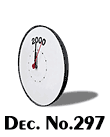 |
 |
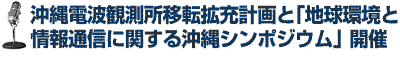 |
|||||||||||||||||
| 藤井 智史 |
||||||||||||||||||
|
沖縄電波観測所では、平成9年度より亜熱帯環境の総合計測技術の研究開発を実施しています。その研究の進展とあいまって、データ利用や次世代インターネットの利用技術の開発を進めるため、このほど、現沖縄電波観測所を、沖縄亜熱帯環境計測・ネットワーク研究センター(仮称)として拡充することになりました。 【亜熱帯地球環境計測技術の研究開発】 地球環境形成の源となる太陽から受け取るエネルギーの65%は、熱帯・亜熱帯地域に降り注ぎ、地球活動のエンジンの役割を果たしています。また、亜熱帯地域は熱帯と温帯・極地域の間でエネルギー交換の場にもなっています。日本で唯一、その亜熱帯に属するのが沖縄です。この沖縄では、西から東にモンスーン(貿易風)が吹いており、高層にはジェット気流が吹き、台風の通り道にもあたっています。一方、海に目を転じると、黒潮が台湾付近から北上して、琉球弧を取り囲むように東シナ海を流れ、再び太平洋に出てきます。 このように、沖縄付近は、大気環境においても海洋環境においても、ダイナミックに変動する場所であり、地球環境を理解する上で極めて重要な場所です。また、日本の社会全体に大きな影響を与える台風や黒潮の最適観測場所であり、本研究で開発する以下の観測装置の実用化やそのデータ利用は大いに意義があります。
【沖縄関連ネットワーク研究施設整備】 上記の研究観測データの流通や各研究機関との共同研究を進めるため、高速ネットワークの構築を進めます。このネットワークの概要は図2に示します。 まず、観測地点を超高速ネットワークで接続し、各地からのデータをギガビット級の帯域を用いて収集できるインフラを構築します。さらに、共同研究を行う沖縄の研究・教育機関を接続すると共に、IPv6(インターネットプロトコル・バージョン6)実験運用系ネットワークを構築し、共同で次世代インターネット技術を用いたシステム開発、遠隔教育実験をはじめとする利用技術の開発を実施するためのテストベットを構築します。
これらの新たな計画に伴い、現在中城村にある沖縄電波観測所の施設では各所の期待に十分応えられなくなってきました。また、周辺一帯で沖縄県の大規模公園計画が進められ、さらに隣接の中城城が「琉球王国のグスクおよび関連遺跡群」の一つとして世界遺産に指定される運びとなり、沖縄県より観測所移転の可能性が打診されてきました。このため、昨年来より移転候補地を検討し、恩納村にある米軍通信所跡地の一部(恩納村字恩納野原、敷地面積28,636㎡)に移転することについて、地元の住民、地主の方々並びに村の合意が得られ、このほど建築着工の運びとなりました。 新しい研究施設の建物は図3に示すような2階建て(延床面積2,580㎡)で、1階には常設展示場を設けて、地球環境や情報通信の先端技術に関する展示を行うとともに、地元にも役に立つ環境情報の提供や、インターネットなど情報通信にふれあう環境の提供なども行う計画です。 【シンポジウムの開催】 これらの計画の推進にあたり、沖縄電波観測所における活動を沖縄の人々に広く理解していただくことを目的として、沖縄において先導的にご活躍いただいている大学の先生方にご支援いただき、当所主催のシンポジウム「地球環境と情報通信に関する沖縄シンポジウム―21世紀のアジア・太平洋地域の中核研究拠点を目指して―」を、11月18日に恩納村の万座ビーチホテルにて開催しました。 郵政省の田中技術総括審議官の開会のあいさつ、協賛の沖縄県から稲嶺知事(与儀企画開発部長代読)、恩納村からは大城村長、琉球大学からは山城工学部長のあいさつをいただきました。その後、坂田東海大学教授による基調講演「沖縄-新しい地球観測地への期待」、仲里県立看護大学教授の講演「人から人へ」、宮城琉球大学教授の講演「IT革命と亜熱帯環境情報」が行われました。さらに、増子地球環境計測部長ほかによる通信総合研究所における環境計測と情報通信の研究計画の紹介のあと、翁長琉球大学名誉教授、上原県企画開発部参事、住東京大学気候システム研究センター長、平東京大学海洋研究所長によるパネルディスカッション「沖縄における亜熱帯環境と情報通信への期待」を開催しました。
(沖縄電波観測所長) |
||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||
|
|
|

|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||