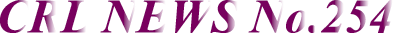
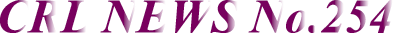
−ありがとうございます、そしておつかれさまでした−
企画部総括主任研究官 外部評価事務局
富田 二三彦
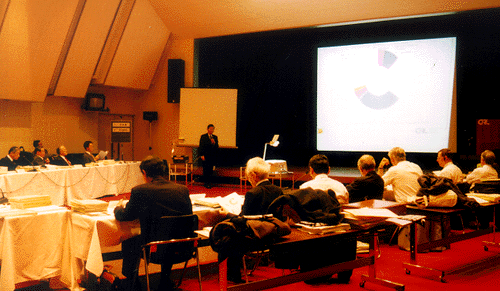
通信総合研究所(CRL)は、理化学研究所の有馬朗人理事長を委員長とする総勢51名(延べ60名)の外部評価委員により、平成8年度に外部評価を受けました。CRLの外部評価は7つの研究部門に対する研究評価と、それを受けた後の研究所全体に対する運営評価の2つにわけて行われ、かつそれぞれの評価とも書面審査と委員会審査の2段階で評価が行われたところに特色があります。また、外部評価を受けた国立試験研究機関としてもトップ集団の中にあります。
1. はじめに
まずはじめに「評価(Evaluation)」という言葉は、ある目的があってそれに値するか否かを評する場合に使用するものであり、例えばあるグループがある研究を推進するに値するか否かを判断するのは「評価」です。しかしながら、あるグループの状況を審査して、おまけにその進むべき道を助言したりすること(例えば小・中学校の通信表)は「審査(Review)」であって「評価」ではありません。今回当所が行った外部評価の場合、研究部門によりEvaluationとなったところも、Reviewが主となったところもあり、それを受けて行った所全体の運営評価はどちらかというとReviewが主体でした。このようにEvaluationとReviewが混在していることを承知の上で、日本語で「外部評価」、英語では主に「Review」を使用していることをお断りします。
2. なぜ外部評価を受けるか
国立試験研究機関(国研)は、国全体で必要であるが、民間ではやらないかやれない研究を行う場所です。CRLの場合、郵政省に設置された研究所で、主に郵政省を通じて国の予算を使用する必要性と目的を持った組織ですから、CRLで行われる研究活動がある方向性を持ち、それを保つために研究の「管理」があるのは当然です。一方、自由な発想から新しい物や技術や知識を生み出すために研究者は多くの場合「自由」を希求し、そもそも何が出るかわからない研究を「管理」することはできないと考えています。また、研究にはさまざまな面で「フレキシビリティ」が必要であるのに対し、行政機関としての国研には、国の予算が正当に使用されていることを常に明らかにしなければならない「制約」もまた課せられています。
つまり国研は、「管理と自由」、「フレキシビリティと制約」という研究に関する矛盾を生まれながらに持っているので、もともと運営が難しく、かつその運営は、経済・社会や科学技術の動向等により常に見直していかなければなりません。このようなチェックや見直しは当然所内のしかるべき方針決定組織で行われてきたものですが、今後新たな研究分野を開拓し先端研究をめざす国研としては、従来の自己点検だけでは不十分で、定期的な外部からの評価とその公開が特に必要になってきました。
3. 外部評価の背景
郵政省 電気通信技術審議会の第85号答申「技術創造立国に向けた情報通信技術に関する研究開発基本計画について」においては、我が国の科学技術に関して、これまでのキャッチアップの時代は終焉を迎え、今後は、未来を切り拓いていかなければならない時機を迎えていると認識されています。つまり、これまでは、先行している諸外国の研究状況をサーベイしてノウハウを取り込み、更に改良して世界一をとるというような研究サイクルであったものを、世界に先駆けて研究領域を開拓していく、無から有を生み出せるように研究のスタイルを変革していかなければならないということです。
また、先の科学技術基本法に基づく科学技術基本計画においては、新しい時代に向けて、新たな研究開発システムを構築するとともに、大学・研究所等、官・民等、国内・外等の連携・交流の拡充、強化を図り、また研究開発に関し厳正な評価を実施することによって、我が国全体の研究開発の抜本的な活性化を図るとされています。つまり、科学技術創造立国をめざして政府の研究開発投資額を大幅に増やすが、そのカウンターパートとして厳正な評価が必要であるということです。
4. CRLにおける外部評価の目的
かつて、電電公社の民営化に伴ってCRL(当時は電波研究所、RRL)が有線分野の研究も担当することになり、研究分野は飛躍的に増大しました。また、予算も1978年頃から1991年頃までの冬の時代の後、科学技術基本計画等による追い風を受けて近年急速に改善されつつあります。ところが研究者数はここ20年間横ばい状態にあり、近年の情報通信基盤研究へのさらなる研究分野の拡大にもかかわらず改善の見通しはありません。CRLにとってこのような深刻な構造的問題「要員不足の中での研究分野の拡大」に、今後どのように対処していくべきかが課題となっています。
また、近年の予算拡大は主に情報通信基盤研究に関するユーザー・オリエンテッドな研究開発への要請に基づくものです。CRLが国立研究所としてこのような要請にいかに応えていくべきか、つまり「ユーザー・オリエンテッドな研究の立ち上げを国研でいかに行っていくべきか」はCRLのもうひとつの課題となっています。
すでに述べたような社会的な背景と、CRLのこのような状況を踏まえ、これまでの研究活動とその成果並びに今後の計画について、外部専門家及び有識者により外部評価を行う必要があると考えられます。更に、その結果を一般に開示することは、国研としてのCRLの存在意義と社会的役割について国民の理解と信頼を得、研究活動をさらに活性化して優れた成果をあげていくことにつながると考えられます。
いずれにせよCRLは国立の研究機関ということで、それなりの額の公的資金により研究の継続性が一応保証されています。よってそこで行う研究には責任が伴い、自らの研究状況及び第三者による研究の評価結果を一般に開示するのは当然の義務と考えられるのです。
5. 外部評価委員会の構成と審議事項
評価は、外部評価委員会において、研究評価委員会と運営評価委員会に分かれて実施されました。
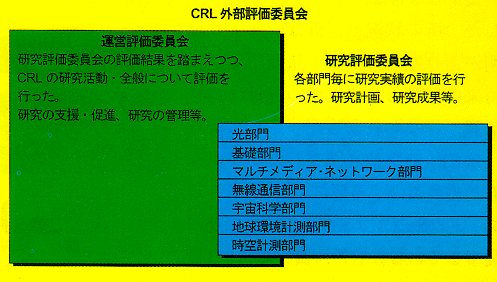
5.1 研究評価委員会について
研究評価委員会では、7つの専門分野に分かれて主に研究計画や研究成果等について各部門毎に研究実績の評価が行われました。7部門は光部門、基礎部門、マルチメディア・ネットワーク部門、無線通信部門、宇宙科学部門、地球環境計測部門、時空計測部門です。CRLにおける研究分 野が拡大しているため、このようにいくつかの部門に分けて研究評価を行うことは必然ですが、部門に分けたことによりいくつかの困難が待ち受けていました。
第一の難関は委員の選出です。研究評価委員の人選については、外国からの委員を含める、部門により民間の研究者を含める、またできるだけ第三者からの評価を受けるため、委員長にはCRLの客員研究官を指名しないという方針により、各研究分野の専門家を各々4〜10名選出して委員への就任を依頼しました。ところがこの研究評価は、主に各研究部門の成果等を中心に評価していただくものなので、それぞれの分野の国際レベルの専門家ということも考えなければなりません。その結果、これまでCRLとつながりのあった先生も含まれたり、部門間で先生の取り合いになったりすることもありました。この点については、分野による研究者の層の厚さの違い等もあり、致し方なかった考えます。
第二の難関は、どの研究グループがどの分野で評価を受けるかという判断です。これについては評価委員の案を呈示しながら個々の研究グループとも相談して決定しました。その結果、学際的な研究を行っているグループでは、ひとつの研究室のスタッフがそれぞれ別の部門で評価を受けるというような事態も発生しました。
最後の難関は統計データを作成する際に発生しました。後で述べる運営評価では各研究部門の性格や研究状況の違いも審査の対象となります。各部門の研究者数や予算額や成果の量を算出するため、ある程度大雑把な分類をせざるを得なかったことをここでお断りしておきます。つまり、運営評価委員会のための資料においては、部門間での論文数等の成果のダブルカウントを避けていますが、運営評価資料における各部門毎の数値は、各研究部門毎に作成した個別資料の数値とは必ずしも一致していません。
5.2 運営評価委員会について
運営評価委員会では、研究評価委員会の評価結果を踏まえつつ、主に研究の支援・促進、研究の管理等研究活動全般について評価が行われました。委員については、先ず委員長を理化学研究所の有馬理事長にお願いし、産・学・官の有識者に人文系の有識者を含める、外国でCRLに近い研究分野の研究所長を含める、研究評価と同じくCRLの客員研究官は指名しないという方針で、委員長と相談の上各委員を選出し、委員への就任を依頼しました。
実際、外国人以外に、官の代表としては、科学技術庁の科学審議官にお入りいただき、民間からも経団連の産業技術懇談会の主査やNTTの研究開発本部長にも、大変お忙しいなかご参加いただきました。また、経済学の先生やマスコミの記者の方にもご参加頂き、広い分野の皆様から貴重なご意見を頂くことができました。
外部評価委員会全体の構成を図1に委員名簿を表 1に示します。
[総勢51名(延べ60名)、内国外委員14名(外国人10名)]
6. 評価のスケジュール
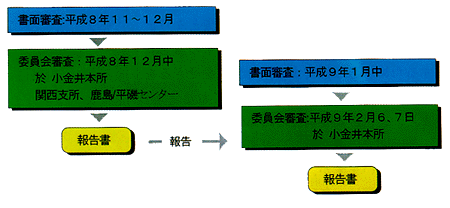
運営評価委員会、研究評価委員会ともに、評価は文書による審査、及び委員会開催時の討論や面接による審査の両者により行いました。ま ず、CRLより評価用資料が各委員宛て送付され、事前に評価票に評価結果を記入して回収しました。
6.1 研究評価委員会について
研究施設の見学や研究職員と直接対話するために、委員会を各部門ごとに1回開催しました。1996年12月の1〜2日間、通信総合研究所(東京都小金井市)及び鹿島/平磯センター及び基礎部門のみ関西支所(兵庫県神戸市)において開催しました。
6.2 運営評価委員会について
CRLの見学や職員との討論を行うために、委員会は、1997年2月6日、7日に通信総合研究所において開催されました。委員会席上、各研究評価委員会委員長からは各部門での評価報告の概要が紹介されました。所の状況や運営は幹部より説明があり運営に関する諸問題並びに将来の展望も含めた所の方針につき討議が行われました。さらにより一層CRLの実状を調査したいという有馬委員長のご希望により、6名のポストドクトラルフェロー、定常業務に従事している5名の所員、更に2日目には、6名の研究リーダーより、それぞれの研究や業務に関する問題点や要望事項について報告を受け、議論が行われました。このような現場の研究者と評価委員との直接対話は各研究部門でも行われましたが、今回のCRLの外部評価の特色のひとつです。スケジュールの全体像を図2に、評価委員会の模様を写真1、写真2に示します。

写真1 運営評価委員会 |

写真2 評価委員 所内視察 |
7. 評価委員会を終えて
全体として評価された点と同時に厳しい意見や有益な助言が評価委員より与えられました。特に、研究部門により、基礎を標榜するならば論文数が多くないこと、一方、国立研究所の役割である、行政から見て国民に役立つことを行う部門に対しては、論文だけではない評価基準が必要であるという意見がありました。主に評価された点及び主な助言を、外部評価委員会報告書より抜粋します。
7.1 主に評価された点
7.2 主な助言
8. おわりに
外部評価の結果、国研としての役割や研究ベクトルの絞り込みなどに関して多くの助言が与えられました。これに応えて対応(アクションプログラム)を実施し、今後も引き続き国研としての役割を明確にしつつ、いくつかの課題に沿った研究を行っていくことになりますが、一方、職員ひとりひとりの頭の中の発想は自由です。「与えられた課題研究を遂行する途中の自由な発想から、往々にして優れた研究が生まれ出ること。また、課題研究を推進するためにはそれを支える優れた基礎研究が必要であることを考え、できる限り研究のしやすいフレキシブルな環境作りをめざしていくべきである。」これが今回の外部評価で得られた大きな教訓のひとつと思います。
最後に、研究職職員が約300名の研究所に対して延べ60名もの外部評価委員にお集まりいただきました。時には文字にし難いような、歯に衣も何も着せないような貴重なご批判やご意見をいただきましたことを心より感謝いたします。職員の側も、外部評価に対応するため通常の研究や業務に追加して多くの仕事が課せられました。もちろん評価を受けたことによるプラスの面もあり、また外部から評価していただくことは国研の責務とはいえ、マイナス面とプラス面のバランスから考えると、多大の準備を必要とするような外部評価は少なくとも数年間隔にすべきであるという感想があります。