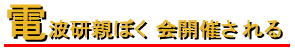今回は『研究往来』始まって以来、初の女性研究員の登場です。明石海峡を間近にのぞむ神戸市西区のCRL関西先端研究センター。田中さんはそこで“原子”というミクロの世界の実験に携わっています。
「このセンターは、明日あさってに役立つというよりは、10年、20年といった長いスパンで、情報通信技術のベースとなる先端技術の基礎研究を行う目的で設立されたと聞いています」
関西先端研究センターは1989年に設立され、今年で10周年を迎えます。田中さんの説明の通り、長期的な視野に立って情報通信の高度化を目ざす、最先端技術の研究を進めています。情報系、物性系、バイオ系の3分野を主な研究テーマとしていますが、田中さんの所属する電磁波分光研究室は物性系の研究室で、6名の研究員がいます。
「レーザーを使って、原子レベルで物質を制御したり計測したりしようというのが私の研究です。原子のなかでも電荷をもった状態の原子をイオンといいますが、これをレーザーで冷却することによって、動きを制御し、精密な測定をしやすくします。原子を理想的な状態にすることができれば、将来は高性能デバイスの開発につながるかもしれません」
一般には解りにくい研究の内容を、かみくだいて丁寧に説明してくれる田中さん。親しみやすい雰囲気とハキハキした話し方がとても印象的です。
「高校時代に物理に興味をもってから、学生時代を通して、同じ分野の研究に関わり続けることができたのはとてもラッキーですね。物理をやっている者として、常に物質に接していたい、実験に携わっていたいという思いがありましたが、ここは設備も充実しているので、仕事をしながら『この手で原子を操作しているんだな、ミクロの世界と関わってるな』という実感をもつことができます」 |
 | | 手にしているのはイオントラップ電極の模型 | 入所前にセンター内を見学したとき、館内の設備や実験機器を見て「こんなところで実験できたらいいな」と思ったといいます。希望がかない今は実験に明け暮れる毎日。自分自身、恵まれた研究環境にいるということは自覚している。しかし、だからといって「毎日が楽しい」とばかりは言えないという田中さん。
「仕事の時間は自分でコントロールしやすいのですが、朝から実験の準備を始めてもうまくいかず、夜になって、やっと条件が整ってくるなんてこともよくあります。そういうときは夜遅くまで仕事を続けることもあります。実験というものは自然が相手だから、なかなか自分の思い通りにはいかないんです。むしろ、うまくいかないことの方が多いぐらいです。でも七転八倒し、試行錯誤しながら進めていくうちに、フッとうまくいく瞬間がある。それがあるから続けていられるのかもしれないですね(笑)」
CRLのなかでもまだまだ少ない女性研究員。しかし、田中さんはそんな環境を嘆くこともありません。
「大学から大学院と、上に進むごとにまわりに女性が少なくなっていくんです(笑)。“研究者”というのが、女性の職業の選択肢から自然に消えていくんでしょうね。でも、センターの一般公開のときに『こういうところに入るには、どうすればいいんですか?』なんて真剣に聞いてくる高校生ぐらいの女の子もいたりして…。がんばってほしいですよね」
この研究センターに入ってから、田中さんのライフスタイルにもちょっとした変化が。 |
 | | 目下の気分転換はこの車で | 「子どもの頃から20数年習っていたピアノが趣味だったんですが、寮に入っているので、たまに部屋で電子ピアノを弾くぐらいになりました。ここに来てからはむしろ、アウトドアにめざめました。テニスを始めて合宿にも参加したり、明石の海に行って、1日浜辺で過ごしたり。最近、初めてバッティングセンターに行って、楽しい所だということも発見したし…」
のんびりした田園風景の残るセンターの周辺。山に囲まれた京都育ちの田中さんには、海に面した明石という土地はすこぶる快適だそう。
「海が近いのはいいですね。海のものはおいしいし、浜辺で遊べるし。気分転換にはとてもいいです」
そんな田中さんが今、一番楽しいのは新車のハンドルを握っているとき。10年乗っていたクルマを昨年、思いきって買い替えました。
「嬉しくてあちこち走り回っているんです。この前は気がついたら鳥取まで行ってしまって(笑)。オフのときは、研究とまったく違うことをやってみるのがいいみたいなんです。そういうときに研究のヒントが浮かんだりするので…」
どこまでも研究熱心な田中さん。
将来の目標は?
「10年、20年経っても、同じように研究が続けていられたらいいな、と思いますね。研究テーマにしろ、実験にしろ1度離れてしまうと、とても敷居が高くなってしまう気がするんです。この研究センターのなかにも、お子さんを育てながら立派に研究と両立させておられる方がいます。そういった先輩をお手本にして頑張らなくっちゃ、と思います。」 |
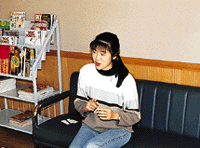 「科学とは同じ条件のもとで行ったら、誰がやっても同じ実験結果が得られるという客観的なものである必要があります。しかし、『実験が成功しました、だからここで終わります』ということではない。何かひとつ解れば、そのもっと先が知りたくなるし、もっといいものをつくりたいというのが研究の基本的な流れだと思うんです。ひとつの疑問が解明できれば、また新しい疑問が出てくる。実際、基礎研究ってすごく泥臭い部分もありますし…。ただいつも思うのですが、今の私達の生活を支えている科学技術って、もとをたどれば基礎研究によって得られた技術の積み重ねです。これまでに私達がこのセンターで上げてきた成果も、そういった“積み重ね”の一部なわけですね。ですから現在私が取り組んでいる研究も、将来実用化され、社会の役に立つことを見届けられたら、それはとても幸せなことですね。そのとき、『ずっと好きなことをやってきてよかったな』って思えるかもしれません」 「科学とは同じ条件のもとで行ったら、誰がやっても同じ実験結果が得られるという客観的なものである必要があります。しかし、『実験が成功しました、だからここで終わります』ということではない。何かひとつ解れば、そのもっと先が知りたくなるし、もっといいものをつくりたいというのが研究の基本的な流れだと思うんです。ひとつの疑問が解明できれば、また新しい疑問が出てくる。実際、基礎研究ってすごく泥臭い部分もありますし…。ただいつも思うのですが、今の私達の生活を支えている科学技術って、もとをたどれば基礎研究によって得られた技術の積み重ねです。これまでに私達がこのセンターで上げてきた成果も、そういった“積み重ね”の一部なわけですね。ですから現在私が取り組んでいる研究も、将来実用化され、社会の役に立つことを見届けられたら、それはとても幸せなことですね。そのとき、『ずっと好きなことをやってきてよかったな』って思えるかもしれません」 |
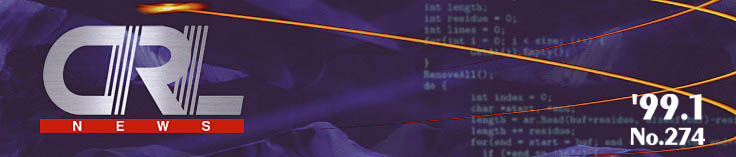
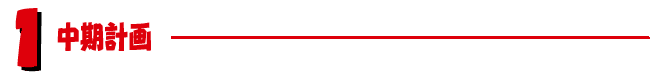
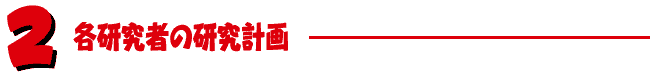
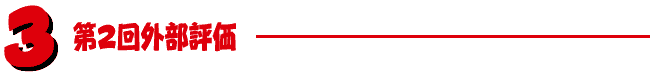
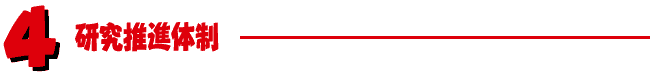
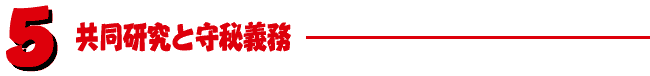
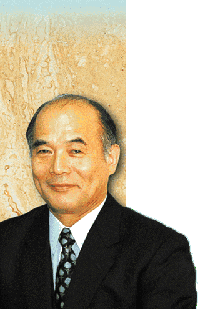 明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。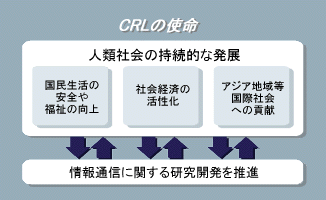

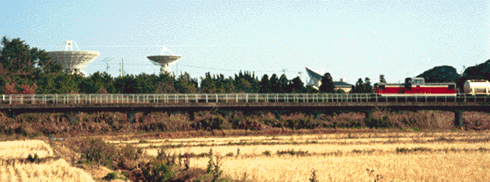
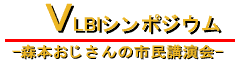
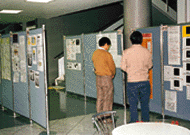
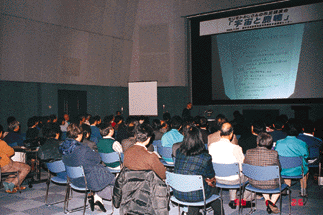

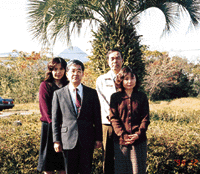

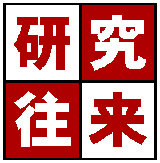
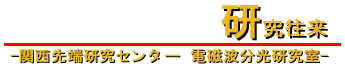
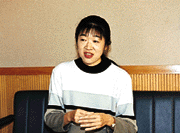


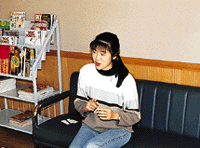 「科学とは同じ条件のもとで行ったら、誰がやっても同じ実験結果が得られるという客観的なものである必要があります。しかし、『実験が成功しました、だからここで終わります』ということではない。何かひとつ解れば、そのもっと先が知りたくなるし、もっといいものをつくりたいというのが研究の基本的な流れだと思うんです。ひとつの疑問が解明できれば、また新しい疑問が出てくる。実際、基礎研究ってすごく泥臭い部分もありますし…。ただいつも思うのですが、今の私達の生活を支えている科学技術って、もとをたどれば基礎研究によって得られた技術の積み重ねです。これまでに私達がこのセンターで上げてきた成果も、そういった“積み重ね”の一部なわけですね。ですから現在私が取り組んでいる研究も、将来実用化され、社会の役に立つことを見届けられたら、それはとても幸せなことですね。そのとき、『ずっと好きなことをやってきてよかったな』って思えるかもしれません」
「科学とは同じ条件のもとで行ったら、誰がやっても同じ実験結果が得られるという客観的なものである必要があります。しかし、『実験が成功しました、だからここで終わります』ということではない。何かひとつ解れば、そのもっと先が知りたくなるし、もっといいものをつくりたいというのが研究の基本的な流れだと思うんです。ひとつの疑問が解明できれば、また新しい疑問が出てくる。実際、基礎研究ってすごく泥臭い部分もありますし…。ただいつも思うのですが、今の私達の生活を支えている科学技術って、もとをたどれば基礎研究によって得られた技術の積み重ねです。これまでに私達がこのセンターで上げてきた成果も、そういった“積み重ね”の一部なわけですね。ですから現在私が取り組んでいる研究も、将来実用化され、社会の役に立つことを見届けられたら、それはとても幸せなことですね。そのとき、『ずっと好きなことをやってきてよかったな』って思えるかもしれません」