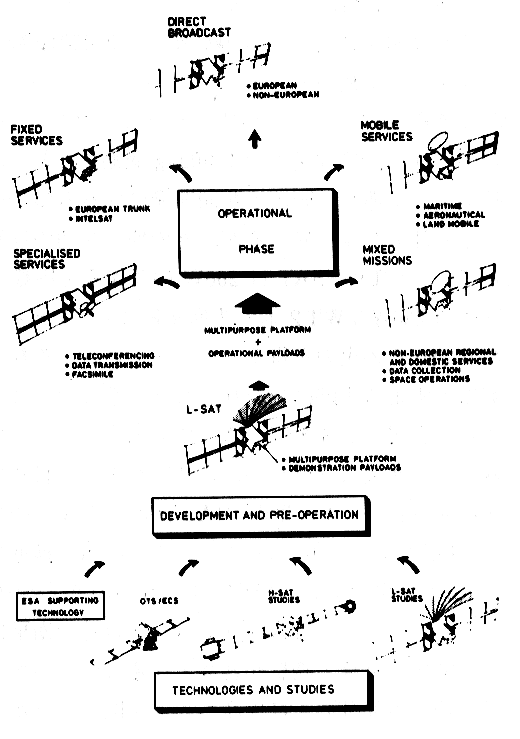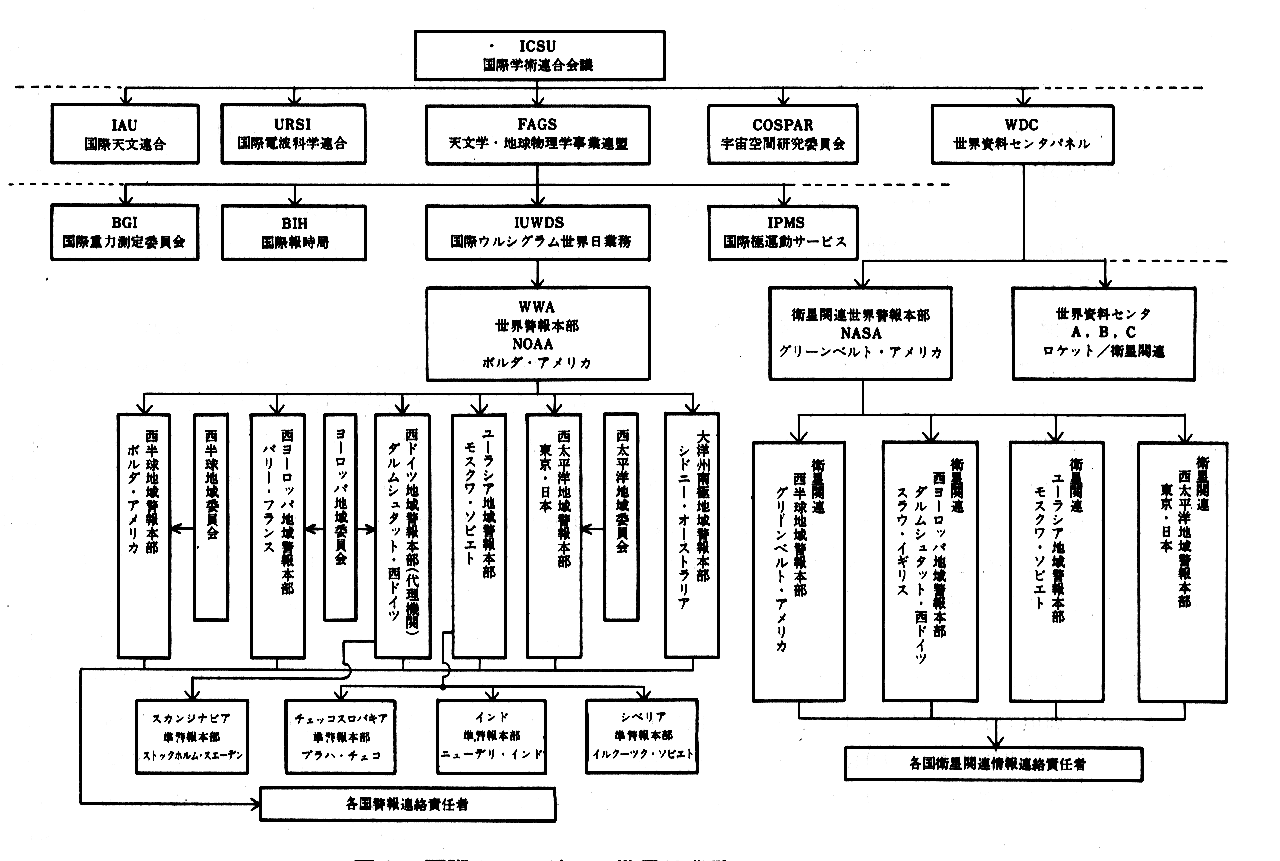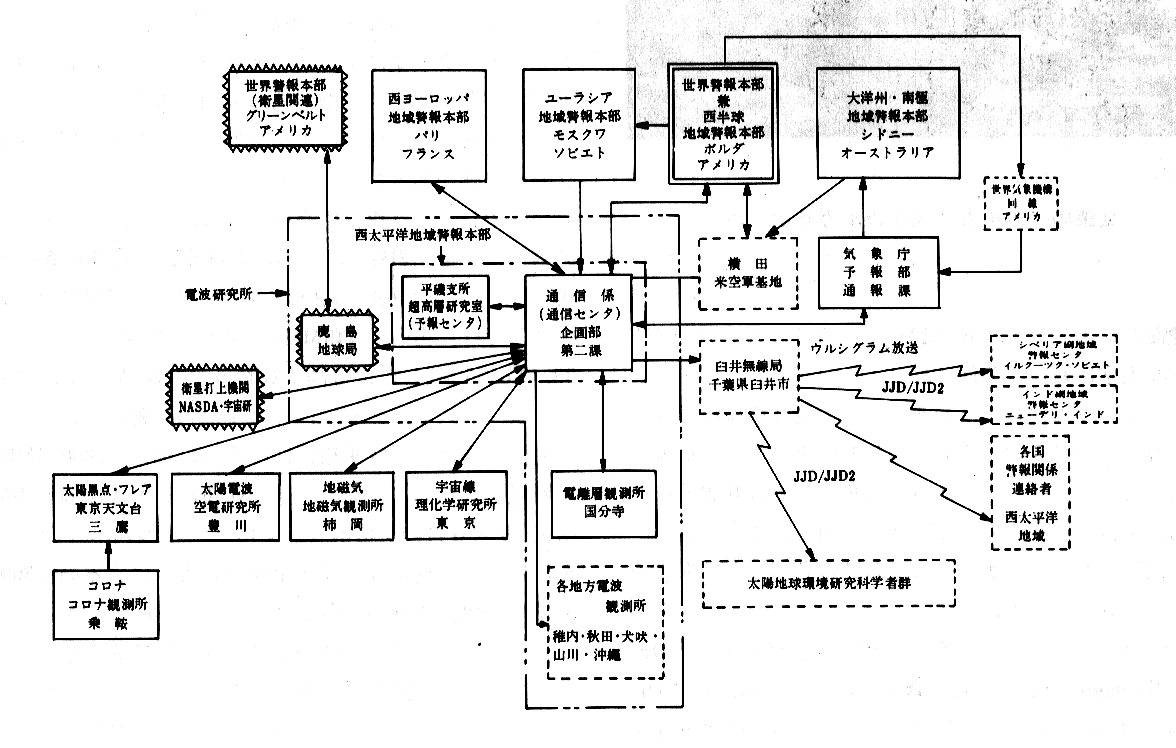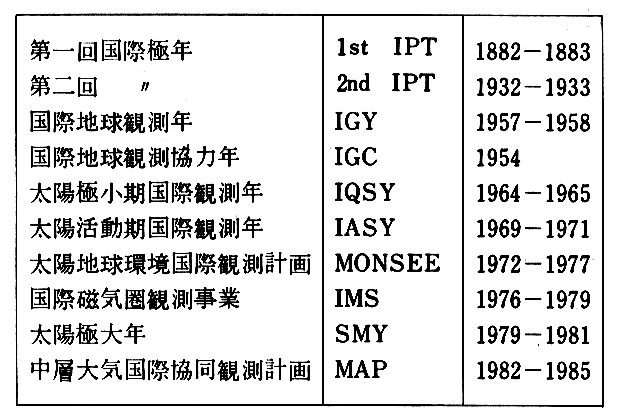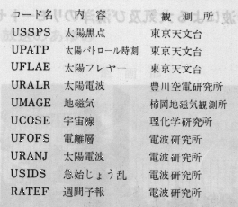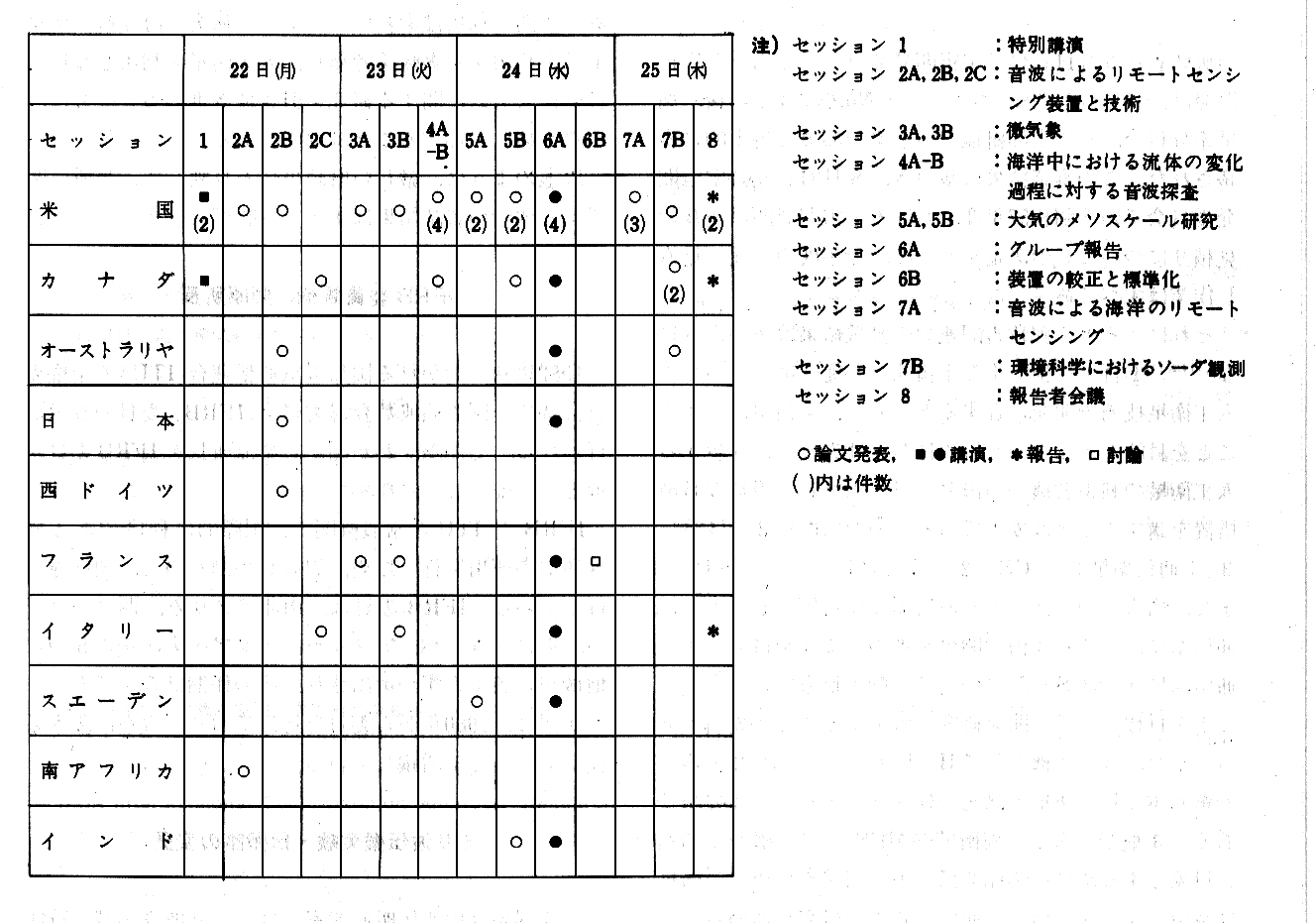世界の放送衛星開発の動向
衛星通信部
はじめに
昭和53年4月8日に打上げられた,わが国初の実験用
中型放送衛星(BS「ゆり」)による実験は順調に進行して
いる。58年度には実用放送衛星(BS-2)が打上げられる予
定であり,さらには第二世代のわが国放送衛星の構想や
展望をねりあげる段階に来ている。こうした状況をふま
えて,世界各国の放送衛星開発計画の動向をさぐってみ
たので,その概要を紹介する。
各国の衛星開発の動向
ここでは各国別に,①これまでの開発実験経過,②今
後の開発計画,③ポリシーの順に解説する。
(a)カナダ
カナダはこれまで,通信技術衛星(CTS)と通信放送衛
星(ANIK-B)による放送衛星実験を行っている。CTSは
ちょうどわが国のBS規模のもので,1976年1月に打上
げられ,約4年間にわたりアメリカと共同で実験が行わ
れた。CTSの静止軌道上の重量は345㎏,バイアスモー
メンタムの三軸姿勢安定方式で,200WTWT1個と20W
のTWT2個を搭載している。実験内容は12/14GHz帯
によるテレビ放送.逆方向チャンネル(音声等)を持っ
た教育テレビ,電話やディジタル通信のほか,医者向け
の医学教育番組や,遠隔診断の実験も行った。CTSに
はいくつかの不具合が発生したが,その主なものは(豗)
打上げ5か月後,静電放電に起因すると思われる太陽電
池アレイの破壊が起こり,電力容量の15%が失われた。
(豩)テレメトリ受信信号強度は約-113dBmの設計であっ
たが,ミッション遂行に入って間もなく-145dBmまで下
り各種コマンドに苦慮したこと,などである。しかし,
本実験で12/14GHz帯による衛星放送の有効性と柔軟性が
確認されたとしている。
ANIK-BもまたCTSと同様,展開型ソーラー・アレイ
をもった三軸姿勢安定衛星である。1978年12月に打上げ
られたANIX-Bの目的は国内用の直接放送(12/14GHz
帯)と通信(4GHz帯)のための衛星である。この衛星の最大
の特徴は,高々20WそこそこのTWTAによって直接放
送を実現しようとすることである。これはCTSによる実
験で,この程度でも質の高い受信が可能であるというこ
とが判明したためである。CTSと同様の12GHz帯で,
四本の円形ビーム(ビーム幅2°)によってカナダ全土を分
割してカバーする。ビームの内側では直径1.2m,ビーム
周辺では直径1.8mの受信アンテナによって十分満足で
きるテレビ画像が得られる。実験結果によるとスレッシ
ョルドの2dB以上では評価4(良い)程度の画像が得ら
れている。スレッショルド付近でも評価3と4の間ぐら
いにあり,画像はスレッショルドの下でもまだよく見え,
画質の低下は強雨時の短時間の場合以外はがまんのでき
るものであるとしている。カナダは人口の約75%が都市
部に集中しており,平均10数チャンネルのケーブルテレ
ビジョンを持っている。したがってカナダにおける直接
放送衛星(DBS)は,人口密度の低い所の人々約600万を
その対象としている。
今後の計画としてはANIK-Cがある。これはANIK-Bと
は異なってスピン安定の衛星で,カナダ南部におけるテ
レビジョン中継用と大容量の通信需要に応えるものであ
る。衛星搭載の中継器は,1チャンネルが54MHz帯幅の
16のRFチャンネルに分割される。一つのチャンネ
ルは出カ15WのTWTを使用しているので,総出力は約
240Wとなる。衛星の送信アンテナのカバレッジは楕円形
の四つのビームによってカナダ、を分割カバーする。 AN
IK-Cはシャトル又はデルタ3910のどちらででも打上げ可
能の設計となっており,1981年11月に打上げの予定であ
る。
カナダは欧州宇宙機構(ESA)の準加盟国として宇宙
開発にとりくんでいるが,打上げロケットの開発は行わ
ず,アリアンやシャトル等他国のものに頼ることとして
いる。衛星については,国内のニーズを主体に設計・製
作を行い,国内の宇宙産業を刺激するとともに,輸出市
場への能力をも身に付けようとしているとみられる。
(b)ESA
ESAは1975年4月に設立された。フランス,西ドイツ
の他・計11か国が加盟している。フランスが64%を出資,
西ドイツが20%,他は5%以下となっている。ここでは
ESAの衛星の他,加盟国単独又は共同の衛星もとりあげ
る。
ESAの軌道試験衛星OTS-2は,1978年5月に打上げ
られた。打上げ時重量は865㎏であった。OTSは11/14
GHzを用いた通信衛星であり,将来の放送衛星にもその
適用が可能な衛星技術及び通信設計思想を確立するため
の試験衛星である。OTS-2には二つの競合する技術が
搭載された。例えば,直線及び円偏波のアンテナ,TWT
用の二種類の電源,二種類のモーメンタムホイール等で
ある。衛星搭載中継器は11/14GHz,出カ2oWの6チャ
ンネルである。OTSは3年目の運用に入っても順調であ
る。OTSの本来の業務は,静止位置保持マヌーバ,熱制
御,電力管理の三つであるが,各種のサービスのデモン
ストレーションを実施した。実験期間中,OTS-2にい
くつかの不具合が発生した。その主なものは,(豗)静止
軌道に入って2〜3か月後にTWTAが一台故障した(こ
れは多分ポッティング内のクラックに高圧のアークが飛
んだことによるものと考えられている),(豩)2台のTW
TAが独立に数回,自然にスイッチオフとなった,等々
である。OTS-2による実験で得られた結果は満足すべ
きものであり,ヨーロッパ通信衛星(ECS)等の設計に十
分反映したとしている。
なお,OTSに先立ち仏・独共同開発の静止通信衛星
SYMPHONIE:静止軌道重量230㎏,設計寿命5年,三
軸安定,液体アポジの採用)によっても同様の実験が行
われていることを付記しておく。
今後の衛星開発計画は1,000㎏級から2,000㎏級のも
のまで連綿として続いている。
TV-SAT(西ドイツ)とTDF-1(フランス)は,それ
ぞれの国内向け直接放送用の1,000㎏級衛星(トランス
ファ軌道上)であり,両国の共同開発に成るものである。
ミッション部分が多少異なるが,その他は共通の技術を
利用している。TV-SATは260WのTWTを搭載し,
TDF-1は230W TWT2本の並列運転により1チャンネ
ルあたり350Wの出力を得ることとしている。それぞれ
が準実用と実用の段階に分かれており,準実用では3チ
ャンネル,実用では5チャンネルで運用することになっ
ている。この衛星にはいくつかの特徴があり,目新しい
技術が投入されている。TV-SATは別々の3つのモジ
ュール(通信モジュール,サービスモジュール,推進モジ
ュール)に細分化できる。TDF-1は5つのモジュールに
分割できる。こうした方式はヨーロッパ以外の衛星にも
見られ,製作・試験・調整が容易となるほか,バス系な
ど共通に使える部分の大量生産への道を開くことができ
る。TV-SATを例にとるとさらに次のような特徴的技
術があげられる。(豗)統一化推進システム(UPS)の採用,
(豩)トランスファ軌道から三軸姿勢安定化の適用,(豭)
イオンエンジンの採用,(豳)超軽量ソーラ・アレイ(UL
P)の採用。(豗)は従来の固体アポジモータと姿勢制御
用の液体推進システムを統合したものである。(豩)は(豗)
によって可能となるものであり,静止軌道投入にあたっ
てスピンフェーズを含まないので,スピンフェーズ用の
装置を必要としない。(豭)は水銀等の分子をイオン化さ
せ高電圧で加速し推力を得るもので,衛星重量を大幅に
軽減する。(豳)は強固なカーボンファイバーフレームか
ら成り,重量は0.7㎏/㎡で1㎏あたり40〜60Wの電力
を発生する。衛星の寿命は7〜10年で,さらに改善し
た技術を用いれば10〜12年に延びるという見通しも持
っている。TV-SAT/TDF-1は1983/84年にアリアン
で打上げられる予定である。ただしシャトルによる打上
げも可能な設計となっている。
1,000㎏級の衛星としては他に,実用通信衛星のECS,
海事衛星(MARECS),フランス独自の計画である国内用
静止通信衛星(TELECOM-1)などがあげられる。ECSは
OTSを踏しゅうしており,寿命(7年),容量(電話2万ch),
等がスケールアップされている。TELECOM-1はフラ
ンスの海外領へのテレビ伝送をはしめとしたミッション
を含んでいる。ここで鍵となる考え方は,OTSやECS
に使われたバスが,MARECSやTELECOM-1にも
利用されるということである。ミッション要求にあわせ
て多少の修正はなされるが,このようにして本質的には
同一の衛星を大量生産することと同等になる。以上の衛
星は厳密には通信衛星であるが,将来の大型衛星L-S
ATの開発へ吸収,発展させられる内容をもっている。
ESAのL-SATは約2,300㎏(トランスファ軌道上)
の第2世代の大型多目的衛星である。L-SATは直接
衛星放送を含む多様なミッションを搭載するものである。
ESAでは市場調査の結果,近い将来は大型の多目的衛星
の需要が増えるとしており,1983〜94年の間に35個〜60
個ぐらいの衛星が売り込め,そのうち85%は大型衛星に
なるという結論を得た。L-SATはこのような目的に対
応する開発と準実用のための衛星である。衛星には12GHz
のテレビ直接放送用トランスポンダを2本搭載してあり,
1本はイタリアに対する準実用業務(固定アンテナ),も
う1本はヨーロッパ全体に時分割で実験を行うもの(ス
テアラブルアンテナ)である。その他20/30GHz帯でテ
レビ会議等の実験とデモンストレーションを行う。衛星
はやはり3つのモジュール部から構成されており,又U
PSの採用も考慮している。L-SATは順調にいけば,
1984年第1四半期に打上げられる予定である。
ヨーロッパの宇宙開発は,アメリカに比べると相当遅
れて出発しているので,戦略をしっかりと練りあげてい
るようにみえる。ロケットは,初めから2,000㎏級の衛
星を静止軌道に投入できるものをめざしている。各衛星
の開発にムダがない。いろいろなミッションに対応して
一つ一つの衛星を別々に製作するのでなく,バス系など
できるだけ共通に使える技術の開発を配慮している。同
一世代の衛星はミッション目的が異なっても,多くの共通
部分をもち, いわば横の兄弟関係にある。一つ一つの開
発した衛星技術は,次の世代の衛星へ発展・止揚されて
いく関係にあり,縦の世代のつながりにもとぎれがない。
図にはL-SATを軸とした開発フェイズが示してある。
また,衛星は,アリアンによる打上げを前提として設計
しているが,シャトルによる打上げも考慮されている。
以上のことはすべて,宇宙産業の世界市場を念頭にお
いた設計思想であろう。
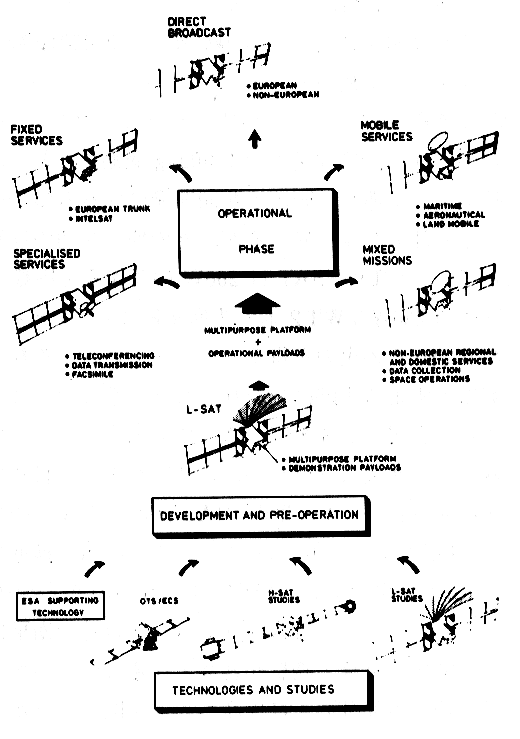
L-Sat衛星の開発
(ESA Journal 1980 Vol.4 No.3)
(c)アメリカ
アメリカは世界で初めての本格的な衛星放送実験を行
っている。それは,1974年5月に打上げられた応用技術
衛星ATS-6によるものである。静止軌道上の重量約
1,400㎏,ゼロモーメンタムの3軸姿勢安定方式(日本の
BSと同じ方式)である。直径9mの展開型アンテナを搭
載しており,2.6GHzで0.9度,860MHzで2.7度のビ
ーム幅を得ている。衛星中継器の出力は2.6GHzで20W,
860MHzで80Wであるが,後者は高出力半導体の並列
運転により得ているのが特徴である。ATS-6そのもの
は南北位置制御は行わないこととしていたが,実験用の
イオンエンジンを搭載して実験を行い,動作は良好であ
った。テレビ放送は2.6GHz帯の2波を使用する。受信
装置はすべて同一のもので,直径3mのアンテナ等から
成っている。実験結果では50dBのS/Nは確保されたと
いう。受信局によってはテレビ画像の他に音声による双
方向通信の機能をもったものもあった。ATS-6による
実験は,ロッキー山脈地区のように面積では30%を占め
るが,人口では4%にしか達しないようなアメリカ国内
の辺地に住む人々を対象として行う保健・教育に関する
衛星放送の実用性を検証するために実施したものである。
実験の内容は,アパラチャ山脈地区,ロッキー山脈地区,
アラスカ地区の小,中,高等学校の生徒や教師向けの教
育番組,また診療所や病院の医師を対象とした番組の伝
送や遠隔診療も行った。双方向通信をとり入れた生番組
により,一方向的になりやすいテレビ授業に生徒の参加
感が高まったとしている。また,関係者の間ではATS-6
規模のものを今後打上げるのはあまりにも高価だとして
おり,むしろ12GHz帯を使用したCTS規模のものに興
味を示しているという。
アメリカでは衛星の製作や運用にあたる実力のある企
業が割拠しており,放送衛星についてはこうしたところ
で種々の構想や計画を打ち出している。そのうちの二,
三をあげてみる。GE社のアメリカ国内向けの放送衛星
の構想では,アメリカ国内を2個又は4個のビームでカ
バーするいわば日本のBSをスケ-ルアップした様な衛
星と,もう一つは,50ほどのマルチスポットビームで国
内をカバーするような衛星である。衛星中継器の出力は
前者が250W,後者が10W又は20Wである。地上受信機
は両方とも同一で,アンテナ径1mで価格300ドルほど
の局である。また,太陽電池発生電力は前者が9,100W,
後者が4,000Wとなっている。マルチスポットビームの
アンテナも軍用として既に開発の実績があるという。た
だ,これらの衛星が経済的に見合うような適当な市場が
いつごろ出現するかということが問題だとしている。
通信衛星会社(COMSAT)では直接衛星放送の具体的
な計画をもち,連邦通信委員会(FCC)にその法的な対応
を迫っている。その計画によると,1985年に東海岸から
サービスを開始し,9か月後には西海岸においても開始,
世界初の有料のDBSをめざしている。 3チャンネルに
よる1日の延べ放送時間は54時間。地上の受信アンテナ
は直径0.75m前後。画質は晴天時はケーブルテレビ並み
で,大雨時には画は見えない。放送周波数は12.1〜12.7
GHzで,衛星の軌道位置は115°W,予備は0.5°離してお
き,事故時でも視聴者はアンテナを動かさずともすむよ
うにする。COMSATの調査によるとテレビが全く見え
ない世帯が120万,1〜2チャンネルしか見えない世帯が
400万を越え,有料テレビを見ていない人々は数千万ほ
ど存在し,遠隔地の問題はDBSでなければ解決できな
いとしている。また,DBSはペイ・ケーブルよりは競争
力が弱いがSTV/MDS(両者とも空中波によるペイ・テ
レビ)よりは強いという予測も行っている。
FCCの行ったDBSに関する政策決定のための予備的
作業の中では,(豗)最近のFCCの規制緩和政策からみ
て,DBSに対しても緩やかな規制を行うのが望ましい。
(豩)DBSを,現存する補充サービス(例えばSTV/MDS)
と同様のものと位置づけ,複合型規制を行うのが望まし
い,(豭)多数の申請に対する解決法としては,競売方式
かすぐれている,などと述べている。アメリカではケー
ブル又は空中波によるペイ・テレビが相当普及しており,
アメリカにおけるDBSは,とりあえずペイ・テレビと
して導入される公算が大きいとみられる。
(d)インド
インドでは,NASAの応用技術衛星(ATS-6)の後半
の1年を借用して,国内の約5,000の村を対象とした教
育テレビジョン放送の実験を行っている。放送内容は農
業技術,家族計画,衛生,学校教育,職業技術等であり,
毎日4時間,二つの言語で放送した。
インドで計画中の国内衛星(INSAT)も,こうした実験
内容を踏しゅうしたものと言えよう。INSAT-1は多目的
衛星であり,共同受信用のテレビ放送の他,固定通信業
務と気象データ業務の三業務を目的とする。放送用とし
ては二つのトランスポンダを搭載し,上りの周波数は6
GHz帯,下りはATS-6と同様2.5GHz帯である。
トランスファ軌道での重量は1,000㎏となっている。ま
た,アポジモータに液体燃料を採用,太陽電池パネルに
対する太陽圧のバランスをとるための太陽セイルを備え
ていることなどを特徴としている。衛星はデルタ3910ロ
ケットとシャトルの両方に適合し,74°Eと94°Eに2個打
上げ,運用は1981年の予定としている。
(e)北欧諸国
デンマーク,フィンランド,アイスランド,ノルウェ
ー,スウェーデンの北欧五か国では,1つでも2つでも
多くの番組を利用したいという共通の要求があり,この
ためDBSを利用する計画がある。DBSによると,さら
に他の方法に比べて次のような利点−(豗)当初からほぼ
100%のカバレッジが可能,(豩)運用開始まで短期間であ
ること,(豭)北欧の他国の番組も利用できる,(豳)費用
も比較的安い,ことなどがあるとしている。地上受信機
のアンテナ径を0.9mとしたとき,衛星中継器の出力は
東部北欧カバレッジの場合450W,西部北欧カバレッジ
(アイスランドのみ)の場合200Wが必要だとしている。
実用化試験期間では,東部,西部がそれぞれ4チャンネ
ル,1チャンネルで運用。実用期には現用衛星2個によ
り,それぞれ8チャンネル,2チャンネルとなる。なお,
軌道予備を1個打上げる。計画では,最初の衛星の打上
げ目標を1983年とするのは可能であるとしている。
(f)ソ 連
ソ連ではモスクワシステムと呼ばれるテレビジョン分
配用システムを開発し,実験を行っている。これは衛星
からの送信124GHz帯を使用するので,地上業務に有害
な妨害を与えないように回線設計され,衛星中継器の出
力は40Wとなっている。地上の受信局のアンテナ径は2.5
m,ビーム幅は±0.1°となっており,複雑な追尾システ
ムを省き,受信システムの簡素化とコスト引き下げを行
っているのが特徴である。中央のテレビプログラムは,
地上回線を通して送信地球局に送られ,12mのアンテナ
で、衛星に送信される。衛星からは'適当なサービスエリ
アへ向けて送信する。その信号は地上ネットワークの地
球局で受信され,ユーザに向けて1W,10W又は100W
で再送信される。これは有線でも分配する。ソ連領内全
部をカバーするには,53°W,90°W,140°Wに配置した
三つの衛星が必要となる。受信地球局の設定は,むしろ
地上系からの妨害を避けるため自然の要害や建物等のし
ゃへい効果等を利用することとしている。実験結果によ
るとモスクワシステムは地上業務にいかなる妨害も与え
なかったばかりか,映像のS/Nは54dB以下とはならな
かったとしている。
おわりに
以上,おおまかにみてきたが,ESAの努力には目を
見張るものがある。科学技術の発展過程は,世界史の流
れにも似て“不均等”に発展してきたし,今後ともその
ように進行するだろう。一国による独走体制が未来永劫,
永久不変に続くものであろうか。ここに後発国の生きる
道もある。宇宙開発は無限の可能性をさえ秘めていると
言える。ユニークなアイデアを出す余地は無限にある。
こうした立場を通していかなる国であっても,その持て
る知恵を出しあい,奮斗努力すれば人類の発展向上に貢
献していくことができるはずである。
(第二衛星通信研究室長 下世古 幸雄)
ウルシグラム放送のあゆみ
企 画 部
はじめに
当所の歴史と共に歩んできた重要な業務であるにもか
かわらずウルシ,ウルシグラムと言う言葉は所内におい
てもあまり知られておらず,漆器に使う漆(うるし)と間
違える人もいまだにある位で,言葉としては聞いていて
も内容はほとんど知らない人も多いことと思われる。こ
の機会に理解を深めていただければ幸いである。
ウルシ(URSI)とは
ウルシ(URSI)とは国際電波科学連合Union Radio Scientifique Internationale(仏語)
の頭文字を取った略
称である。URSIの歴史は大変古く1919年(大正8年)に
出来た組織で,国際学術研究会議の第1回総会において,
電波伝搬及び無線通信に関する研究を促進するために設
立された。事務局はブラッセル(ベルギー)にあって,
現在の加盟国は38か国,総会は3年に1回開催され, 第
20回総会は今年の8月にワシントンで開催され,当所か
らも代表が参加している。なお,日本は第2回総会(1927
年ワシントン)から参加を始め,日本学術会議が加入し,
電波科学研究連絡委員会が連絡対応をしている。
URSIの常設サービス機関として,IUWDS(国際ウル
シグラム世界日業務)があるが,当所の業務と深いつな
がりがあるので別項で説明する。なお,URSIはITU(国
際通信連合)の下部組織であるCCIR(国際無線通信諮問
委員会)とも密接な連絡を保ち,CCIRから要請された
研究課題に応えている。
ウラシグラム(URSIGRAM)とは
URSIにGRAMを加えた造語(他の例で,TELE+GRAM=TELEGRAM,
電報)である。電波の伝わり方に深
い影響がある太陽面上の現象(太陽フレアー,コロナ,黒
点,太陽電波雑音等の異常現象など)や地球及び地球の周
りに起きる現象(地磁気や地磁気嵐,電離層や急始電離
層じょう乱現象,宇宙線など)を観測して,そのデータ
をコード化したものをウルシグラムとよんでいる。そし
てこのウルシグラムはIUWDSの通信網を通じて観測者
相互で毎日データを交換し,無線通信回線の確保,電波
警報,電波予報などに役立てている。
IUWDS(国際ウルシグラム世界日実務)
IUWDSは,International URSIGRAM and World Days Service
の略称である。この組織の仕事を要約する
と,天文学,地球物理学及び宇宙科学の国際的な団体に
対して「活動」を促進し「調整」し「サービス」を行う。この
IUWDSの生いたちは,1957年7月から1年半,67か国
が参加して全世界的な観測網を動員して共同観測を行っ
たIGY(国際地球観測年)が成功裏に終了した後で,IGY
の時の“世界日”プログラムの多くの活動を今後も継続し
ていくために1959年に創立されたIWDS(国際世界日業務)
と1930年頃に創設された迅速データ交換活動を代表する
CCU(ウルシグラム中央委員会,URSIに所属)が合併し
て1962年IUWDSを発足させた。合併後の所属はFAGS
(天文学及び地球物理学事業連盟)になったが,URSIの
常設サービス機関として活動をしている。このIUWDS
のもとに世界中央警報本部(WWA:World Warning Arency米国(ボルダー))
と5つの地域警報本部(RWC)及び4
つの準地域警報本部(ARWC)がある(図1参照)。この5
つのRWCの一つ西太平洋地域警報本部(WPRWC)を日
本(当所に設置・委員長若井登)が担当しており,担当地
域はビルマ,香港,インド,インドネシア,日本,韓国,
フィリッピン,台湾の国々である。地域本部の主な仕事
として日本の場合を例にすると
(1)各地域本部間のウルシグラム情報の交換
(2)ウルシグラム放送による情報の伝達
(3)地域的警報の発令と伝達
(4)世界日警報の収集と伝達
(5)人工衛星に関する情報の収集と伝達
などをウルシグラム通信網(国際テレックス,国際電報,
ファクシミリ,電話等)を通して毎日おこなっている
(図2参照)。
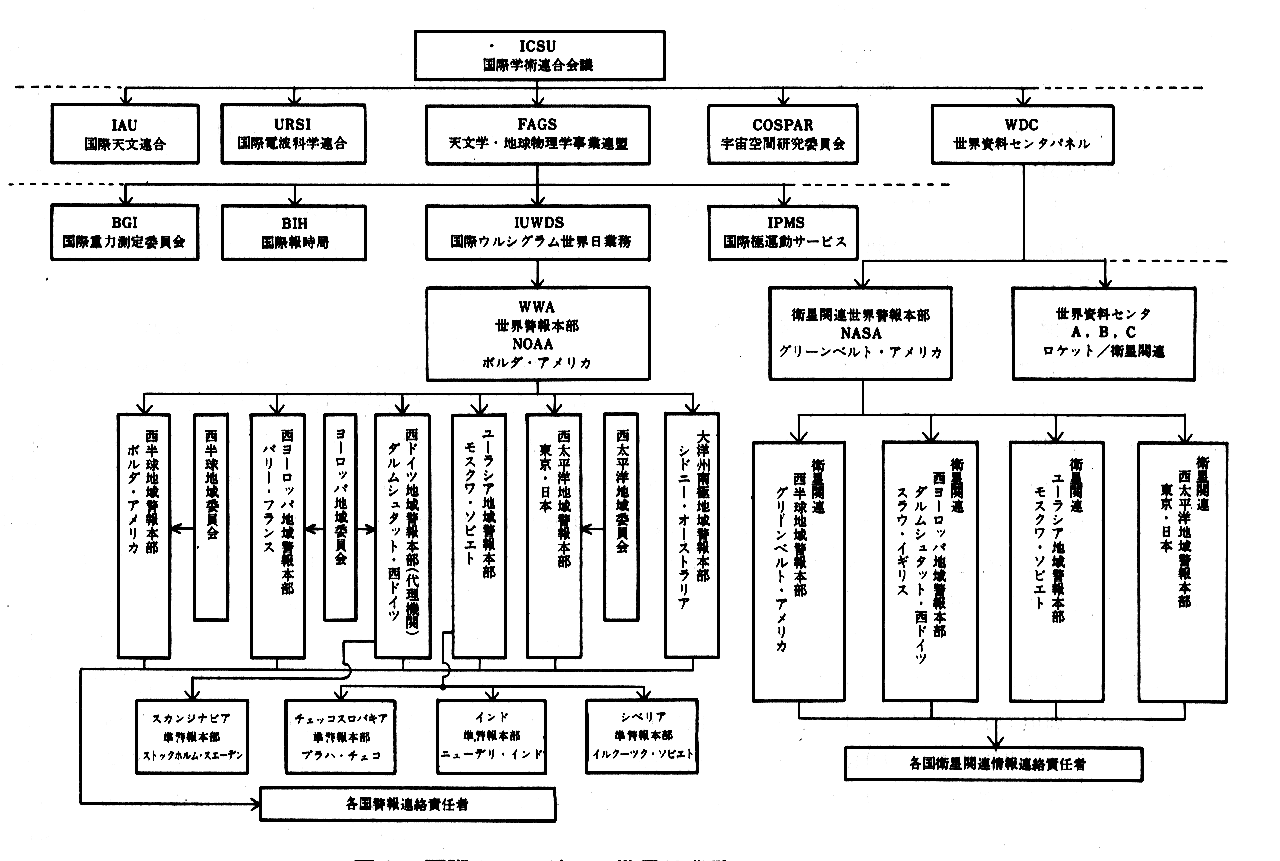
図1 国際ウルシグラム世界日業務ネットワーク
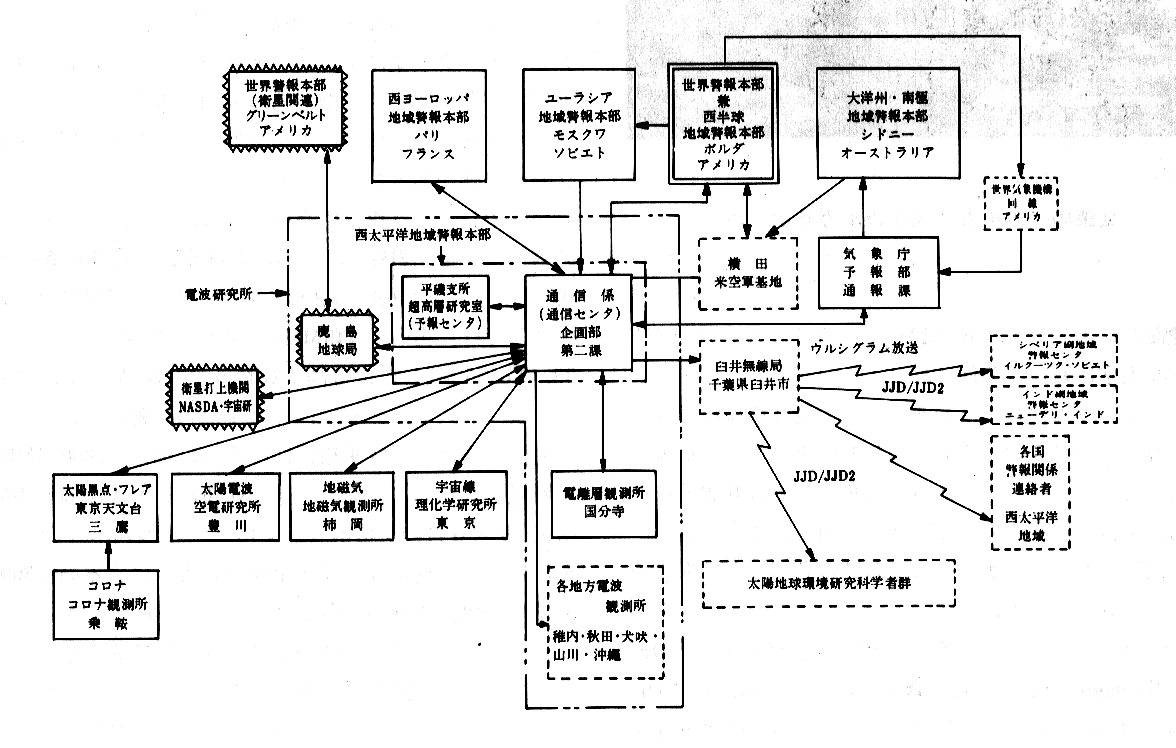
図2 ウルシグラム情報交換組織系統図
ウルシグラム放送と放送スケジュール
(1)ウルシグラム放送の歴史
世界で一番最初のウルシグラム放送は,1928年(昭和
3年)にURSIの勧告にもとづいてフランスで始められ,
現在ウルシグラム放送は,アメリカ,フランス,ソ連,
インド,日本の5か国(7か所)で実施している。
日本におけるウルシグラム放送は1932年(昭和7年)9
月から国際電気KK(KDDの前身)の小山送信所から放送
していたが,第2次世界大戦のため中断された。戦後,
電離層の研究や電波警報の必要性が高まるとともに,第
9回URSI総会の要請により1941年12月25日,当所の前
身である中央電波観測所で再開され,現在に至っている。
送信所は当所構内の一番南側の木造の庁舎に設けられ,
送信機は戦後の物資の少ない折なので方々から部品をか
き集め,苦労して組立てられた。公称3kWの送信機であっ
たが周波数も変動が激しく不安定なものであった。それ
でも8,9MHzで1日に5回の放送を行っていた。IGY
が始まることになって,ウルシ通信網が整備,強化され,
10kWの送信機を購入し,8〜23MHzの間で8波,1日15
回の放送を行った。人員も4名が9名に増員され,24時
間4交代の勤務となった。観測計画はIGYからIGC,
IQSY等と表1のように進められてきた。この間アンテ
ナの真近かにも家がおし寄せてTV,ラジオヘの受信障
害を与えるとの苦情が多く出され,とうとう昭和40年に
千葉県の電電公社臼井送信所へ送信業務を依託すること
になった。これを機に放送は10,15MHz(5kW)で1日1回,
国分寺でキーイングを行うようになった。
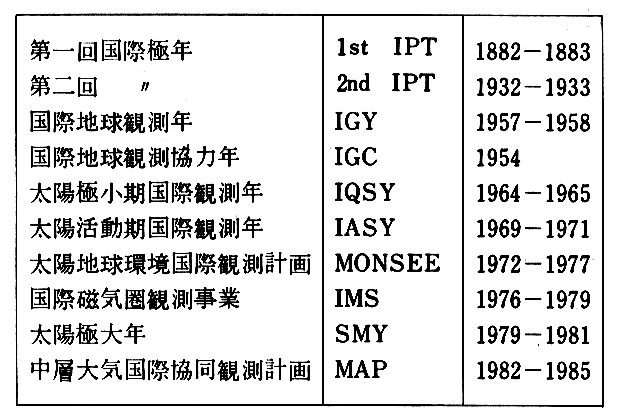
表1 国際協同観測計画の動き
(2)ウルシグラム放送の内容
(ア) 世界的地球物理警報(GEOALERT WWA)
WWA(世界中央(等報本部)は,太陽や地磁気の観測結
果に基づいて各RWC(地域本部)が決定したアドバイス
を基にして,世界的警報を決めてRWCに通知する。こ
れがGEOALERT WWAで,毎日の相対黒点数,地磁気,
太陽電波のトータルフラックス値,太陽黒点の位置や状態,
予報が含まれている。
(イ) 速報(PRESTO)
太陽フレヤー,太陽電波,地磁気等に異常現象が発生
したときに直ちに発出して異状現象のあった事を警告す
る。
(ウ) 日本の地域警報(GEOALERT TOKYO)
平磯支所超高層研究室は,毎日大陽や地磁気の状態,
ウルシグラムデータ等をもとにして,地域警報を決めW
WAにアドバイスを行う。日本の出す地域警報がWWA
で採用される率は他のRWCよりかなり高くこの5月で
は93.5%に達している。
(エ) ウルシグラム情報
ウルシグラムは観測項目名を表わす文字,日付,観測所
名やデータを5桁の数字で表わすなど,コード化されてい
る。このデータを解読するには右に示すコードブックが
必要である。
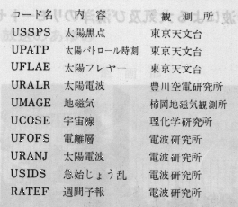
(3)人工衛星の打上げ情報
人工衛星情報の取りまとめ役として,NASAの中に衛
星中央警報本部(World Warning Agency for Satellite)
があり,人工衛星打上げ情報を始め多くの情報を集収し
ている。これらの情報はSPACEWARN NETWORKを
通じて交換されている。当西大平洋地域警報本部は衛星西
太平洋地域警報本部も兼ねているので,主に人工衛星打
上げ情報もウルシグラム放送に入れて放送している。
おわりに
太陽と地球は切っても切れない関係にあり,太陽の影
響を受けない日は一日たりともありません。それでいて
大陽の全てが分かっている訳ではなく,又太陽と地球の
環境を調査・研究することが通信や交通の安全確保に寄
与している。そこで国際協力として観測結果を迅速に交
換するウルシグラム放送やIUWDSの事業は太陽がある
限り続けられると云っても過言ではない。そのためには
ウルシグラム放送システムの改善,交換データの電算機
化等により更に確実で迅速なウルシグラム業務を遂行で
きるよう努力していきたい。
(第二課 通信係長 潰田 一輝)
音波による大気及び海洋のリモートセンシング国際シンポジウムに出席して
福 島 圓

会議場のカルガリ大学カルガリホール
標記シンポジウムが6月22日から25日までカナダのカ
ルガリ大学において開催された。
シンポジウムの目的は音波による大気及び海洋のリモ
ートセンシングにおける最近数年の成果について討論し
批判しようというものである。対象としては基礎的研究,
技術,装置のほかに環境問題への応用も含まれている。
4日間にわたるシンポジウムにおける各国からの発表を
セッションごとに表に示す。
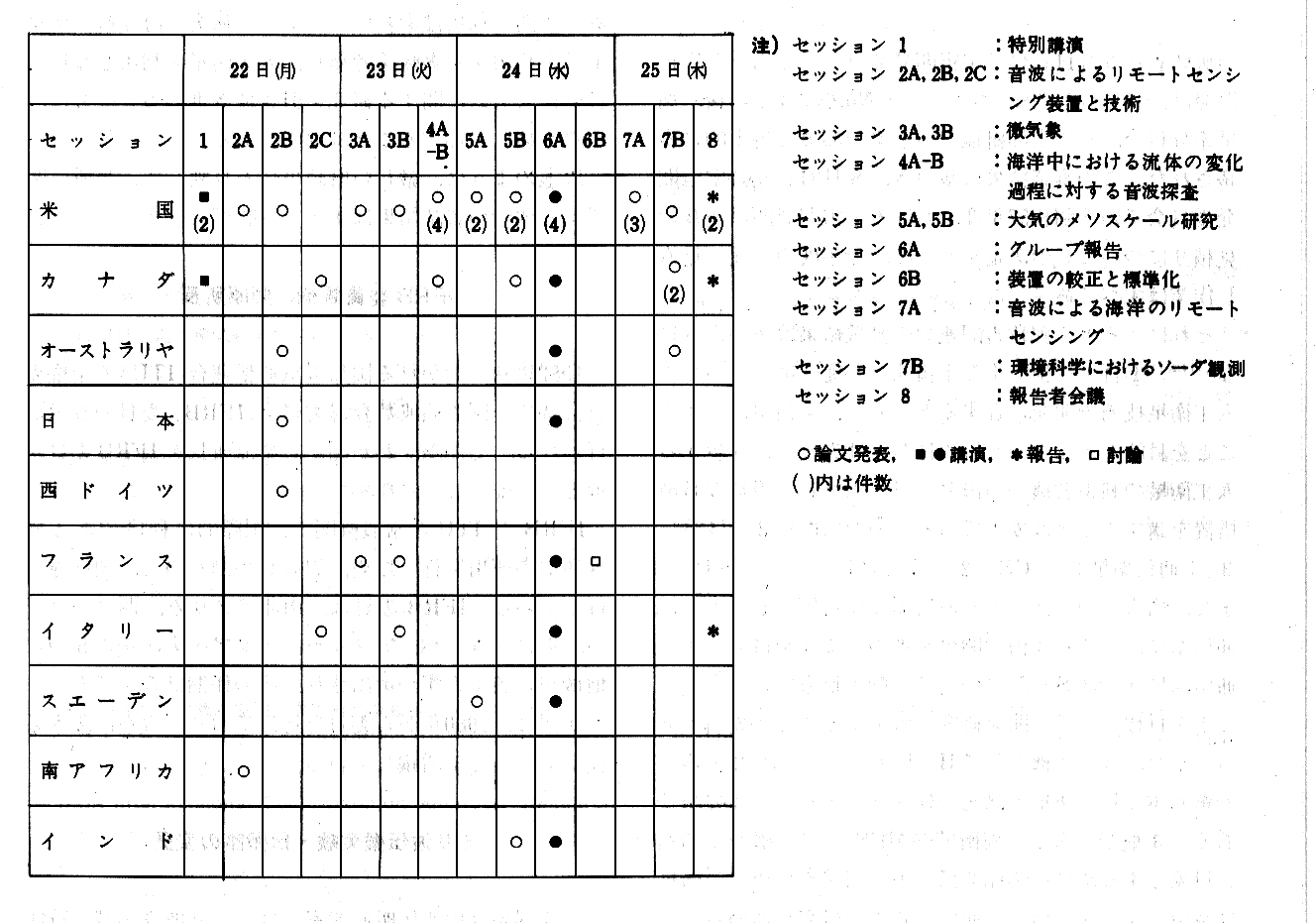
シンポジウム日程
開会日のセッション1では,カルガリ大学副学長Dr.
P.J.Kreugerの歓迎の辞で始まり,ついでNOAAのDr.
C.G.Littleからリモートセンシングの現状と重要性を
指摘した座長所感が述べられ,最後にNOAAを退職し
てコロラド大学で暫く教鞭をとることになったDr.E.H.
Brownから“大気音波探査と海中音波探査との類似性”
と題した興味深い特別講演があった。
続く各セッションでは,総合報告〈セッション(2A,
2B,2C),(3A,3B),(4A-B),(7B)〉,32の論文発
表,11の講演,4の報告と討論(司会フランス環境科学
研究センター(CRPE)のA.Well教授)が行われた。
シンポジウム参加者は10か国,約50名であったが,
アブストラクト集によるとソ連及びスイスから各1件の
申込みがされていた。全般的に米国の寄与が大きいこと
は従来と変わらないが,米国以外からの発表も増えてお
り隔世の感があった。
今回のシンポジウムで当所からは,“可搬型ラスレー
ダ”(セッション2B)と,“日本における大気音波探査の現
状”(セッション6A)の2件を発表した。“可搬型ラスレ
ーダ”では,当所の445MHzラスレーダ(本ニュースNo.
33,No.55参照)による高度数百mの気温高度分布測定
の実状,ラスレーダ測定に及ぼす風の影響,ラスレーダ
反射波のスポット状集束特性の報告に加えて,890.5MHz
上層風ラスレーダ(本ニュースNo.61参照)の予備的実験
結果(6×6台の受信機及び受信アンテナのネットワーク
を使用した反射電波強度集束像追跡方式による高度300m
位までの風向風速高度分布測定結果)を報告した。ブラウ
ン管上に数秒で伸びてゆく温度曲線の実時間表示データ
などを,映写時間5分の16ミリ映画にして説明を行った。
従来ラスレーダ測定で生ずるばらつきが何によるもの
かはっきりしていなかった。今回,風の影響による音波波
面の水平移動を映画にしてばらつきの要因を説明したと
ころ,大方の共鳴を得たようだった。この日の夕刻のパ
ーティで,筆者の発表が今日のハイライトだったと言っ
てくれた人もいた。
“日本における大気音波探査の現状”については,電
波研はじめ国内各研究機関でのここ数年間の進展をまと
めて発表した。内容は当所のラスレーダ開発,逆転層に
よるUHF TV電波117㎞通路における電界上昇等公害
資源研における音波レーダ利用による大気境界層研究,
電力中研におけるドプラ音波レーダの長期性能評価試験,
気象研におけるドプラ音波レーダ開発計画,京大防災研
における簡易型ラスレーダ開発実験などの現状報告の他,
当所で開発した音波レーダ性能較正法の説明を行った。
このセッション6Aでは溝演者が増えたため,予定さ
れた講演時間を半分に減らされてしまった。大体の要旨
は述べたつもりであるが,時間が足りなくなり,どこま
で理解されたか心残りである。しかし,セッション6B
(装置の較正と標準化)で司会者から発言を求められたの
で追加説明をした。なお,音波レーダ較正法については,
われわれの提案した標準反射体(コーナーレフ)利用によ
る方法より,気温変動直接測定との比較に大方の興味と
関心が集中していたようである。
最後に二三の印象を述べる。先ず,大気汚染への応用
を扱ったセッション7Bにおいて,ペンシルベニヤ大学
のD.W.Thomson教授はその総合報告の中で,音波レー
ダの効果的利用を妨げているものとして,使用者側の立
場での大気汚染対策計画が欠如していることを挙げてい
た。このほか,ユーザから見たドプラ音波レーダに関す
るものがいくつか発表されていた。新しい装置や方式の
開発に当っては常にユーザを意識して推進することが重
要であろう。
また,1973年の国際シンポジウム(オクラホマ大学での
大気音波探査研究集会)に出席した時と比べて,今回は対
等な研究者もしくはライバルとして見られているように
感じた。これも,この分野の研究で彼等と肩を並べられる
ようになったためだろうかと思う。いろいろの意味で楽
しかった今回のシンポジウムに出席する機会を与えてい
ただき感謝の気持で一ぱいである。
(第二特別研究室長)
短 信
電波音波による対流圏の探査実験
第二特別研究室では,上層風ラスレーダ(本ニュース
No.61)の性能評価を目的に標題の実験を8月5日から21
日までの期間,福島県長沼東小学校校庭において実施し
た。
主な実験目的は,アレー状に配列された6×6台の受
信機によって反射電波集束像を追跡することにより,高
度500〜600mまでの風向風速及び気温の高度分布を測定
し,測風気球観測及び低層ラジオゾンデ観測との比較デ
ータを取得することである。
実験開始に先立って,装置の主発振器の故障というト
ラブルもあったが,予期以上のデータを収録することが
でき,取得データの整理結果に期待が寄せられている。
宇宙開発計画見直し要望の審議結果
郵政省が6月11日付で宇宙開発委員会に提出した宇宙
開発計画の見直し要望(本ニュースNo.64)はその後,衛
星系分科会,その上部組織である第一部会で集中的に審
議された。この審議結果に基づき,8月31日臨時宇宙開
発委員会での「昭和57年度における宇宙開発関係経費の
見積りについて」の決定をもって,今年度の一連の見直
し作業はすべて終了した。
それによると,郵政省関連分の審議結果は次のように
なった。①自主技術による宇宙開発の促進策について:
人工衛星技術の開発に資するとともに,実利用に供する
ことを目的とする人工衛星の打ち上げ失敗により生ずる
人工衛星の利用者機関の損害に対し国として適切な救済
措置を講ずることは妥当である。②通信衛星3号(CS-
3):通信衛星2号(CS-2)による通信サービスを継続し,
また,増大かつ多様化する通信需要に対処するとともに,
通信衛星に関する技術の開発を進めることを目的とする
通信衛星3号(CS-3)について,静止軌道に打ち上げる
ことを目標として,開発研究に着手することは妥当であ
る。また,打上げ機としてH-Iロケットを使用するこ
とを基本として衛星の諸元の検討を進めることは妥当で
ある。③航空・海上技術衛星(AMES):航空機及び船舶
を対象とする衛星移動体通信枝術の開発のために,衛星
塔載用ミッション機器,通信方式等の研究を進めること
は、妥当である。④実験用静止通信衛星Ⅱ型(ECS-Ⅱ):
将来の増大する通信需要に対処するため,ミリ波帯中継
器,準ミリ波帯高性能中継器等の衛星搭載用通信系機器
及び新しい衛星通信方式の研究を引き続き進めることは
妥当である。⑤新しい周波数帯を利用した衛星放送に関
する研究:22GHz帯等の周波数帯を利用した新しい衛星
放送技術を確立するため,地域別衛星放送システム,新
しい衛星放送方式等の研究を行うことは妥当である。⑥
通信技術衛星(ACTS-G):将来における大規模かつ多
様な宇宙通信の技術基盤を確立することを目的として,
衛星搭載可能なマルチビームアンテナの研究を引き続き
進めることは妥当である。⑦衛星搭載用電磁環境観測ミ
ッション機器の研究:宇宙電磁環境じょう乱警報を行う
ため必要な衛星搭載用電磁環境観測ミッション機器の研
究を行うことは妥当である。⑧衛星搭載用能動型電波リ
モートセンサーの研究:衛星搭載用雨域散乱計等の能動
型電波リモートセンサーの研究を進めることは妥当であ
る。⑨衛星利用捜索救難システムの研究:海洋観測衛星
1号を利用する実験を考慮し,人工衛星を利用した捜索
救難システムに関する研究を引き続き進めるとともに,
国際実験に参加することは妥当である。
以上のように,厳しい財政事情を反映して, 当所に関
係する要望の審議結果はすべて“研究”レベルとなった。
IFRB委員候補に栗原所長
1982年秋に開かれる国際電気通信連合(ITU)の全権委
輿会議で,国際周波数登録委員会(IFRB)委員の改選が
行われる。その際,わが国から栗原所長をIFRB委員候
補として推すことになった。
IFRBはITUの常設機関で、国際的に秩序のある無
線通信の連用を行うため,周波数の割り当て,調停等を
行っている。IFRB委員は,南北アメリカ,西ヨーロッ
パ,東ヨーロッパ,アフリカ,アジア・大洋州の5つの
地域から各1人ずつ選出され, その任期は6年である。
わが国は,1960年から委員を送っており,現在は藤木栄
氏が委員として活躍している。
ミリ波伝搬実験・伝搬路の変更
電波部超高周波伝搬研究室では,ミリ波降雨減衰特性
の解明を目的として,昭和54年度より伝搬実験を実施し
ている(本ニュースNo.36)。当初,日立中研−電波研の
間(約1.3km)で4波を用いて実験を開始し,昭和55年度
末からはさらに,別の2波の伝搬実験システムを既設伝
搬路に沿った国分寺電報電話局一当所の間(約760m)で運
用しデータ収集を行ってきた。今回後者のシステムを,
既設伝搬路とはほぼ直交した東京経済大学−当所(約810
m)の伝搬路で実験することとなり,去る7月末に移設作
業を完了,実験を再開した。この移設の結果,6波の減
衰データを同時に比較するという利点は失われるものの,
このうちの2波(34.5GHz,50.4GHz)が同一の大気の窓
に属しその降雨減衰特性は同質なので,この2波を介し
て,統計的に2つの伝搬路のデータを有効に利用できる。
また,降雨減衰の伝搬方向による角度特性を得ることも
期待される。