

大瀬 正美
はじめに
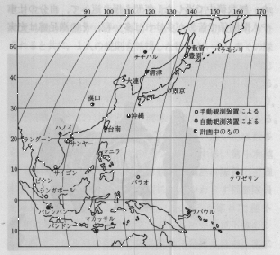
図 戦前、戦中の日本の電離層観測所分布図
昭和19年には,電波物理研究所職員の中で現役入隊す
る青年が14名いた。その中で私は一番早く9月に入隊し
た。幸い内地の教育隊に残ったので終戦後,昭和20年10
月に復員して復職した。その頃の電波物理研究所は上野
毛の多摩美術学校内にあったが,戦災でほとんど焼失し
ていた。昭和20年12月,陸軍行政本部,第5陸軍技術研
究所が移管されて, 手動型電離層観測機と共に第9棟
(現在南極事務室のある建物)に移転してきた。昭和21年
1月,当時電離層課長であった青野さんから「お前はラ
バウルに行く予定になっていたから, 日本の最南端であ
る九州鹿児島観測所の創設に行くように」と言われた。
昭和21年3月,現地調査に行き各地を調査した結果,指
宿海軍航空隊山川送信所跡(現在の山川電波観測所の場
所)に決定したわけである。一旦帰京して手動型電離層
観測機の部品を集めて組み立てを行った。(当時新発田,
深浦等各地方観測所開設のため機器の調整をしたのも第
9棟であった)。そして7月山川に出発した。 最初の建
設期は昼間は生活面の水道工事その他建物補修等の重労
働が続き,夜になって観測機器の調整をはじめる毎日で
あった。昭和28年1月国分寺へ転勤になり, しばらくは
電離層課電波伝搬係に席を置いていた。昭和30年,日本
の南極観測参加が決定した頃,再び青野さんから「お前
は南方を希望していたが, もっと南の南極に行く気はな
いか」と言われて早速希望したことが,以後26年間南極
観測に関係するようになった始まりである。そして1/4
世紀を経た現在も南極事務室は第9棟にあり,遂に近代
建築の建物に席を置くことがなかった。
南極観測と共に歩む
第1次南極観測隊が出発した昭和31年頃は,日本もよ
うやく高度経済成長時代が始まった時期で,戦後の時代
はまだ抜けきっていなかった。
第1次観測船宗谷による広範囲な電離層移動観測は,
全く経験がなく,色々な準備のため8月頃から11月8日
の出港まで,ほとんど浅野ドックの宗谷に泊り込んで電
離層観測機の調整を行った。本番の船上観測は南極へ行
くというのに,連日印度洋の暑さと船の動揺の連続であ
ったが,若さで乗り切ることができた。氷海での苦闘も
12時間交替の物資輸送作業もすべて順調に進み昭和基地
が建設された。11名の越冬隊を残せたことは幸運の一言
につきよう。この第1次の成功があったればこそ,今日
ある南極観測の基礎が確立されだともいえよう。昭和37
年から40年まで3年9か月の間,宗谷の老朽化に伴い南
極観測は一時中断のやむなきにいたったが,第7次から
「ふじ」の就航により,南極観測は年毎に堅実な発展を遂
げることができた。
私が南極へ最後(現役としてはおそらく最後になると
思う)に向ったのは,第19次隊の昭和52年11年であった。
この間に氷海及び昭和基地で迎えた正月は通算11回を数
え,電波研究所在職中の大半を南極観測と共に歩んでき
たことになる。入所当時南方を希望したことに始まり最
後まで南とは縁が切れなかった。戦後の混乱期であった
昭和20年代には山川観測所,30年代に昭和基地の建設と
2か所の観測所を建設する機会に恵まれたことは,私の
人生においてよりよい経験を得ることができた。今振り
返ってみると,厳しい昭和基地の建設作業より,昭和21
年当時の物資が欠乏していた頃の山川観測所建設の方が
はるかに大変であった。しかし山川で経験したアンテナ
建設及び諸作業がその後の昭和基地建設に大きく役立っ
たことは事実である。初期の越冬生活は現在のように完
備した居住棟はなく,観測室の一隅にベニヤ板の簡易べ
ットを作り生活したものである。夜は燃料節約で暖房機
を停止するため朝方の室温は常に零下になっていた。し
かし馴れてくると,15分毎の電離層定時観測の雑音が子
守唄のように聞こえ,モニターともなりよく眠れたも
のである。私は越冬生活においても遂に現在の完備した
居住棟には, これまた一度も居住することがなかった。
越冬の場合は衣食住が確保されており,何ら生活面での
苦労はなかったが,物資輸送の少ない宗谷時代は越冬中缶
ビールの配給はミッドウインター(南極の冬至)に1本
のみで,第5次の一番機が運んでくれたビールの味は今
でも忘れられない。
現在は物資も豊富になり生活面での不自由はなくなっ
てきたが形を変えた共通点はある。一方,地方観測所
に単身赴任する場合,生活を家族と2分される経済面で
の負担,その他もろもろの問題があろう。この点南極で
の越冬生活は衣食住が保障され,かつ経済的にも家族に
負担がかからないこと,1年すれば確実に帰国できるこ
と等を考えると,私でなくとも南極越冬を希望するよう
になろう。今や日常生活における危険度は国内において
も交通事故その他を思えば,昭和基地の方がむしろ安全
度は高いとさえ言える。家族との連絡も現在は衛星通信
による電話連絡及びハムを利用し,もはや地球の果とい
うイメージは薄らいできた。1か月の電報字数が300字
と制限された頃から思えば,雲泥の差である。ただ留守
家族の方はやはり未知の世界ということもあり,また子
供の教育等である程度不安感は残るようであるが,留守
をあずかる当所の南極担当者が常に銃後の守りを固める
ことにより隊員も安心し,また留守家族にもある程度は
納得してもらえるものと思われる。

第一次南極観測隊員(左から大瀬,岡本,会田)
南極での人間関係ともろもろの思い出
閉鎖された社会での越冬生活も終りに近ずき,一番機
が基地に到着した日,故郷の香りや家族からの手紙等と
1年ぶりに再会できる喜びは言葉で表しようもなく, ま
た,無我夢中で過した1年間を振り返って,自分の仕事
や人間関係で苦労が多ければ多い程, その満足感は充実
したものとなろう。また自分が歩んだ人生の一こまとし
て,その越冬経験は以後自分の行動に対して自信を持た
せる力になってくるものである。
隊員はそれぞれの観測や仕事を行う上では,各部門の
利益代表であるが,自分だけの殻に閉じこもることなく,
閉鎖社会の人間関係では,全員作業でも,苦しい観測の
手伝いでも自分からその苦労を買って出る位の積極性が
なければうまくゆかない。他部門の仕事を極力理解する
よう努力して,協力をしないかぎり, おのずから自分
の仕事にもはね返ってくることを知っておかなければな
らない。
越冬観測を終り,帰路の船上で「越冬1年を振り返っ
て」の反省会なるものを行うと,若い隊員の中からかな
らず「観測や仕事もさることながら,人間関係について
非常によい勉強となり,今後の人生経験に大変役立つこ
とを多く学ぶことができた」という発言が出る。越冬を
通じての団体生活は,ぶっつけ本番であり, 1年間の長
丁場でもあるため, ごまかしやめっきはきかない。このよ
うな体を張った実戦はおそらく国内では経験することは
できないだろう。越冬生活を経験した人達にのみ通用す
る醍醐味でもある。
南極での生活は常に厳しい自然との闘いでもある。基
地の建物に居るかぎりは日本の生活とあまり変らないが,
一旦基地から旅行に出ると越冬開始から25年を経過し,
装備の充実した現在でも厳しさはアムンゼン,スコット
の時代と同じである。まかり間違えば生命にかかわるこ
ともあり得る。したがって各隊次により昭和基地内規が
定められている。ブリザード(強烈な吹雪)を経験する
ことにより,これだけ科学の進歩した時代でも,大自然
に立ち向う人間がいかに無力であるかを痛切に感じさせ
られると共に,1人の規則を無視した行動がいかに多くの隊
員に迷惑をかける結果となるかを知り,団体生活を通じ
て常に各自責任ある行動がとれるように訓練されてくる。
とかく南極とは何が起こるかわからないのがところであり,
また何事も未知の世界として興味を引くところでもある。
私の越冬生活の中で忘れることのできない想い出は数多
くあるが,紙面の都合で次の三つを紹介する。第4次越
冬(昭和35年)時に同じ超高層観測の福島紳隊員の遭難
事故があった。当時懸命な捜索にもかかわらず福島隊員
を発見することはできなかった。ところが第8次越冬
(昭和42年)終了時,第9次隊により基地から風下側4.2
㎞の西オングル島の西端で福島隊員は発見された。実に
7年4か月ぶりの対面であった。この夏は基地周辺の雪
どけが早く,海氷から第2次に残置したカラフト犬の遺
体が発見され,隊員の中にも何かしら福島隊員が発見さ
れるのではないだろうか,というような予感が強かった。
奇しくもこの時は4次に福島隊員と一諸に起居を共にし
た隊員14名のうち7名が基地に滞在していた。何か宿命
的なものを感ぜずにはいられない。
次に第8次越冬(昭和42年)時,真冬の8月に隣りの
マラジョージナヤ(ソ連基地)を訪問した。1週間滞在
しての帰路,新南岩(昭和基地から約240㎞)の調査に立
寄り,終了後帰路の海氷クラック(氷の割目)を渡る時,
雪上車が落ちた。水没するまでの時間は1分位であった
だろうか,食糧を搭載していたソリを切りはなすのが精
一杯であった。運悪くこの雪上車には電界強度測定を行
うため,連絡用通信機2台を積んでいた。水没する間際,
雪上車のスイッチが海水で短絡してライトが点燈し, ク
ラクションを鳴らしながら,ホイップアンテナが折れ曲
り姿を消して行く光景は今でも忘れることはできない。
次に第12次越冬(昭和46年)時,冬期ロケット実験の
最中に,組立調整室の床下に設置していたロケット搭載
機器保温用暖房機の調子が悪く隊員が調整を行った。夕
食前に終了してシートをかぶせて隊員は食堂棟に帰って
きた。食後ロケット隊員がレーダテレメータ室に行った
時,組立調整室床下から煙の出ているのを発見して急報
した。全員消火器を持って急行したが,その時はほとん
ど鎮火していた。室内は煙に包まれていたが,幸い低温
のため大事には至らなかった。組立調整室にはS-210
型ロケット2基がセットされていた。今考えても冷汗も
のであった。
むすび
人間は若い頃に色々な経験をしておけば,自分自身が
年を取ってからの人生が豊かになるということを現在私
は痛感しているところである。10年経てば10才年を取る
ことは避けて通ることのできない宿命である。今でも南
極の大自然に接し,広く見聞してきた自分の人生に対し
て後悔はしていない。ただし,何事を行うにも自分自身
の健康管理には充分注意して,何時いかなる時でも自信
をもって物事を実行できる心がまえが常に必要であろう。
最後に次期世代の人達に大いなる期待をよせるものであ
る。
(電波部 主任研究官)
調 査 部
はじめに
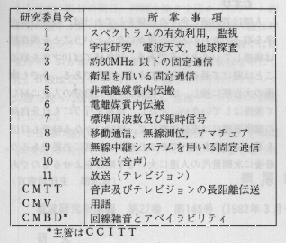
表 CCIRの研究委員会及びCCIRとCCITT
との合同研究委員会
CCIRにおける研究活動
CCIRの最近の活動の中から,若干取り上げて見たい。
① ミリ波及び可視・赤外
これは前記のCCIRの所掌及び「電波」の定義とも
関連があり,CCIRでは日本の努力の結果,1975年回
章により研究問題Q. 53/1 (40GHz以上,特に電波の
最高周波数領域,及び赤外・可視領域のスペクトラムの
電磁波による通信システム)が設定された。そして現在
これに応えた報告Rep. 664(40-3000GHzの周波数帯利
用のレビュー),Rep. 885(可視及び赤外の減衰),Rep.
681(赤外及び可視光による宇宙研究)がCCIRテキス
トに載っている。このほか,1982年の第15回総会の結果,
耕しいQ. 25/2(赤外及び可視光を利用する宇宙通信シ
ステム)が設けられた。
当所においても,40GHz以上の周波数資源, レーザに
よる衛星姿勢の高精度決定方式, レーザによるリモート
センシング等について研究開発が行われており, その成
果をCCIRへ寄与している。
②静止衛星軌道(GSO)
CCIRその他の各種国際機関でGSO有効利用の検
討がなされている。問題は,GSO及びそこで使用され
る電波が有限な天然資源であることである。12GHz帯の
放送衛星については,1977年の世界無線通信主管庁会議
(WARC-BS)において第一地域(ヨーロッパ,アフ
リカ)及び第三地域(アジア,豪州)の国々に対し,軌
道位置と周波数が割り当てられた。例えば, 日本は軌道
位置110度に8波を割り当てられた。
CCIRでは,主として中間作業班IWP4/1が1968
年の設立以来,GSOの有効利用について研究を行って
きた。そして,WARC-79では, GSOのプラン化に
関する世界無線通信主管庁会議(WARC-ORB)の
開催が決議され(1985年及び1988年に開催予定),これ
に先行するCCIRの準備会議(CPM-ORB)が来
年7月に開かれる予定になっている。昨年のCCIR第
15回総会では,SG4その他のSGの研究成果をまとめ
た文書Doc. PLEN/10(WARC-84のための暫定報告
書)が採択された。
GSOの有効利用については,昨年のITU全権委員
会議でも論議された結果,条約第33条(無線周波数スペ
クトル及び対地静止衛星軌道の合理的使用)の中に「発
展途上国の特別な要求及び特定の国の特殊な地理的事情
を考慮しつつ」という字句が追加された。
GSO及び周波数のプランニングの方法には,おおざっ
ぱに言って,固定的プラン(いわゆるアプリオリプラン)
と多国間調整による方法とがある。前者の例が,前記の
12GHz帯放送衛星のプランであり, これは主として発展
途上国の主張に沿ったものである。GSOの有効利用の
ためには,多国間調整による方法がよいと言われており,
来年のCPM-ORBでの論議の行くえが注目される。
③ FGMDSS
「将来の全世界的な海上における遭難安全制度(FGM
DSS)」は,本年3月に開かれた移動業務に関する世界
無線通信主管庁会議(WARC-Mobile)の主な議題の
一つであった。国際海事機関(IMO)は,FGMDS
Sの1990年導入を目途として検討を進めている。
CCIRにおけるFGMDSSの研究が本格化したの
は,1980年のSG8中間会議からで, 政府間海事機関
(IMCO,1982年5月からIMOと改称)の要請による
ところが大きい。移動業務に関するWARCは,1987年
にも予定されており, CCIRにおけるFGMDSSの
研究は今後も続けられる。
④ データ中継衛星
NASAは本年4月スペースシャトル第6回飛行(チ
ャレンジャー号)において,データ中継衛星(TDRS)
を打上げたが,上段ロケットの不調により,静止化が難
行している。TDRSの計画は,1970年頃スタートし,
打上げスケジュールはこれまでたびたび延期され,やっ
と実現の運びとなったわけである。
CCIRでは,1970年にSG2にQ. 11/2(宇宙局に
よる地球局と宇宙機との間の無線回線)が設定され,ほ
とんど米国からの寄与文書によりTDRSに関するテキ
ストが作成されてきた。TDRS自体は静止衛星で,こ
れとLANDSAT-4のような周回衛星との間に衛星
間回線(ISL)が作られる。TDRSシステム展開後
は,従来のNASAの人工衛星追跡網(STDN)は,
その局数削減などによる合理化・効率化が進む。米国は
TDRSシステムに続く将来の追跡・データ取得システ
ム(TDAS)について,1981年のSG2最終会議で既
に報告している。
一方SG4では,静止衛星間のISLに関ずる研究が
進められており,その成果はRep. 451-3(固定衛星業務
の衛星間回線)としてまとめられている。
おわりに
昨年のCCIR総会,ITU全権委員会議等の最近の
動向の中から若干取り上げた。その際,「電波時報」その
他の文献を参考にさせていただいたことをお断りすると
ともに感謝いたします。
(衛星計測部長 中橋信弘)
上瀧 實
はじめに
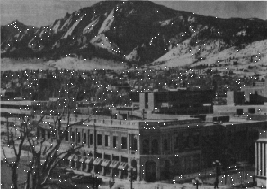
ボルダーの冬景色
生活雑感
Boulderは人口約8万人の研究学園都市でコロラドの
州都デンバアから北西へ車で40分程のところにある。東
からなだらかな起伏で続く大草原が西に立ちはだかるロ
ッキー山脈と突き当った所にある海抜1600mの高原都市
である。
市の発祥は他の西部の町と同様,19世紀後半(1858年
10月17日)ゴールドラッシュ時に現在の市の西端の
Boulder Canyon に15人の山師がテントを張った事に始ま
る。その後,市は東からの農産物と西からの鉱物の中継
点として発達していった。現在は多くの研究所, コロラ
ド大学などがある研究学園都市となっている。
気候は気温の変動が激しく乾燥した内陸型で,東京か
ら行った筆者は,当初喉が乾いたり,唇が荒れたりし,毎
日大量に飲んだ果物ジュースの美味しさが印象的であっ
た。冬の雪も二,三日のうちにそのまま昇華してしまい,
雪の下からは乾いた土が出てくる始末であった。したが
って,夏の芝生の水まきは欠かせぬ仕事で,公園や各家の
庭には散水器が置かれ,青空に吹上がる水の輝きはBoulder
の夏の風物である。
日本のように草木を通して,はっきりと四季の移ろい
を感じることはできぬが,二月の聖バレンタイン,四月
のイースタ祭にはじまり,十月のハロウイン,十二月の
クリスマスにいたるまで一年間の折々にある記念日には
各家庭で思い思いの趣向を凝らした催しやパーティを行
い,年月の節目を感じ忘れ得ぬ想い出が作られていくよう
だ。こうした記念日には,筆者も同僚の家庭に呼ばれた
り,また我が家に来ていただいたりして楽しい日々を過す
ことができた。クリスマスの豪華な料理,夏の夜に満天
の星を仰ぎながらの屋外パーティなど忘れることはでき
ない。
慌しい日本へ戻った現在,Boulderでの一年間の生
活は長い夢を見ていたかのようである。
おわりに
僅か一年間の米国の生活であったが,一日一日が新鮮
で印象深い毎日であった。知り得た米国人が皆, 自由で
のびやかな暖かい人々であった。近年米国経済の不況が
伝えられているが,果しなく広大な砂漠をリボンの様に
貫ぬき通るハイウェイは現代の万里の長城に匹敵するほ
ど迫力があり,米国の底力を暗示しているようであった。
最後に当たり, この様な機会を与えて下さった科学技
術庁,郵政省及び当所の関係各位に深く感謝いたします。
(企画部 第1課 主任研究官)
衛星計測部第一衛星計測研究室
当研究室の歴史は比較的新しく,昭和54年7月14日に 衛星計測部に属する二つの研究室の一つとして活動を開 始した。所掌では「衛星による対流圏以下の領域につい ての計測に関する研究を行うこと」と規程されているが, 具体的には大気,地表,海面等の自然環境を電波を使っ て測定する電波リモートセンシングの研究を行うのが 当研究室に課せられた使命である。研究室としての歴 史は浅いが,中味の研究はより早い時期から行われて いる。黎明はCS,BS計画が軌道に乗り始めた49年 頃で,電波によるリモートセンシングの研究を行うべき ことがプロジェクト報告書の中で要望されている。50, 51年になると衛星のミッション機器の一つとしてマイク ロ波放射計を取り上げ,電波によるリモートセンシング の可能性及び装置の設計検討が進められた。しかし,当 部発足に最も大きな要因の一つとなったのは,53年に航 空機搭載マイクロ波雨域散乱計/放射計の開発が世界に 先がけて開始されたことであろう。以後の研究は同装置 による実験研究が中心となり進められている。(高杉 敏男)
企 画 部
58年度新規採用職員の研究所に於ける職場訓練が4月 から5月にかけて行われた。初・中級採用者7名,上級 採用者9名(研究所4名,監理局5名)であった。ほと んどの者が濃紺色のスーツに身を包み,頭髪もスッキリ と爽やかで,挨拶もはっきりと,正にピカピカの一年生 であった。食堂に居るときなどは一際目立っていたが, 電波研究所勤務者に限って言えば研究所独特のスタイル に染むのにはそう長くかからないだろう。そして, その スーツは年に数回お勤めを果たすのみとなり,体型が変 らなければ10年以上使えることは我々の経験から言える だろう。(第一課)