 |
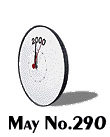 |
 |
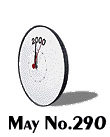 |
 |
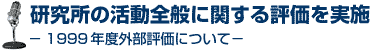 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平 和昌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信総合研究所では、研究所の活動全般に関して外部有識者により評価を受ける、いわゆる「外部評価」を昨年度に実施しました。江崎玲於奈博士(ノーベル物理学賞受賞者、前茨城県科学技術振興財団理事長、現芝浦工業大学学長)を委員長とする総勢70名の委員(国外委員15名を含む)により外部評価委員会が構成され、研究所の現在の研究活動や運営の状況、研究所が描く将来計画について、書面による評価や委員会会合における長時間に亘る議論をお願いしました。当研究所の外部評価は、1996年に初めて実施したのに続き2回目の実施です。
「国の研究開発全般に共通する評価の実施の在り方についての大綱的指針」が1997年の内閣総理大臣決定として示され、国立試験研究機関である当所は、この指針に基づいて評価を実施することとなりました。この指針には評価時期についての指標が記述されており、3年を目安として定期的に評価することとなっています。前回の外部評価から3年を経過した昨年度、当所としては2回目の総合的な外部評価を実施することを決定しました。 今回の外部評価を実施するにあたっては、特に以下の2つのポイントに重点が置かれました。 (1) 上述の大綱的指針においては、「重点的資金による研究開発課題」の評価の実施が明確化されています。そこで、当所において実施されているすべての重点的資金による研究課題に対して、その課題実施の意義を明確にするために、課題別に評価を実施しました。 (2) 2001年に実施される政府機関の行政改革に伴い、当所は「独立行政法人」に移行することが決定されています。そこで、独立行政法人化後に当所が推進すべき研究開発及びその実施体制に関する将来計画案について、評価委員会においてご議論をお願いしました。 2. 外部評価委員会の構成と審議した事項 外部評価委員会は、評価する事項に応じて2種類の委員会構成がとられました。それぞれの委員会の評価事項は以下のとおりです。 ①機関評価委員会:当所の現在の運営状況と活動の全般に関する評価、将来の運営・活動方針に関する評価を行いました。機関評価委員については、5ページに示します。 ②研究評価委員会:当所で研究開発を実施している研究分野を以下のように大きく4つに分類し、各分野ごとに重点的資金による研究課題の計画・体制・成果等に関する評価を実施しました。なお、必要に応じて分野内に分科会を設けて評価の効率化を図りました。各分野の研究評価委員については、5ページに示します。 分野1:次世代情報通信基盤技術 分野2:次世代無線通信システム技術 分野3:電磁波計測技術及び環境情報の高度利用技術 分野4:情報通信基礎・基盤研究
(1)審査について 評価の実施に際しては、機関評価委員会及び研究評価委員会ともに、(a)評価用資料に基づいた書面審査、(b)評価委員会会合時における討論による審査の2種類の審査を行いました。なお、スケジュール等の都合上、書面審査のみをお願いした委員もおられます。 (2)評価委員会会合のスケジュール 図1に、外部評価委員会全体の活動スケジュール(評価実施の流れ)を示します。機関評価委員会および研究評価委員会それぞれの評価の流れは、以下のとおりです。なお、今年3月28日には、外部評価委員会による評価結果について江崎委員長が報道発表を行いました。 ①機関評価委員会 機関評価委員会の会合は、昨年12月16日及び17日に当所の本所(東京都小金井市)において開催しました(写真1~3)。16日は、当所の運営および活動について現状報告を行い、運営における諸問題に関して討論をお願いしました。また、研究評価委員会による評価結果・講評について各研究分野の評価委員長よりご報告いただき、これらに関する質疑応答及び議論をお願いしました。さらに、研究施設のご視察も行いました。 17日には、独立行政法人化を2001年4月に控えた当所の将来計画案について当所幹部が提案し、将来の展望に関する当所の方針について討議をお願いしました。また、9名の若手研究職員との自由討論を開催し、各自の研究の状況や職場への希望などを述べ、質疑応答を行いました。午後に入り、評価委員のみでご討論をされた後、所長をはじめとする当所の全部長が出席の中、江崎委員長からこの外部評価全体にわたる総括講評をいただきました(写真4参照)。 ②研究評価委員会 研究評価委員会の会合は、昨年4月から11月にかけて、先に述べた研究分野またはその分科会ごとに開催しました。分野4の一部の分科会会合は当所の関西支所(兵庫県神戸市)において、他のすべての会合は当所の本所においてそれぞれ開催されました。分野によっては、会合の中で研究施設のご視察もあわせて実施しました。
機関評価では、当所の現在の運営状況と活動の全般に関する評価、将来の運営・活動計画に対するご議論をお願いしましたが、その評価結果から、現在の運営・活動全般に関して主に評価された点と助言、将来計画案に対する助言を以下にまとめました。 (1)現在の運営・活動全般に関して主に評価された点 (a)社会への貢献について 研究所の成果は、我が国や世界に対して誇りのもてる貢献をしている。 (b)開かれた研究所運営について 優れた研究成果をインターネット上で閲覧できることや、研究所で活動している研究員の3分の1近くを外部の機関から招集できていることなど、開かれた研究所運営を常に考えている。 (c)人材の確保について 学位取得者を多く採用しており、優秀な人材確保をしている。また、非常勤職員制度の導入を実現し、外部からの人材確保に努めている。 (d)研究者の意欲増進について 「表彰制度」、「奨励研究制度」、「特別昇給制度」、「特許の研究者持分認可制度」等、多くの施策が打ち出されている。 (e)評価について 早くから外部評価を積極的に取り入れている。特に、外国人の評価者をメンバーに含めることにより、外部評価を充実させている。また、前回の外部評価結果に対して誠実な対応と改善努力をしている。 (2)現在の運営・活動全般に関する主な助言 (a)研究テーマについて 研究職員の定員数を極端に増やすことは不可能であるため、実施する研究テーマを厳選しなければならない。 (b)研究予算について 研究テーマに対する外部評価結果及び部内の評価結果に基づき、各研究テーマに配分する研究予算額を決定するプロセスが導入できるようになると、予算に関してより効率的な運用ができる可能性がある。 (c)組織について 組織を構築する際、「予算や研究テーマが変わることに応じて組織も変える」という勇気ある姿勢をとることが重要である。 (d)研究支援について 研究支援者の不足を解決する手段として、研究開発よりも研究支援部門に適性を有する職員を研究支援者に充てることも一つの方策である。 (e)研究交流について 今後は特に欧米との共同研究の推進を図るべきである。 (f)学術的貢献及び社会的貢献について 国際標準化に対する貢献や、社会で広範に活用されるソフトウエア開発等の業績も、学術的貢献度の指標として評価されなければならない。また、今後は社会との絆をより一層強化し、特に次世代を担う子供たちへの啓発や教育活動へ積極的に参画していくことを期待する。 (3)将来計画に対する助言 (a)独立行政法人化について 独立行政法人化によって無駄なものは除かれていくという効果は期待できるが、効率化の追及にとらわれすぎてしまうことが懸念される。従来から育ててきた研究所の良さを継続して活かし、国民の利益へ貢献してもらいたい。 (b)組織について 独立行政法人化によりできあがった組織を固定的なものとして考えず、国民からの要請や周囲の状況変化に応じてフレキシブルに対応していくことを考えていくべきである。 (c)運営の資金について 先端的な技術開発に関しては、産業界との協調関係を深めながら実施する必要がある。そのためにはマルチファンディングの運用方法を検討し、構築することが必要であると考えられる。 5. 外部評価を終えて
(企画部企画課) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999年度外部評価委員会の委員 外部評価委員会の評価委員は、国外委員15名を含む総勢70名の以下の委員で構成されました(敬称略。ご所属および役職は1999年3月現在)。 1.機関評価委員会
2.研究評価委員会 分野1:「次世代情報通信基盤技術」
分野2:「次世代無線通信システム技術」
分野3:「電磁波計測及び環境情報の高度利用技術」
分野4:「情報通信基礎・基盤研究」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||