 |
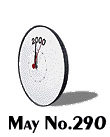 |
 |
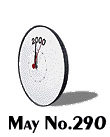 |
 |
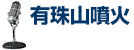 |
|||||||||||
| 梅原 俊彦 |
||||||||||||
|
3月31日13時10分、北海道洞爺湖温泉南側の有珠山(732m)が噴火しました。(写真参照)噴煙は上空約2,700メートルまで上昇、風下には大小の火山れきを含む火山灰が大量に降り積もりました。 火山性地震の活発化により3月28日に「臨時火山情報」の第1号が発表され、老人ホームなどでの避難が早期に行われ、幸いな事に被害は少なくてすみました。翌3月29日には火山噴火予知連絡会(予知連)の緊急火山情報の中で「地震活動が急速に活発化、数日以内に噴火の可能性大」との見解が明らかになりました。有珠山噴火対策本部は、噴火前としては前例の無い避難勧告、避難指示を行ない、約1万2000人の周辺住民(伊達市、壮瞥町、虻田町)を避難させていました。
通信総合研究所(CRL)は、災害監視や状況把握に非常に有効な観測装置である航空機搭載合成開口レーダ(SAR)を開発しており、実際の適用例として、有珠山観測の準備を急遽開始すると共に、関係機関との連絡をとりながら、取得されたデータを予知連の事務局である気象庁へ速やかに提供しました。 SARは、Xバンド(9.55 GHz)をCRLが、Lバンド(1.27 GHz)を宇宙開発事業団(NASDA)がそれぞれ開発し、同期観測により2周波で映像データが取得できます。Xバンドの水平分解能は1.5mであり、2つのアンテナを搭載することによって高さ方向の観測も可能です(インターフェロメトリ機能)。また、電波を用いているので火山活動につきものの水蒸気や噴煙に遮られること無く、さらに、曇りであっても噴火口付近の状況が観測可能であるという特徴を持っています。 最初の観測は、4月6日に行なわれました。当日の現地の天候は曇、航空機での観測高度は12,000mであり、肉眼で地上の様子を確認する事は出来ませんでした。観測終了後直ちにCRLでデータの処理を行ない、翌4月7日には処理した映像データを気象庁に提供しました。4月10日、11日は、地下のマグマが地下水に触れて生ずるマグマ水蒸気爆発が継続していました。マグマが有珠山に供給されているとすれば、今後の大噴火につながる可能性があったため、6日以降の有珠山周辺の地形の変動を捉えるべく4月12日に2回目の観測を行ないました。 観測結果 4月6日と12日に得られた有珠山の西、洞爺湖温泉から南側の領域(図1の四角で囲んだ領域)の映像を比較すると、次のような特徴が見られます(図2、図3参照)。 ・金毘羅山の火口の拡大。 ・12日の映像では国道230号沿いに新たに現れた火口が数カ所見られる。 ・洞爺湖温泉街への砂防ダムを乗り越えた泥流が道路を覆っている様子が見られる。 この2回の観測の間の高さ情報についての変化を調べましたが、山の形の変動は捉えられませんでした。この結果を検証するために、予知連有珠山部会へ出向き情報交換を行ったところ、有珠山自体の隆起については噴火前の3月中旬頃から噴火後数日(4月5日頃)までに数十mに及んでいましたが、その後はさほど大きな変化がなかった事が判りました。
今回の火山噴火観測により、我々が研究開発を行なった世界最高水準の合成開口レーダの能力の高さを示す事が出来ました。一方、災害情報提供には緊急観測への即応性が不可欠である事が改めて判りました。また、火山において、マグマの供給による山の形の変動を捉えるためには、定常状態での観測データが必要であり、危険性の高い地域のデータベースを充実させておく必要があります。 今回のように火山噴火に伴う地形変化を正確に求めるためには、航空機自身の飛行情報(緯度、経度、高度等)をより正確に測定する必要があり、今後これらの検討を行ない、精度の向上を目指して行きたいと考えています。 (地球環境計測部データ応用技術研究室) 図の解説 今回の噴火は金毘羅山と国道230号線付近の西山で発生しました。図1の四角で囲まれた部分のSAR画像(4/6、4/12観測)を図2、3に示します。 金毘羅山付近の火口が大きくなっています。マグマ水蒸気爆発で火口が広がったものと推測されます。その上方の洞爺湖温泉街を比較すると、図2に比べ、図3では道がぼんやりとボケた様になっており、泥流の堆積があった事を示しています。さらに図左中央付近の国道230号線のすぐ脇に新たな火口が数点確認できます。
|
||||||||||||
 | ||||||||||||

|
|

|
||||||||||
|
||||||||||||