 |
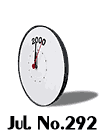 |
 |
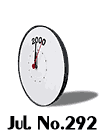 |
 |
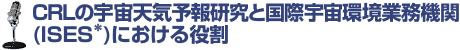 |
|||||||||||||
| 丸橋 克英 |
||||||||||||||
|
宇宙天気予報とは 通信、放送、測位、地球観測などの分野で人工衛星がひろく利用されています。宇宙利用を安全に進めるには、宇宙環境の実際の変化や推移予測が必要です。宇宙の環境は人工衛星や宇宙機器に影響を及ぼすからです。このような宇宙環境の予報を、地上の天気予報になぞらえて、「宇宙天気予報」と呼びます。当所は宇宙天気予報の実現に向けた研究を進めています。 宇宙天気予報の国際機関ISES 宇宙天気予報は世界中の観測データを集めて、効率的に利用することによって、はじめて可能になります。したがって、国際協力によって実施する必要があります。このための国際機関としてISES(アイセス)があります。米国、オーストラリア、日本を中心に11ヶ国**が参加しており、当所が日本のISES予報センターを運営しています。 ISESの前身は、国際電波科学連合(URSI)の勧告で生まれたIUWDS***です。長年にわたって、電波伝搬に関連の深い、太陽現象や地球物理現象を通報する業務を実施してきました。近年その活動の中心が宇宙天気予報へと移行してきたことから、1996年にISESと名称を変更しました。 ISESの組織強化に向けて 宇宙天気予報の研究は、宇宙科学の分野で一つの大きな潮流になっています。宇宙天気が研究者の強い関心の対象になるにつれて、大学や研究機関の試行的な予報が、インターネットを通じて、世界にあふれる状況が生まれています。ISESにとって、この状態は基本的には歓迎すべきものです。しかしながら、試行的な予報が無責任に出され、内容が相互に矛盾する状況も生まれています。矛盾する予報は研究者の注意を呼ぶ役割を果たしますが、一般の利用者には混乱のもとです。ISESは宇宙天気予報の唯一の国際機関として、このような混乱を解消する責務を負っています。 このためには、優れた予報技術を標準として採用したり、優れた予報機関をISESのメンバーに迎え入れるなど、研究コミュニティーに対して、積極的な活動を展開することが必要です。宇宙天気の分野で実力が広く認められていることが大前提になります。 このような観点から、ISES委員長を選挙で選び、その指揮のもとで、ISESの運営体制を強化する方針が全参加国で確認され、1999年の委員長選挙で、筆者が選ばれました。 ISES憲章の制定
ISES憲章は、「標準化された手法による宇宙天気予報の提供と、そのために必要な観測とデータ交換を行うこと」をその使命とし、またISESの予報センターの資格基準を明確に規定しています。同時に、その実施体制として、役員、予報センター、メンバー、作業班等、組織と役割を定め、日常的に予報の研究を進めることを宣言しています。 CRLの役割 宇宙天気の新しい研究成果を予報の実務に取り入れるISESの作業班活動は、昨年から始まっています。当所ではISES予報センターの運営を研究者がひきうけているという特徴があります。CRLの宇宙天気予報研究と、それに基づくISES作業班における指導的な役割が大いに期待されています。 (宇宙科学部長) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
 | ||||||||||||||

|
|

|
||||||||||||
|
||||||||||||||