 |
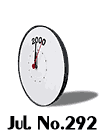 |
 |
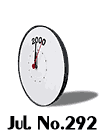 |
 |
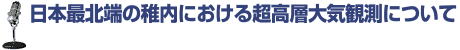 |
|||||||||||||
| 五十嵐 喜良 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
日本最北端の稚内電波観測所の超高層大気観測施設で行われている超高層大気観測について紹介します。稚内電波観測所では、高度60km−1000kmにある電波の反射体として知られる“電波の鏡”電離層の観測を行っています。電離層の中でも、高度100km付近に突発的に発生するスポラディクE層(Es層)は、テレビ、防災無線、飛行機など生活に密接な関係のある分野で利用されているVHF帯電波の異常伝搬の原因となることが知られています。ところが、このEs層の名前の由来は、“突発的に発生する層”という意味であり、この発生を予報することは大変難しいと思われてきました。最近の我々の研究によるとEs層の発生頻度に、2日−16日周期の変動が見いだされ、5月から6月のEs層の発生頻度には、4−6日周期が卓越することがわかってきました。この周期成分は、高度60−100kmの中間圏や下部電離圏とよばれる領域の風の変動にもみられ、Es層の発生頻度と関係ありそうだということが、稚内と山川電波観測所に設置された大型中波MFレーダによる観測から明らかになってきました。 この現象を理解し、予報できるようにするためには超高層大気の風のグローバルな変動や局所的な風の変動とEs層の発生メカニズムとの関係についてさらに詳しい研究が必要です。このため、対流圏から成層圏高度までの風や大気の乱れを高精度に連続観測できるだけでなく、電波の伝わり方に影響する下部電離圏の観測も可能で、下層大気と超高層大気の上下結合に関する研究、超高層大気環境変動に関する国際共同研究を進めるための中核となる観測装置として“超高層大気観測用VHFレーダ”を新たに開発し、稚内の超高層大気観測施設に設置し、2000年6月12日より観測を開始しました。 超高層大気観測施設は、稚内飛行場の近くにあります。電波と光により超高層大気変動を詳細に観測するための観測施設であり、超高層大気観測用のMFレーダ、VHFレーダと大気光観測イメージャーから構成されています。超高層大気観測用VHFレーダは、144本の3素子八木アンテナで構成されるアレイアンテナにより、半値幅約6度の細いビームを形成し、波長が6.5m程度のパルス電波を上空に発射し、大気中の空気の乱れにより散乱する非常に微弱な散乱電波を受信し、リアルタイムで高度な信号処理をすることにより、風の流れや大気中の擾乱現象を、時間分解能1分、高度分解能150mという高分解能で観測することができます。このレーダ装置は、昼夜を問わず超高層大気の風を連続観測できるユニークな観測装置です。成層圏における飛翔体の研究開発や高層気象観測などの分野での利用の可能性もある多機能なレーダ装置です。また、大気光観測イメージャーは、昼間に太陽光のエネルギーを受けた大気中の酸素分子などが蓄積したエネルギーを夜間に光の形で放出するため大気が発光する現象(大気光)を利用して、超高層大気の変化を観測する装置で、大気中の波動現象や太陽活動極大期に出現が期待される低緯度オーロラの活動を無人で連続観測できます。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
この超高層大気観測施設は、電離圏・超高層大気に関する日本最北端の観測拠点としての特徴を生かして、ネットワークで共同研究機関に接続され、グローバルな規模で国内外の共同研究機関と連携して共同研究を推進するマルチメディア・バーチャル・ラボラトリー(MVL)の実験施設としても活用されます。この観測施設や稚内、犬吠、山川、沖縄の電離層観測施設は、通信総合研究所の本所(東京都小金井市)に設置された大容量のダイナミックデータサーバと接続され、電離圏・超高層大気に関する研究機関と共同して、取得された大量の観測データを共有化し、居ながらにして共同研究を進める新しい研究開発スタイルを実現するMVL構築に向けた実証実験を進めているところです。 (宇宙科学部 電磁圏研究室長) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
 | ||||||||||||||
|
|
|

|
||||||||||||
|
||||||||||||||