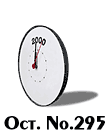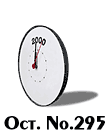平成12年9月30日、米国航空宇宙局(NASA)のDC-8型機が名古屋空港にやってきました(写真)。NASAが7月から10月にかけて行った、パシフィックリム2000キャンペーン(環太平洋地域をアメリカのジェット推進研究所(JPL)の航空機搭載合成開口レーダ(AIRSAR)を用いて観測実験を行うキャンペーン)の一環として日本にやってきたものです。AIRSARは、日本に来るまでに、タヒチ、ニュージーランド、オーストラリア、シンガポール、フィリピンなどを経由して観測を行いました。日本での観測は、通信総合研究所(CRL)がホストとなり10月2日と4日の2日間、北海道から九州までの広い領域のデータを取得し、6日に次の目的地グアムに向かいました。これとほぼ同期してCRLの航空機搭載合成開口レーダ(Pi-SAR)も10月2日から5日までの4日間で同じ地域を観測しました。
合成開口レーダ(SAR: Synthetic Aperture Radar)は、マイクロ波を用いて昼夜・天候にかかわらず地上の様子を映像として高分解能で観測することができます。そのため、地震や火山噴火などの自然災害時に活用されるほか、マイクロ波の特性を活かして、森林破壊、海洋汚染、農業利用、都市環境等の地球環境の把握にも大きく期待をされています。CRLのPi-SARが有珠山の観測に活躍したことはCRLニュース5月号でもご紹介した通りです。JPLのAIRSARとCRLのPi-SARは、ともに世界の最先端のSARですが、お互いに異なるユニークな特長を持っていて、同時に観測することによって相補的なデータを収集することができます。また、こうした異種の航空機SARの同時観測は、これまでに例が無いものです。
JPLのAIRSARは、Pバンド(440MHz帯)、Lバンド(1.2GHz帯)およびCバンド(5.3GHz帯)の3つの周波数を用いてポラリメトリ(偏波を用いた観測)かインターフェロメトリ(2つアンテナの干渉を用いた3次元観測)かどちらかの観測をすることが出来ます。これに対し、Pi-SARは、CRLのXバンド(9GHz帯)と宇宙開発事業団(NASDA)のLバンドの2周波をポラリメトリ機能で同時観測することができるほか、Xバンドではポラリメトリとインターフェロメトリを同時に観測することができます。そこで、これら2つのレーダの同時観測から、P,L,C,Xの4周波の映像の比較ができ、周波数による地上の物体の特性の違いを使ったさまざまな分野の応用研究の発展が期待されます。また、AIRSARとPi-SAR共通のLバンドのデータを用いた定量的な比較から、両者のシステムによるデータの誤差が評価でき、それぞれ別の地域で観測したAIRSARとPi-SARのデータを直接比較することができるようになります。
この実験にあたり国内では宇宙開発事業団をはじめ大学、国立研究機関等による地上観測などを共同で行いました。AIRSARのデータは、これから処理が始まるところですが、Pi-SARのデータは、徐々に処理を進め実験参加者へのデータ配布を始めています。CRLを含む国内の研究機関等における今後の比較解析が期待されています。最後に、本実験の遂行にあたりご理解、ご協力をいただいた関係機関に感謝いたします。
(地球環境計測部 データ応用技術研究室長)
 |
| Pi-SAR(CRL)を搭載したガルフストリームII型機(左)とAIRSAR(JPL)を搭載したNASAのDC-8型機(右)。名古屋空港近傍にて。
|
|