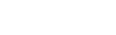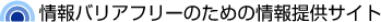視覚障害
視覚障害は、目で物を見る感覚(視力や視野、色覚、光覚等)の働きに障害のある状態をいう。
聴覚障害
聴覚障害は、耳で音を聞き取る能力に障害のある状態をいう。
平衡機能障害
平衡機能障害は、身体のバランスを保とうとする感覚の働きに障害のある状態をいう。めまい、ふらつき、耳鳴りや吐き気などの症状が現れることがある。
音声又は言語機能の障害
音声又は言語機能の障害は、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいう。構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含まれる。
そしゃく機能の障害
そしゃく機能の障害は、そしゃく・嚥下機能の著しい低下を起因として経口的な食物・栄養摂取が困難な状態をいう。
肢体不自由
肢体不自由は、四肢(上肢:手と腕、下肢:足と脚)や体幹(胴体)に障害・欠損等があるため、日常生活で不自由のある状態をいう。
内部障害
内部障害は、心臓や腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫細胞、肝臓等の内臓器官に障害のある状態をいう。
全盲
全盲は、視覚的な情報を全く又はほとんど得られない状態をいう。
盲ろう
盲ろうは、視覚と聴覚の両方に障害のある状態をいう。
次の4種類に大別される。
- ①全盲ろう:全く見えず聴こえない状態
- ②弱視ろう:見えにくく聴こえない状態
- ③全盲難聴:全く見えず聴こえにくい状態
- ④弱視難聴:見えにくく聴こえにくい状態
弱視
弱視は、眼鏡やコンタクトレンズを用いても十分な視力を得られない状態をいう。
色覚障害
色覚障害は、他の人と色の見え方が著しく違ってしまっている状態をいう。
高齢者
世界保健機関(WHO)の定義では、65歳以上の人を高齢者という。
学習障害
学習障害は、知的発達の遅れや視聴覚機能に問題がないにもかかわらず、聞く・話す・読む・書く・計算するなどの特定領域にだけ著しく困難さを示す状態をいう。
ディスレクシア
ディスレクシアは、学習障害の一種で、全体的な発達に遅れはないものの、文字の読み書き学習に著しい困難を抱える障害をいう。
知的障害
知的障害は、記憶や計算、読み書き、学習などの知的行動に障害のある状態をいう。
精神障害
精神障害は、精神機能に障害のことにより、日常生活や社会参加に困難をきたしている状態をいう。
統合失調症、気分障害(躁うつ病、うつ病、躁病)、精神症・ストレス関連障害など様々な種類がある。
発達障害
発達障害は、脳機能の発達に関係する障害である。他人との関係づくりやコミュニケーション等が苦手であるが、優れた能力が発揮されていることもあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい。
中途障害
中途障害は、生まれた時からある先天性の障害と異なり、病気や事故等の事態によって生じた障害をいう。
障害者手帳
障害者手は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称である。
○障害者手帳
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市又は中核市の市長が交付する手帳である。
○身体障害者手帳
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
障害者雇用率
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務がある。(障害者雇用促進法43条第1項)
○従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者の雇用を義務付け
<令和6年4月から令和8年6月まで>
民間企業:2.5% 国、地方自治体:2.8% 都道府県等の教育委員会:2.7%
<令和8年7月以降>
民間企業:2.7% 国、地方自治体:3.0% 都道府県等の教育委員会:2.9%
○障害者雇用率
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html#01