 |
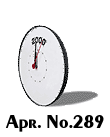 |
 |
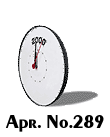 |
 |
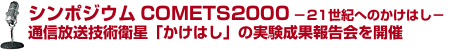 |
|||||
| 若菜 弘充 |
||||||
シンポジウムでは、COMETSの開発と実験に関わった多数の機関からその詳細が報告されました。開発報告では、宇宙開発事業団からCOMETSに搭載された3つのミッションの開発に関する報告がされました。続いて、中継器系、イオンエンジン系、姿勢制御系、2液式統合型推進系の開発に関して、それぞれ日本電気、東芝、三菱電機、石川島播磨重工業から報告がありました。
COMETSの運用時、当研究所では、Ka帯(31及び21GHz)とミリ波帯(47及び44G Hz)による移動体衛星通信実験並びに21GHzによる衛星放送実験を実施しました。 移動体実験では、従来より高い周波数を使うことによる電波伝搬特性の違い(樹木、電柱、電線等による遮蔽効果が周波数により異なる)、衛星の仰角による伝搬特性の違い、自動車走行時の通信実験、航空機を用いた衛星通信実験、携帯端末同士の直接衛星通信が可能となる再生中継器の性能評価実験を行いました。軌道の関係で、日本で実験ができない時期には、オーストラリアのシドニーに実験車を輸送し現地の国立研究所や大学と共同で実験を行いました。 衛星放送実験は2007年から実用化が可能な新周波数21GHzを用いた実験で、BSハイビジョン放送より4倍から5倍の広帯域高精細(HD)映像の衛星伝送実験、多チャネルHDTV伝送実験、立体HDTV実験等を実施しました。当初は家庭用の75cm径のパラボラアンテナで受信する実験を計画していましたが、COMETSが周回衛星となってしまったため、このアンテナに追尾装置を取り付けて実験を行う一幕もありました。 さらに、アジア太平洋地域における降雨による信号減衰の統計的特性を調べる目的で、オーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、日本に受信局を設置して3機関共同観測を行いました。短期間ではさすがに充分なデータを取得できませんでしたが、熱帯降雨地域の雨の降りかたは日本と異なっており極めて興味深いデータを得ることができました。 静止化失敗後、多くの関係者の昼夜を問わない努力により、衛星搭載機器の基本機能確認試験や数多くの通信放送実験が行われ、短期間ながら、様々な国内外の研究機関や大学と共同研究ができたことは大変有意義でした。得られた研究成果を次世代の衛星通信放送技術へ活用していきたいと考えています。 (第三研究チームリーダー)
|
||||||
 | ||||||

|
|

|
||||
 世界最高速HEMT(高電子移動度トランジスタ)を開発 世界最高速HEMT(高電子移動度トランジスタ)を開発
 東京エアロスペース2000出展 東京エアロスペース2000出展
 6号館完成 6号館完成
 第98回 通信総合研究所
研究発表会のお知らせ 第98回 通信総合研究所
研究発表会のお知らせ
 新規採用者の自己紹介 新規採用者の自己紹介
 学位取得者リスト/学会受賞者リスト/
人事異動 学位取得者リスト/学会受賞者リスト/
人事異動
|
||||||