 |  |
 |  |
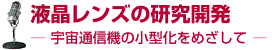 | ||||
| W. クラウス | ||||
| はじめに | ||||
| 液晶波面変調器の構造 | ||||
| ||||
| 駆動電極の設計 | ||||
| ||||
|
印可電圧による発生する位相分布は、常に目やCCDカメラで観測できないため、液晶レンズを2枚の偏光板の間で挟んで、位相変調を写真1bに示すような強度変調に変換しました。この強度分布を数値的に解析した結果として、図4に示すような位相分布を得ました。焦点距離を80mmから180mmまで変化させても、回折限界に近い(理想のレンズとほぼ同じような)結像が得られることが分かかりました。ここでは、130mmのみの焦点距離で観測した強度分布を写真2に示します。 | ||||
| ||||
| まとめ (宇宙通信部宇宙技術研究室) | ||||
 | ||||
| ||||
 タンパク質モータの動きの仕組みを追って タンパク質モータの動きの仕組みを追って−定説を覆す滑りメカニズム ―  デジタル・ナロー通信方式とは? デジタル・ナロー通信方式とは?−400MHz帯等業務用無線の周波数有効利用の促進に向けて ―  BOOK INFORMATION BOOK INFORMATION |