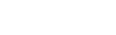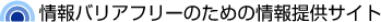「デジリハ」について教えてください。
仲村:福山型先天性筋ジストロフィーという難病を抱えている創業メンバーの加藤さくらの娘さん「まこちゃん」の存在がきっかけです。この難病は次第に筋肉が弱くなってしまい、将来的には呼吸や飲み込みなどの身体機能にまで影響が出る可能性があります。そのため、幼少期からリハビリすることが必要です。
しかし、「まこちゃん」にとってリハビリは楽しいものではありませんでした。特に福山型先天性筋ジストロフィーはリハビリで改善する部分はあるものの、現在完治する治療法がないため、病状を悪化させないように状態を維持するためのリハビリをすることが多いです。そのため、モチベーションにつながり難いと言えます。
加藤は、子どもが苦痛を感じないで良い効果を得ることができるリハビリを模索していて、現在当社代表である岡勇樹に相談しました。岡は、医療や福祉の専門性と難病や障害の当事者性を活かしたコンテンツづくりを行うNPO法人Ubdobe(ウブドベ)の代表理事を務めています。岡も加藤と同じような課題を感じていて、二人の思いが一致したことから、デジタルアートを活用したプロジェクトが発足しました。
このプロジェクトに、デジタルアートやアプリを開発するクリエイターはもちろんのこと、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、看護師など医療福祉に関わるメンバーが参画しました。障害のある当事者やリハビリのことをよく理解しているメンバーが集い、プロジェクトを推進してきた点は特徴だと思います。

リハビリは体の機能を維持・向上させるために必要なものです。しかし、リハビリの多くは単調で、ときには苦痛を伴うため、子どものモチベーションを維持することが難しいという課題がありました。そこで、エンタメのように楽しみながら取り組めるリハビリを創り出せないかということで、同じ志を持つ障害児を育てる保護者、理学療法士や作業療法士などのメンバーが集まってデジリハを考案しました。
「デジリハ」の活用にはパソコンとセンサーが必要です。視線の動きを捉えるセンサーや手の骨格推定をするセンサー、四肢の動きを検知する加速度センサーなどを用いて運動を検知し、有線やBluetoothなどで接続し、データをパソコンに送信します。それにより、例えば、パソコンに動物のデジタルアートが表示されたとき、それをじっと見続けたり、手で掴んだりする動作をセンサーが捉えることで、動物を捕まえたことになります。現在、5種類のセンサーが連携可能です。プレイ環境には複数の選択肢があり、パソコンの画面上でプレイする方法や、大きな壁に映して直接触れてプレイする方法があります。使用環境やお子さんの特性に応じて、最適なプレイ環境を選べます。