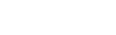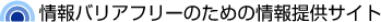どのようなきっかけで「BOCCO emo」の開発をスタートされたのでしょうか。
多賀谷:もともとは、初代「BOCCO」が2015年に登場しており、「BOCCO emo」はその2代目になります。初代「BOCCO」は、代表の青木が仕事で忙しくしていても子どもとコミュニケーションが取れるようなツールがほしいという思いから開発されました。
その後、2018年に初代「BOCCO」を増産するのか、それとも次世代機を開発するのかを判断する時期がありました。当時は、2015年から3年間の間に同価格帯のハードウェア性能が向上し、さらにスマートスピーカー*が流行し始めた時期でもありました。そこで、初代「BOCCO」のコンセプトを引き継ぎつつ、音声認識機能を取り入れた次世代機の開発に取り組むことにしました。
発案からおよそ2年の開発期間を経て、「BOCCO emo」は誕生しました。そして「BOCCO emo」を世に送り出したところ、高齢者向けのサービスに活用したいという声を複数の方々からいただきました。その中の一つが、「セコム暮らしのパートナー久我山」での実証実験です。同施設では、セコムとDeNAのコミュニケーションサービスが展開している、高齢者のQOL(生活の質)向上を目指すコミュニケーションサービス「あのね」を提供するにあたり、「BOCCO emo」を活用した実証実験を行いました。その結果、誰かとつながる安心感や孤独の解消、生き生きとした生活の継続に「BOCCO emo」が役立つことが認められたため、今では同施設でも導入されています。
*AIアシスタント機能を搭載し、音声で操作できるワイヤレススピーカーのこと。インターネットに接続して、音楽再生、情報検索、家電操作など、さまざまな機能が利用可能
「BOCCO emo」はどのような仕組みで稼働しているのでしょうか。
多賀谷:まず、本体には音声認識器と音声合成器が内蔵されています。そのため、本体のボタン操作、もしくはハンズフリーでメッセージを送ることができるほか、スマホアプリを通じて遠隔からテキストメッセージを打ち込んで「BOCCO emo」の声で発話が可能です。また、各種センサーも内蔵されています。例えば、人感センサーとして機能する「レーダーセンサー」により、人が近くにいるかどうかを認識できます。「照度センサー」は部屋の明るさを判断し、「加速度センサー」は「BOCCO emo」が立っているのか倒れているのか、あるいは何かにぶつけられたかなどの状態を検知できます。これらにより、ユーザーが操作した際にどのようなリアクションをすべきか判断できる仕組みです。
さらに、オプションの各種センサーと連動させることで、注意喚起やリマインドも可能です。たとえば、おやつの箱にセンサーを取り付けると、箱を開けた際に「夜に食べると良くないよ」と声を発したり、室温を検知して「今部屋が暑いよ」と教えてくれたりします。このように、センサーを活用して気づきを与える機能も搭載されています。他にも、スマートスピーカーでいう「スキル」のように、お気に入りのコンテンツを購読する仕組みも搭載しています。「BOCCO emo」でも同様に、“BOCCOチャンネル”という機能を追加でき、お気に入りの機能をアドオンすることが可能です。
この“BOCCOチャンネル”には、高齢者向けに頭の体操をしてくれるコンテンツがあります。登録しておくと、毎日指定の時間に「BOCCO emo」がなぞなぞやクイズを出してくれます。また、ヘルスケアチャンネルといった体重計や血圧計などのヘルスケアデバイスと連携できる機能もあります。基本的には、家族同士のつながりをサポートすることがメインですが、このような“BOCCOチャンネル”を通じて、一人暮らしの高齢者に気づきを与えたり、よき話し相手になってくれたりします。