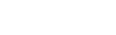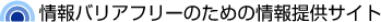「ケアびー」が目指す未来はどのようなものですか?
私たちは、「自宅を介護施設にする」というビジョンの実現を目指しています。このビジョンは、単に在宅介護をサポートするだけでなく、利用者が住み慣れた環境で介護施設に近いレベルのケアを受けられる体制を構築することを意味します。そのために次のような具体的な取り組みを進めています。
1つ目は、利用者が一貫したケアを受けられるよう、ケアマネージャーや訪問看護師、医療機関での活用ケースを増やしたいと思っています。例えば、「ケアびー」を通じてオンラインで服薬指導や診療が可能になるので、移動時にかかる高齢者への負担も大幅に軽減することが期待されます。
2つ目は、多様な対象へ展開することです。「ケアびー」の設計理念である「機械が人に合わせる」を軸に、高齢者以外の対象にも対応するツールとして進化させていくことを視野に入れています。実際に「障害を持つ方にも利用できるのではないか」という声を多くいただくようになっています。
障害者を支援の対象とするには、障害の種類や症状、ニーズが多様であるため、個別の調整や機能追加が必要となります。例えば、視覚や聴覚に制約のある方には、音声ガイドや点字ディスプレイを接続するなどの追加機能が必要になると考えています。また、身体的な動作が制限される方には、音声認識や目線操作といった代替的なインターフェースを導入することも視野に入れています。
3つ目は、「ケアびー」を中心とした持続可能なケアモデルを構築することです。「ケアびー」をコミュニケーションツールとして活用し、介護者、医療機関、行政が連携しやすい環境をつくることで、誰もがその人らしい生活を送れる社会を実現したいと思っています。このモデルで「ケアびー」が要(かなめ)となることで、個人の尊厳を守りながら、より包括的で効率的なケア環境を提供していきます。
今は高齢者分野に注力していますが、技術や運用のノウハウを蓄積して、障害者や子どもも対象に加え、新たな展開を本格的に進めていく計画です。このプロセスを通じて、「ケアびー」が幅広く人々の生活の質を向上させる社会的基盤となることを目指していきます。
取材協力:
Hubbit株式会社
取材日:
2024年11月