
| 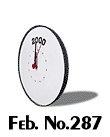 |

| 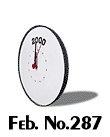 |

|
今回の『研究往来』は、茨城県ひたちなか市にある平磯宇宙環境センターに伺いました。美しい海岸線をのぞむ高台に建つセンターの玄関で、小原さんはにこやかに私たちを出迎えてくれました。 「1969年にアポロ宇宙船の月面着陸、そして70年には日本初の人工衛星“おおすみ”が打ち上げられました。私の少年時代のキーワードはまさに『宇宙』だったんです」 宇宙やロケットに関心をもった理由を、小原さんはこう楽しそうに話します。小原さんの研究テーマは“宇宙空間物理学”。大学院在学中に、科学衛星のプロジェクトに参加(“おおぞら”1984年打ち上げ)そして宇宙科学研究所の職員となってからは“あけぼの”(1989年打ち上げ)のプロジェクトにも参加しました。
その代表的なものがバンアレン帯(放射線帯)で、他にオーロラを起こす粒子が存在する領域もあります」 地球の電離層より高い宇宙空間は“ジオスペース”と呼ばれていますが、人工衛星などによる観測が進むにつれて、さまざまな自然現象のしくみが解明されてきました。 オーロラもそのひとつだといいます。 「太陽風(超音速で太陽から吹き出す荷電粒子の流れ)が吹いてきて、ジオスペースにエネルギーが貯まります。しかし、太陽風のエネルギーは一定ではなく、強かったり弱かったり。エネルギーが沢山たまりすぎると大きな爆発が起き、磁力線に沿って電子が落ちてきて、大気と衝突を起こして光を出すのがオーロラです。このオーロラは、エネルギーの変化の測定によって、発生する時間と場所が予測できるようになりつつあり、近い将来、その情報を一般に提供することも考えています」 以前、国際会議が開催されたスウェーデンで見たオーロラの美しさと、そのときの感動は忘れられないという小原さん。こういった感動が、物事を調べていく動機になるといいます。研究においても、人から得た情報や知識だけでなく、常に自分の実験や体験を大事にしているそうです。 「ジオスペースでは、時々、嵐(ジオストーム)が起こります。嵐の時は、オーロラは激しく輝きます。と同時に、嵐によって放射線粒子が異常に増えて、人工衛星の故障や破壊を引き起こす事があるのです」 自ら人工衛星の打ち上げを体験している小原さんは、その苦労を考えると、衛星の障害となるジオストームを予測し、なんとしても衛星を護りたい気持ちになるといいます。 「2004年には、国際宇宙ステーションが完成する予定ですが、そこでも放射線粒子の脅威は避けられません。ジオストームの予知が正確にできれば、危険を回避することが可能になります。そのため、現在の宇宙科学の流れとして、スペース・ウェザー(宇宙天気)の研究が盛んになっています」 それだけではありません。オゾン層の破壊などにも、ジオストームが関係しているのではないか? という説を唱える研究者もいるといいますから、私たちの生活とも全く関係がないとは言い切れないのです。 未来の宇宙利用を見据え、宇宙環境について語る小原さん。その眼は宇宙にあこがれた少年時代そのままのようです。しかし「子どもたちはあまり宇宙に興味がないようで…」とちょっぴりさみしげなパパの顔ものぞかせます。ちなみに小原さんは奥様と3人のお子さんの5人家族。一番上のお兄ちゃんはすでに「お医者さんになる」という志を持っているとか。 「妻が鎌倉の生まれで海のそばで育ったこともあり、休日には、車で海岸線をドライブしたり、潮干狩りに行ったりして楽しんでいます。年に1、2回は鹿島神宮まで行って、お参りします。『何かいいことありますように』って(笑)」 センター近くの漁港で水揚げされる豊富な海産物に、家族の胃袋も満足しているそうです。
21世紀までもう300日あまり。宇宙は身近になり、研究の対象から利用の時代に移行しつつあります。そこでは、宇宙の“安全な利用”が大きな課題になると小原さんは言います。『鉄腕アトム』にあこがれ、ロケットの打ち上げに胸をときめかせた少年の夢は、確実に現実のものとなる――。その日に向かって、小原さんの宇宙環境の研究は続いていきます。 (取材・文/中川和子) |
|||||||
 | ||||||||