 |
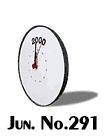 |
 |
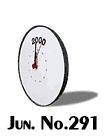 |
 |
 |
|||||||||||
| 今水 寛・宮内 哲 |
||||||||||||
|
概要 私たちはたくさんの道具を使い、便利な生活を送っています。道具の中には、箸やはさみのように、始めは使いこなすのに苦労するけれど、繰り返し練習することで、自分のからだの一部のように自在に使えるようになるものがあります。このような、道具を使う「わざ」を修得するとき、小脳と呼ばれる脳の一部が重要な役割を果たしているのではないかと言われてきました。私たちは、このような道具の使い方を練習しているときの、人間の脳活動を、ファンクショナルMRIと呼ばれる装置で計測しました。その結果、人間の小脳に道具を使う「わざ」が、徐々に獲得されていく様子が初めて明らかになりました。
小脳は、後頭部の下の方にあります(図1)。小脳はからだを速く滑らかに動かすときや、運動技能の修得に重要な役割を果たすと考えられてきました。小脳における学習の仕組みをめぐって、相反する2つの学説がありました。学習とともに、小脳に記憶が蓄積されるという説と、小脳は過ち(誤差)の修正に重要なのであって、記憶は脳の他の場所に蓄えられるという説です。この2つの説を検証するために、私たちは、新しい道具の使い方を学習しているときの、人間の小脳活動を計測し、どのような変化が起きているかを調べました。 実験の方法 実験で使った「新しい道具」は、特殊なコンピュータマウスで、マウスを動かす方向と、画面上のポインタが動く方向に一定のずれが生じるようにしてあります。仕事やゲームで、マウスを使うことが多くなりましたが、例えば、マウスを上下逆さまにして、操作してみてください。初めは戸惑いますが、繰り返し練習することで、自由に動かすことができるようになります。コンピュータ画面に、動き回るターゲットを表示し、特殊なマウスを操作して、ターゲットを追跡するというゲームを、被験者に数時間にわたって練習してもらいました。 練習中の被験者の小脳活動を、関西先端研究センターのファンクショナルMRI(機能的磁気共鳴画像)装置で計測しました。脳の細胞が活動すると、微少な血流の変化が起きます。この装置は、その変化がどの場所で起きているかを、ミリメートル単位の正確さで計測することができます。
図2は、人間の小脳の断面図です。赤い枠で囲った部分では、練習の始めは、盛んに脳活動が起きていましたが、練習が進むにつれて減少しました(図3の赤い曲線)。一方、青い色を付けた部分では、練習を充分にしても、あまり活動は下がりませんでした(図3の青い曲線)。図3の緑の曲線は、青い曲線と赤い曲線の差を示しています。練習の始めは、差がありませんが、練習するにつれて、次第に差が開いて行く様子がわかります。 練習の際のマウスの軌跡データと、ファンクショナルMRIから得られた小脳の活動データを詳細に比較した結果、図2の赤い枠で囲った部分の活動は、マウスの使い方に不慣れなために生じた、過ち(誤差)に正確に比例していました。つまり、図3の赤い曲線で示した活動は、誤差の情報を伝える役目を果たしていると考えられます。一方、緑の曲線は、誤差が少なくなるにつれて上昇していて、この活動は、練習によって修得された、「わざ」の記憶を反映していると考えられます。ちなみに、別の実験で、この活動が単純な手の動きによるものではないことは確認しています。 小脳の学習メカニズム この研究が実証した小脳の学習メカニズムを、次のようなたとえ話で解説してみます。教室に、先生とたくさんの生徒がいるところを想像してください。この場合、先生は、脳の大部分を占める大脳で、生徒が小脳です。先生は始め、たくさんの生徒(図2の赤い枠で囲った部分)にまんべんなく教えていますが、次第に、まともな答えを出す生徒(図2の青い部分)の周辺に、的を絞って教えるようになります。最終的に、他の生徒は居眠りをし、先生までが休んでも、一部の生徒(青い部分)だけで答えを出せるようになります。緑の曲線で示した活動は、先生からの教え(赤い曲線)を差し引いて、青い部分の生徒たち自身が出した答えを反映していると考えられます。面白いことに、先生は正解を教えるのではなく、生徒の間違い(誤差)を指摘するだけです。「わざ」の修得は、このような「淘汰」の結果であると言えましょう。一方、他の道具の使い方を修得するときには、別の生徒たちが活躍すると考えられるので、得意分野を生かした個性尊重のシステムであるとも言えます。 終わりに 実験結果は、冒頭で述べた2つの学説のうち、小脳に記憶が蓄積されるという説を支持しています。小脳が誤差の修正に重要であるという説は、記憶は他の部分に蓄積されるという点で間違っていました。確かに小脳の大部分の活動(赤い曲線)は、誤差に比例していました。しかし、誤差による活動を差し引くことで、修得された記憶を反映する活動(緑の曲線)が検出できるのです。 この研究は、小脳に記憶が蓄積され、その記憶は誤差の情報で修正されるという理論を、初めて人間の脳で実証したことになります。この発見は、心理学・神経科学の分野で重要であるだけでなく、工学的な応用も期待できます。例えば、使いやすいヒューマン・インターフェースでは、小脳の活動も早く減少するが、使いにくいインターフェイスでは、思い通り操作できないため、誤差を反映する活動が、なかなか減らないと予測できます。脳の活動を指標として、インターフェイスの使いやすさを評価することができます。複雑な操作を必要とする機械が多くなってきましたが、箸や、はさみのように、一度使い方を覚えれば、誰にでも、からだの一部のように自然に使えるインターフェイスの開発に役立つと期待できます。 (科学技術振興事業団川人学習動態脳プロジェクト・ 郵政省通信総合研究所関西先端研究センター知覚機構研究室) |
||||||||||||
 | ||||||||||||
|
|
|

|
||||||||||
|
||||||||||||