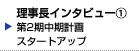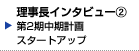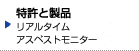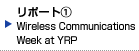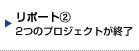![]()
丂![]()
| 乽擔杮偺尋媶惉壥偑悽奅揑偵擣抦偝傟偰巊傢傟傞偙偲傪栚巜偟偨偄乿 | ||
| 憗懍偱偡偑丄怴偨側拞婜寁夋偑僗僞乕僩偡傞偵偁偨傝丄戞侾婜拞婜寁夋傪怳傝曉偭偰偛姶憐傪偍暦偐偣偔偩偝偄丅 | ||
丂傑偨丄奀奜偺尋媶婡娭偲偺楢実偵偮偄偰傕愊嬌揑偵庢傝慻傒傪峴偄傑偟偨丅巹偑棟帠挿偵廇擟偟偨摉帪偼丄俶俬俠俿偼懡曽柺偱慺惏傜偟偄尋媶撪梕傪帩偮偵傕偐偐傢傜偢丄昁偢偟傕崙嵺揑偵偼惓摉偵昡壙偝傟偰偄側偐偭偨傛偆偵巚偊偨偺偱偡丅崙嵺揑側擣抦搙偑幚椡偵斾傋偰掅偔丄奜崙偺尋媶婡娭偲楢実偟偰偄偔偙偲偑昁梫偲姶偠傑偟偨丅忣曬捠怣偲偄偆偺偼僌儘乕僶儖側媄弍偱丄擔杮偩偗偱偱偒偰傕丄偦傟偑奜崙偵捠梡偟側偗傟偽堄枴偑偁傝傑偣傫丅僌儘乕僶儖側媄弍惉壥傪敪弌偟偰偄偔偨傔偵傕奜崙偺尋媶強偲嫤挷偟偰恑傔偰偄偔偙偲偑娞梫偵巚偄傑偡丅崱屻傕峏側傞搘椡偑媮傔傜傟傞偲偙傠偱偟傚偆丅偙傟傑偱丄僼儔儞僗傗拞崙偲尋媶嫤椡嫤掕傪寢傫偱崙嵺嫟摨尋媶傕巒傑偭偰偄傑偡丅崙嵺夛媍傪奀奜偱庡嵜偟偰丄俶俬俠俿偺懚嵼傪擣抦偟偰傕傜偊傞傛偆側妶摦傕揥奐偟偼偠傔偰偄傑偡丅 |
||
| 俶俬俠俿偱偼丄帺傜尋媶奐敪傪幚巤偡傞偲偲傕偵丄奜晹傊偺埾戸偵傕庢傝慻傑傟偰偄傞偦偆偱偡偑丠 | ||
| 挿旜丗巹偨偪偼嶻嬈奅傗戝妛偱偼幚巤偑崲擄側尋媶奐敪偵偮偄偰丄帺傜尋媶幰傪攝抲偟偰幚巤偟偰偄傑偡偑丄尋媶奐敪偺拞偵偼丄奜晹偺尋媶奐敪儕僜乕僗傪妶梡偟偨曽偑丄傛傝岠棪揑丒岠壥揑偵幚巤偱偒傞壽戣傕偁傝傑偡丅偦偺傛偆側壽戣偵偮偄偰偼丄柉娫婇嬈摍偺奜晹偺婡娭偵尋媶奐敪傪埾戸偡傞偙偲偵傛傝丄傛傝堦憌偺惉壥傪嫇偘傞偙偲偑壜擻偲側傝傑偡丅 丂傑偨丄埾戸尋媶偵偼傕偆1偮偺儊儕僢僩偑偁傝傑偡丅偦傟偼丄変乆偑尋媶奐敪偟偨撪梕傪幚梡壔偵帩偭偰偄偔偙偲丄尋媶奐敪抜奒偐傜奐敪抜奒偦偟偰惢昳壔偲偮側偘偰偄偔嫮椡側庤抜偱偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅偙傟偼幚嵺偵偼側偐側偐搘椡偑昁梫側晹暘偱偁傝丄堦挬堦梉偵偼偄偒傑偣傫偑丄抧摴偵宲懕揑側庢傝慻傒傪懕偗偰偄偔偙偲偑昁梫偲峫偊偰偄傑偡丅 丂傕偆1偮丄朰傟偰偼側傜側偄栶妱傪NICT偼帩偭偰偄傑偡丅偦傟偼丄尋媶惉壥偺傾僂僩僇儉傪堄幆偟偰丄惉壥傪愊嬌揑偵敪怣偟偰偄偔偲偄偆偙偲偱偡丅埲慜偼幮夛揑側梫場傕偁傝丄偄偢傟偺岞揑側尋媶婡娭傕偙傟傜偺敪怣偵娭偡傞堄幆偑掅偐偭偨偲巚偄傑偡丅崱屻偼尋媶惉壥傪偄偐偵偟偰幮夛偵峀偔敪怣丒採嫙偟偰偄偔偐偲偄偆偙偲偑壽戣偺1偮偵側偭偰偄傑偡丅傑偨丄抦嵿傪扴摉偡傞僙僋僔儑儞偺塣梡傗僷僥儞僩偺庢摼側偳傕廳梫偱偡偑丄抦嵿偲偄偆尋媶惉壥傪崙嵺揑側昗弨偵傑偱帩偭偰偄偔偙偲傕戝愗偱偡丅擔杮偺尋媶惉壥偑悽奅揑偵擣抦偝傟偰巊傢傟傞偙偲傪栚巜偟偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅昗弨壔偲偄偆偙偲偼崙嵺揑偵傕崙撪揑偵傕擄偟偄偙偲偱偼偁傝傑偡偑丄傗傜側偗傟偽搘椡偑柍偵側偭偰偟傑偄傑偡偐傜丅 |
||
| 偲偙傠偱丄崱婜偺拞婜寁夋婜娫偱偼怴偨側僗僩儔僥僕乕偲偲傕偵丄巃怴側慻怐懱惂傊偺夵慻偑峴傢傟偨傛偆偱偡偹丅 | ||
挿旜丗僗僩儔僥僕乕偲偟偰偼俁偮偺拰傪棫偰偰丄偙傟傪幚峴偡傞偨傔偺慻怐傪栚巜偦偆偲峫偊偰偄傑偡丅傑偢丄僗僩儔僥僕乕偺侾偮栚偺拰偑乽怴悽戙僱僢僩儚乕僋媄弍乿偱偡丅岝僱僢僩儚乕僋傪拞怱偵丄偙傟偐傜偺僱僢僩儚乕僋偼偳偆偁傞傋偒偐傪尋媶奐敪偟傑偡丅柍慄捠怣傗塅拡捠怣側偳傪帇栰偵擖傟偨挻崅懍偺僱僢僩儚乕僋媄弍偵娭偡傞尋媶傪悇恑偡傞椞堟偱偡丅俀偮栚偺拰偑乽儐僯僶乕僒儖僐儈儏僯働乕僔儑儞媄弍乿偱偡丅忣曬捠怣傪傛傝偄偭偦偆恖娫偵恎嬤側傕偺偵偡傞偨傔偺尋媶奐敪傪峴偄傑偡丅嵟屻偺拰偑乽埨怱丒埨慡偺偨傔偺忣曬捠怣媄弍乿偱偡丅戝婯柾嵭奞偺懳墳傗僙僉儏儕僥傿側偳丄傗傞傋偒偙偲偼嶳愊偟偰偄傑偡丅埲忋俁偮偺尋媶奐敪椞堟偵婎偯偒丄俈偮偺尋媶僙儞僞乕偵嵞慻怐壔偟傑偟偨丅偦傟偧傟偺尋媶僙儞僞乕偵尋媶僌儖乕僾傪愝偗丄僌儖乕僾儕乕僟乕偺傕偲偵尋媶僥乕儅傪棫偰偰尋媶慻怐傪峔惉偟丄儕僼儗僢僔儏偟偰尋媶奐敪偵庢傝慻傕偆偲偟偰偄傑偡丅 丂偙傟偵壛偊偰丄僾儘僌儔儉僨傿儗僋僞乕偲偄偆巇慻傒傪摫擖偟傑偟偨丅俶俬俠俿偼奜晹偲偺楢実尋媶婡擻傪帩偪傑偡偑丄偦偆偄偆傕偺傪堦娧偟偰帇栰偵廂傔偮偮丄憡屳偺嫤挷偟偨尋媶娭學傪抸偔昁梫傕偁傝傑偡丅偦傟傜傪墶抐揑偵挱傔偰尋媶僗僩儔僥僕乕傪棫偰偰恑傔丄岠棪揑側儅僱僕儊儞僩傪峴偆栶妱傪扴偆偺偑僾儘僌儔儉僨傿儗僋僞乕偱偡丅傑偢俇偮偺僾儘僌儔儉偵偮偄偰奜晹偺桳幆幰偵廇擟偟偰偄偨偩偒丄僾儘僌儔儉傪僐乕僨傿僱乕僩偟偰偄偨偩偔偙偲偵偟傑偟偨丅崱傑偱偵側偐偭偨億僕僔儑儞偱偡偑丄僾儘僌儔儉僨傿儗僋僞乕偺曽乆偼挻堦棳偺愭惗曽偽偐傝側偺偱旕忢偵婜懸偟偰偄傑偡丅
丂偙傟偵壛偊偰丄僾儘僌儔儉僨傿儗僋僞乕偲偄偆巇慻傒傪摫擖偟傑偟偨丅俶俬俠俿偼奜晹偲偺楢実尋媶婡擻傪帩偪傑偡偑丄偦偆偄偆傕偺傪堦娧偟偰帇栰偵廂傔偮偮丄憡屳偺嫤挷偟偨尋媶娭學傪抸偔昁梫傕偁傝傑偡丅偦傟傜傪墶抐揑偵挱傔偰尋媶僗僩儔僥僕乕傪棫偰偰恑傔丄岠棪揑側儅僱僕儊儞僩傪峴偆栶妱傪扴偆偺偑僾儘僌儔儉僨傿儗僋僞乕偱偡丅傑偢俇偮偺僾儘僌儔儉偵偮偄偰奜晹偺桳幆幰偵廇擟偟偰偄偨偩偒丄僾儘僌儔儉傪僐乕僨傿僱乕僩偟偰偄偨偩偔偙偲偵偟傑偟偨丅崱傑偱偵側偐偭偨億僕僔儑儞偱偡偑丄僾儘僌儔儉僨傿儗僋僞乕偺曽乆偼挻堦棳偺愭惗曽偽偐傝側偺偱旕忢偵婜懸偟偰偄傑偡丅 |
||
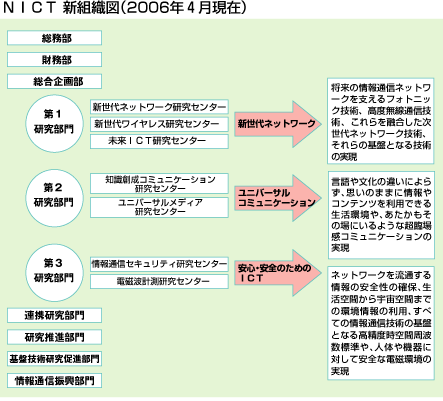 |