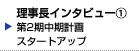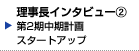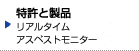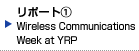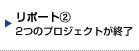![]()
![]()
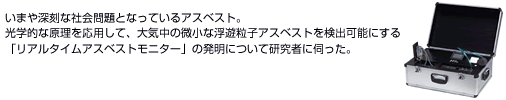
| Q. アイデアや装置の工夫など、もっともご苦労された点はどこでしょう。 | ||
繊維状粒子を識別する方法として、散乱光の偏光を計測する方法は、研究開発を提案したときから頭にありました。そこで、共同研究者の伊藤繁夫東洋大教授に円柱粒子と球粒子の光散乱プログラムを開発してもらい、卒研生の力も借りて、光散乱の偏光を計算して、レーザー光を入射する方向で計測するのが良いということを見付けました。しかし、強いレーザー光を入射する方向と同じ方向で、微弱な散乱光を計測することはほぼ不可能ですので、レーザー光からぎりぎり少しずらした方向で散乱光を計測する方法を工夫して装置を実現しました。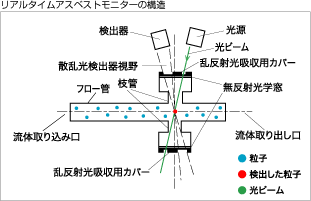 |
||
| Q. 開発時の工夫や苦心などのエピソードはありますか? | ||
|
||
| Q. NICTの「研究成果展開支援制度」を利用して改良を行ったと聞きました。 | ||
| 本発明をアスベスト問題に役立てるべく、装置の信頼性を高めて製品として実用化するために、平成17年に新設された「研究成果展開支援制度」に応募して研究対象に選定されました。この制度によってフィールド測定実験や較正作業を中心に行い、この部分については製造担当のエスコム株式会社に加えて、柴田科学株式会社に較正を担当してもらい、両社で協力して初期の試作品を実用品まで仕上げることになりました。NICTの技術をアスベスト問題に少しでも役立てたいと願っています。 | ||
| Q. 新たな夢、研究への意気込みなどもあればお聞かせください。 | ||
| 開発した装置は、空気中の繊維状粒子を検出するものです。アスベストを取り扱う作業場などでは、繊維状粒子はほぼアスベストとみなして良いのですが、一般大気中や建物内などでは、繊維状のものなどその他にも多くの粒子があって、その中にアスベストが混じっているという状態が普通であるためアスベスト粒子を識別することが課題です。アスベスト除去工事やアスベスト建材を使った建物などからのアスベスト粒子の飛散の監視など、その必要性が高まっています。繊維状PCM法でも同じ問題があり、アスベストを識別できる分散染色法や偏光顕微鏡法を用いる方法が検討されています。光散乱を用いるリアルタイムモニターでも、アスベスト粒子を識別できる方法の開発が求められており、この課題に挑戦していきたいと思います。 | ||
| 技術概要: ●発明者 廣本 宣久(ひろもと のりひさ) ●特許第2881731号 NICTが取得した特許は有償で利用することができます。これらの特許権の実施および技術情報については下記までお問合せください。 情報通信研究機構 研究推進部門 知財推進グループ TEL.042-327-7464 E-mail: ip@ml.nict.go.jp |