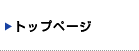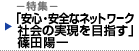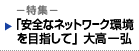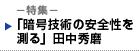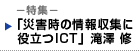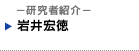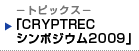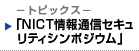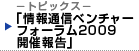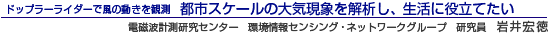
 都市部の風を観測し環境問題解決に役立てる
都市部の風を観測し環境問題解決に役立てる
「地面にドップラーライダーを設置し、都市スケールの大気現象、主に風の動きを観測しています」と語るのは、電磁波計測研究センター環境情報センシング・ネットワークグループの岩井研究員です。
ドップラーライダーとは、レーザーを照射して大気中のちり(エアロゾル)などの移動速度を計測し、風の動きを検知する装置です。ドップラーライダーは電波を利用するレーダーと異なり、ビルが密集している都市部の地表面近くでも観測ができます。また、都市部でのスケールの小さな大気現象を詳細に観測できるため、都市部の天気予報の精度向上や大気汚染・ヒートアイランドなどの環境問題解決に役立てられます。レーザーには、人間の目に入っても障害が起きないアイセーフの近赤外線レーザーが利用されています。
地道な観測から様々な成果が
岩井研究員は、観測技術と解析技術の研究を担当しており、これまでにも様々な観測実験と観測結果を解析してきました。山形県では農作物に被害を与える「清川だし」と呼ばれる特徴的な強風の発生メカニズムを突き止めるために観測を行い、発生源周辺の3次元的な風の動きを計測しました。また、本部(小金井)での観測結果から、東京上空に飛来した黄砂の空間分布と流れの可視化にも成功しています。
2台のドップラーライダーを使用した仙台空港での観測では、海から吹く風が水平ロール渦と呼ばれる渦を発生させていることを明らかにしました。「2台のドップラーライダーで観測することによって、1台では把握できない、風の流れを三次元的に、かつ詳細にとらえることができました」(岩井研究員)。ドップラーライダーは、機器そのものが高価で日本に数台しかない上に、移動が簡単ではないため、複数台を使用した観測は世界でも数例しか行われていません。
「将来はドップラーライダーのネットワークを設置して、ビル風やゲリラ豪雨、大気汚染など、都市部特有の大気現象や気象現象を観測したい」と語る岩井研究員は、大学在学中は宇宙プラズマに関する研究を行っており、NICTにおいても4年間宇宙天気予報に関する研究に従事してきました。「気象学については3年前の異動後から取り組み始めたばかり」とのことですが、「現場に行ってデータを取ることは自分に合っている」と、気象研究の楽しさも語ってくれました。
Profile
 岩井 宏徳(いわい ひろのり)
岩井 宏徳(いわい ひろのり)
電磁波計測研究センター 環境情報センシング・ネットワークグループ 研究員
大学院修了後、2001年通信総合研究所(現NICT)に入所。宇宙天気予報に関する研究に従事し、現在は主にドップラーライダーに関する研究に従事。