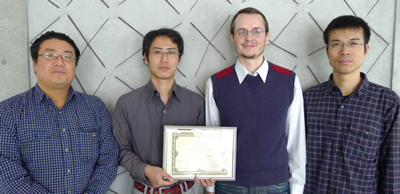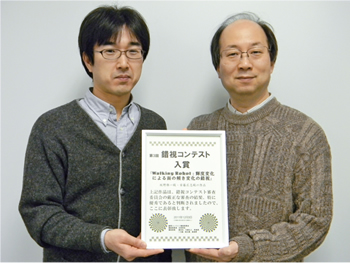| 受賞者 Mohammad Azizur Rahman(アジイズル ラハマン) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
◎受賞のコメント: IEEE Standard.802.22-2011への貢献が評価され、IEEE Standards Associationから感謝状をいただき大変うれしく思っています。私は2009年7月からIEEE 802.22 ワーキンググループで活動してきました。私はセンシング技術に貢献し、システム概念の知的財産を開発しました。現在もこのワーキンググループの中の1つのスタディグループの座長をしています。この受賞をきっかけに、さらに仕事に励みたいと思います。 |
|||||||||
| 受賞者 Eloy Gonzales(エロイ ゴンザレス) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
 |
||||||||
◎受賞のコメント: 今回受賞できたことは、大規模データの利活用に関してさらに研究する大きなモチベーションになります。この研究では、生物学にヒントを得た進化的メカニズムの概念が、特に異種データベースからの知識発見プロセスを改善するために適用されます。この研究を行うにあたり、ご指導とご支援をいただいた皆様に感謝します。 今後は、社会に役立つ情報技術の発展に貢献し、ディジタルデバイドの低減に寄与していきたいと思います。 |
|||||||||
| 受賞者 寳迫 巌(ほうさこ いわお) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
◎受賞のコメント: 委託研究「ICTによる安心安全を実現するためのテラヘルツ技術の研究開発」に於けるイメージャチーム: NECおよび東京大学(アレイセンサ)とNICT自主研究(光源)が連携し、応用範囲が広い技術を実現することが出来ましたことは、皆さんの技術の高さとチームワークの御陰であり、各機関を代表しての受賞です。 |
|||||||||||
| 受賞者 寳迫 巌(ほうさこ いわお) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
 |
||||||||||
◎受賞のコメント: アイデアと基本的技術の実現性検証を自ら実施した後に、より良い技術を持つ外部研究者との協力関係を築くことが出来たことが、今回の受賞につながりました。検出器開発としてはまだ途中ですが、それにも関わらずご評価をいただけましたことは望外の喜びです。 |
|||||||||||
| 受賞者 金 京淑(きむ きょんすく) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
◎受賞のコメント: ソーシャルメディアから実世界で起きている様々な事象とその変化を発見するために必要な時空間情報の収集・分析技術が評価され受賞しました。本デモ論文では、時空間付きTwitterメッセージから東日本大震災に関して時空間によりトピックの変化(動き)を網羅性高く見せています。本受賞を励みに、今後は大量にネットワーク上を流れている多種多様な時空間情報をより早く処理する基盤技術について研究開発を進めたいと思います。最後に、ご支援いただい皆様に深く感謝申し上げます。 |
|||||||||
| 受賞者 宮地 利幸(みやち としゆき) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
◎受賞のコメント: ネットワーク実験において、実験対象の技術以外で起こった障害により、実験対象技術がどのような影響を受けるかという検証はこれまであまり行われてきませんでした。本研究ではこのような検証を可能とするフレームワークの提案を行い、StarBED上でいくつかの例を実施したことを高く評価していただきました。このような実験は自然災害などによるネットワーク障害が発生した際に、ネットワーク全体にどのような影響があるのかなどを検証するために重要なものとして認識しています。この後は、より容易に本フレームワークを利用した実験が行えるよう研究を進めていきます。 |
|||||||||||
| 受賞者 山田 俊樹(やまだ としき) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
 |
||||||||
◎受賞のコメント: 薄膜全般に関する国際会議において、発表を行ったセッションでは様々な有機薄膜、バイオ薄膜の分析技術が発表されていました。私は薄膜中の単一蛍光体からの蛍光を、周囲環境(高真空、窒素下など)を制御しながら、高い分解能で、明るく顕微計測を行う技術とそれを用いた研究成果について発表を行いました。本研究は様々な顕微分光計測への応用が可能であり、今後、ナノ・バイオ分野での幅広い応用を期待しています。 |
|||||||||
| 受賞者 坂野 雄一(さかの ゆういち) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
◎受賞のコメント: 臨場感を生み出す人の視覚のメカニズムを解明する研究のための視覚刺激を作成しているときに、新たな錯視を発見し、今回の受賞に至りました。今後は、錯視のような、人間の視覚メカニズムが持つ特性までも利用した臨場感生成法やその評価手法などを提案できたらと思っています。これまでの研究にご支援、ご協力頂きました多感覚・評価研究室の皆様他、関係各位に深く感謝申し上げます。 |
|||||||||