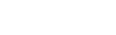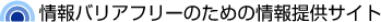ICTリハビリテーション研究会とはどのような団体ですか?
林:ICTリハビリテーション研究会は、リハビリテーションの場にICT(情報通信技術)活用を促進している団体です。2017年の発足当初、作業療法士や理学療法士がICTを活用して、リハビリテーションや支援サービスの質を向上することを目指していました。その後、活動の幅を広げる中で、3Dプリンターの活用に注目するようになりました。それというのも、作業療法士が自助具を3Dプリンターで製作することで、その自助具に関するデータの保存や再現性の向上、品質の改善が期待できると考えたからです。
自助具とは、障害や身体的制約のある人が使う道具を指します。例えば、握力が弱い人のための特殊なスプーンやフォーク、衣類や靴下を着脱しやすくするためのフックなどです。市販されている自助具もありますが、使う人によってフィットする形やサイズが異なります。例えば、同じ握力補助のスプーンであっても、手の大きさや動かせる範囲に合わせて調整を必要とすることが多く、既製品では上手く使えないことがあります。そのため、支援の現場で、作業療法士が利用者に合わせて加工したり、テープで補強したりとカスタマイズすることがよくあります。作業療法士が経験をもとに細かな調整や改良を加えながら、最適な自助具を提供するケースが多いのですが、どうしても労力と時間がかかってしまいます。
このような課題の解決策として、一人ひとりの特性に合わせて自助具を製作できる3Dプリンターが有用であると考えました。また、3Dプリンターを利用することにより、作業療法士や支援者が利用者の身体状況や生活環境に応じた自助具を迅速に製作できるだけでなく、そのデザインデータを保存し、他の利用者とも共有することが可能になります。そこで、現在は3Dプリンターを活用できる作業療法士や当事者を増やすことに注力しています。