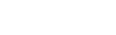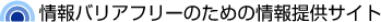山本さんは、パラスポーツを通じて共生社会の大切さを伝えるDE&I教育・研修プログラム「あすチャレ!」の企画や運営を担当されています。2020年のコロナ禍をきっかけにオンライン授業を開始されたとのことですが、対面形式ではなくオンラインを選択することで、新たな可能性が見えたのでしょうか?
私が担当している「あすチャレ!」は、パラスポーツを通じて共生社会の大切さを伝える教育・研修プログラムを、子どもから大人まで幅広い層に提供しています。2016年に始まり、2024年9月末までで開催5,000回、参加人数は50万人を超えています。
当初、対面形式で「あすチャレ!」のプログラムを行っていましたが、2020年のコロナ禍をきっかけに、オンライン授業を導入しました。コロナ禍で多くの学校行事が中止となり、子どもたちが「できないこと」ばかりに目を向けてしまう状況を危惧したことでした。そこで、「今の状況でもできること」を伝えたい、子どもたちの学びを止めたくないという思いから、オンラインでプログラムの提供を始めたんです。
当時は、まだ学校にWi-Fi環境やタブレット端末が十分に整備されていませんでした。そこで私たちは、レンタル会社から機材を借り上げ、学校にお貸し出しする形でオンライン授業をサポートしました。
初めての試みで試行錯誤の連続でしたが、目指したものは「対面でもオンラインでも変わらない体験、かつ双方向のコミュニケーション」です。子どもたちがただ聞いているだけでなく、積極的に参加し、質問できるような双方向のやり取りを大切にしました。

授業の内容について教えてください。
例えば、小学校で実施したオンライン授業は45分間で、その限られた時間の中で、子どもたちに「できるできないではなく、どうやったらできるか」という工夫の大切さを伝えています。
例えば、「私は、車椅子を使うことで、みんなと同じようにできないことや不便なことがあります。でも、工夫次第でできることもたくさんあるんだよ」と伝え、不便や制約を乗り越えるための創意工夫を共有することで生まれる共感の大切さを、子どもたちに考えてもらうようにしています。
また、映像にしてパラスポーツのルールやパラアスリートの工夫を見せることで、子どもたちの「できない」という思い込みを解きほぐし、「できる」可能性を広げていきます。
さらに、オンラインならではの工夫として、チャット機能を活用し、子どもたち全員が自由に意見や質問を書き込めるようにしました。これにより、対面授業では発言しづらかった子どもたちも、積極的に参加できるようになりました。
対面とオンラインの違いはありますか?
オンラインと対面、どちらの形式でも、子どもたちに「同じように」伝えられるよう、様々な工夫をしています。
オンライン授業では、画面越しでも子どもたちとつながりを感じられるよう、表情や声のトーン、カメラワークなどを意識しています。そして、資料をただ画面共有するのではなく、あえてパネルを手に持って見せながら説明したり、ジェスチャーを交えたりすることで、子どもたちが興味関心を持ち、授業に引きつけ、飽きさせない工夫をしています。
また、2台のカメラを使い、全身と表情を同時に映すことで、より臨場感のある授業を実現しています。