 |
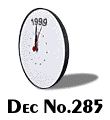 |
 |
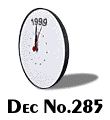 |
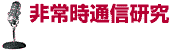
|
||||||||||
| 大野 浩之 | ||||||||||
|
はじめに 1995年1月の阪神大震災の際、既存のテレビ、ラジオや新聞は被災者への情報提供を積極的に行った。しかし、被災地の内外で多くの人々が「自分の肉親や知人が今どこにいてどうしているか」といった情報や「被災地域内の避難所がどのような支援物資を必要としているか」といった情報の提供が十分ではなかったと感じたという。インターネットは、この問題を解決できるだろうか。 |
||||||||||
|
非常時通信システムの開発 被災後、電話回線が復旧しインターネットアクセスが可能になると、主に電子メールを利用した情報交換が始まった。しかし、メーリングリストを作る程度のことは行われたものの、被災者情報交換システムと呼び得るようなシステムは現れなかった。そのためインターネット技術を活用した「被災者支援情報交換システム」の必要性を多くの人が感じた。著者が参加しているWIDEプロジェクト(インターネット研究を推進する世界でも有数の研究グループの1つ、代表:村井 純慶應義塾大学教授)も例外ではなく「非常時にインターネット技術を駆使して問題解決を図るシステム」を研究開発すべくLifeline WG(ライフライン・ワーキンググループ)を発足させた。同WGの現時点での成果が本稿で述べるIAAシステムである。IAAは、「私は生きているぞ!」を意味する“I am alive”の頭文字を取って名付けられた。このシステムは、東京大学、東京工業大学、北陸先端科学技術大学院大学などの大学や民間企業の研究者が研究開発を推進してきたが、本年7月からはこれに本所通信システム部非常時通信研究室が加わり、研究開発において中心的な役割を担いつつある。なお、非常時通信研究室は、本年7月に室長以下室員全員の構成を一新して新たなスタートを切っており、IAAシステムの研究成果を礎に、災害時にその能力をいかんなく発揮する新しい情報通信システム(非常時通信システム)の研究開発を行っている。 |
||||||||||
IAAシステム と運用実験
現時点でのIAAシステムの概要を図1に示す。IAAシステムは、個々の利用者がインターネットに接続して利用するユーザインタフェース部(主に図の上半分に示される)と、被災者情報を格納する分散データベース(図の下半分に示される)から構成されている。
上記以外にも、電子手帳(PDA)や、Compact HTMLブラウザ機能を有する携帯電話を使った被災者情報登録システムの開発も行っている。 分散データベース部分
分散データベースサーバは、データベースプログラムと、サーバ間でデータの同期を行うデータ同期機構からなり、これらによって被災者情報はインターネット上の複数箇所で分散管理され、検索は分散サーバのいずれか1台の上で実施される。分散データベースサーバをどのように実装するかは、難しく興味深い問題であるが、現在の実装では情報の登録や同期には既存のネットワークニュース配送システム(innシステム)の改造版を利用している。また、ユーザインタフェース部分から送られてくる情報や、分散データベース間で相互にやりとりされる同期のために必要な情報は全て暗号化するなどセキュリティ面には十分配慮している。
IAAシステムの配布
今後の展開 (通信システム部非常時通信研究室長) |
||||||||||
 |
||||||||||
|
||||||||||
 安全で安心な電波利用のために 安全で安心な電波利用のために 独立行政法人個別法案について 独立行政法人個別法案について ETS-VII実験終了レポート ETS-VII実験終了レポート
 通信総合研究所50年史の編纂 通信総合研究所50年史の編纂 |