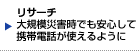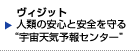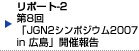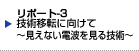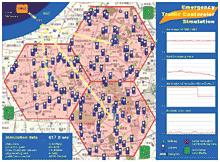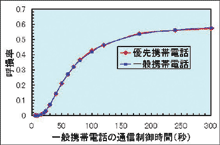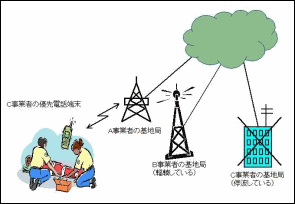| 新時代のネットワーク制御技術 | ||||
| 地震などの大規模災害時には、親戚や友人などの安否確認のため、通信需要が急増し、特に携帯電話ネットワークは混雑し、掛かりにくくなる輻輳(ふくそう)状態となります。例えば、2004年10月23日の新潟県中越地震では、ある携帯電話事業者のネットワークで、地震発生直後から約6時間、全国から新潟県内及び東北管内あての通話が通常時の約45倍も殺到し、輻輳状態になりました。輻輳の問題は、大規模災害時だけでなく、お正月など大きなイベントの時にも起こり、身近な問題でもあります。また、大規模災害時には、このような輻輳の問題だけでなく、携帯電話とネットワークを結ぶ無線基地局が、伝送路断や停電の長期化のために、停波して機能しなくなるという問題も起こります。実際に、新潟県中越地震では、ある携帯電話事業者のネットワークで、合計91局の基地局が停波し、通信できない状況が発生しました。 携帯電話は、本人が、どこでも直接、情報を発信したり受信することができるため、災害時の通信手段として大変有効です。このため、NICTでは大規模災害時でも携帯電話を安心して使えるための様々なネットワーク制御基盤技術の研究に取り組んでいます。ここでは、その取り組みについて紹介します。 |
||||
| 通信時間制御による通信機会の確保 | ||||
| 現在、災害時などの輻輳時には、重要通信確保や通信システムを守るために、あらかじめ登録されている優先携帯電話以外の発信を制御する方式が取られています。このため、多くの一般の携帯電話は、使用できなくなります。これに対し、発信を制御するのではなく、通信時間を制御し、時間は短いながらも多くの通信機会の確保を実現しようという通信時間制御方式を提案しています。具体的には、どのくらいの通信需要の時に、どのくらいまで制御すればよいのかといった計算式の導出、理論解析や計算機シミュレーション(図1)による諸特性評価などを行っています。 重要通信確保の必要性から、優先携帯電話の通信は何も制御せずに、一般の携帯電話の通信時間だけを制御した場合の計算機シミュレーション結果を図2に示します。横軸が一般の携帯電話の通信制御時間で、縦軸が“呼損率”といって掛かりにくさを表しています。通信需要のほとんどを占める一般の携帯電話の通信制御時間が短くなると、優先携帯電話と一般の携帯電話の呼損率が共に低くなり、重要通信の確保とともに、一般の通信も時間が短いながらも実現が可能になることが分かります。 様々な状況における特性評価等を行い、本制御の適応範囲等の検討を進めているほか、今後、普及が予想される、音声をインターネット技術により伝送する携帯IP電話ネットワークでの制御法の検討にも取り組んでいます。 |
||||
| 非常時マルチシステムアクセス | ||||
そこで、NICTでは図3のように、普段接続している事業者の基地局にアクセスできない場合、他の事業者の基地局にアクセスして通信できるようにする非常時マルチシステムアクセスを提案しています。こうすることにより、災害の被害を軽減したり、人命にかかわる重要通信を信頼性高く確保することができると考えています。 現在は事業者の枠を超えた全体の効率を考えたネットワーク制御技術に関する研究に取り組んでいますが、任意の優先携帯電話の高速認証技術や、ソフトウェアのダウンロードなどによる様々な無線方式を利用し、基地局へのアクセスを可能とする携帯電話端末の開発などに向けた研究開発も行っていく予定です。 |
||||
| 公的研究機関としての使命 | ||||
|
||||
|
||||
| 暮らしと技術 Q:通信時間制御では、途中で会話が切られてしまい不便なのでは? A:確かに、この制御では制限時間になると強制的に切断されてしまいます。言い足りないことが多いと、また、掛け直すことになり、さらに、混雑してしまいます。そこで、接続時には、制限時間をディスプレイ表示、制限時間近くになった時には、端末のバイブレーションや警告音を鳴らすことで、会話を手短にしてもらうよう誘導することも同時に提案しています。 |
||||
[重要通信の確保(Establishment
of Telecommunication)]
|
 |
 |