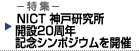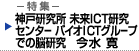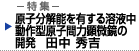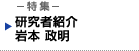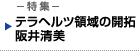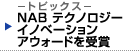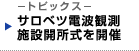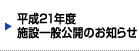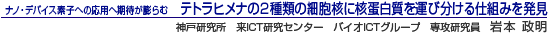
 NICTで開花させた
NICTで開花させた
大学時代からのアイデア
神戸研究所未来ICT研究センターの一翼を担っているバイオICTグループでの最新成果として、繊毛虫テトラヒメナの2種類の細胞核(大核と小核)に核蛋白質を運び分ける仕組みの発見が注目されています。岩本政明専攻研究員は、画期的な発見に携わった研究者の一人です。
「テトラヒメナが2種類の細胞核を持つ変わった生物だということは古くからわかっていました。ふだんは大核の方からだけ遺伝情報を取り出して使い、いざ、次世代の子孫をつくるときに、小核の情報を子孫に渡して、生活で使っていた方の情報は破棄するのです。ただ、その機能制御、メカニズムがどうなっているのか、誰もが不思議に思っていたのです」
この発見につながるアイデアを岩本専攻研究員はずっと持ち続けていましたが、NICTの充実した施設が使えるようになって、ようやく研究が実現しました。具体的に使った技術は、去年ノーベル化学賞を受賞した下村脩博士の、緑色蛍光蛋白質を用いた標的蛋白質の可視化だそうです。
「蛋白質に緑の標識をつけることで、細胞の中のどこにその蛋白質が位置するのかがわかるのですが、テトラヒメナではやや難しい面があったのです。それを自由に使いこなせるようになり、核内のいろんな蛋白質に緑色を発現させて違いを探り、局在を調べたのです」
文章からは読み取れない“コツ”
しかし、報告されている方法で蛍光蛋白質を扱ってもなかなか光ってくれず、1種類目の蛋白質を光らせるまでに、1年近くかかったといいます。ネックを打開したのは、論文の文章からだけでは判らない“コツ”のようなもの。口で説明するのが難しいこのコツは、特に生物学研究ではすごく大事だと感じているそうです。
細胞質と核内をつなぐ核膜孔を構成する蛋白質Nup98には、大核専用と小核専用が存在することを発見して、論文に投稿したのが1年ほど前。改編作業を経て、採択率約20%という Current Biology誌の5月号に掲載されました(電子版は4月)。
「今回我々は、核の入口つまり通路にある蛋白質の違いを見つけたのですが、この蛋白質をナノ・デバイスの素子に使うことで、セレクティブなフィルターを作れないかなど、今回の発見が未来の情報通信システムに応用可能な新たな構造基盤の創出につながればと思っています。」と、夢を膨らませます。
Profile
 岩本 政明(いわもと まさあき)
岩本 政明(いわもと まさあき)神戸研究所 来ICT研究センター バイオICTグループ 専攻研究員
大学院修了後、ハワイ大学博士研究員、科学技術振興機構CREST特別研究員を経て、2007年情報通信研究機構に入所。細胞内遺伝情報の制御機構の解明と、情報通信技術開発への応用に向けた研究に従事。 博士(理学)。