 |
 新世代ネットワーク研究センター 量子ICTグループ 元主任研究員 武岡 正裕 NICTは情報処理推進機構(IPA)および産業技術総合研究所(AIST)との共催により「量子暗号・量子通信国際会議Updating Quantum Cryptography and Communication(UQCC) 2010」を開催しました。
UQCC2010は2007年と2008年に行われた量子暗号国際会議(UQC)に量子通信分野を加え発展させた会議です。実利用が始まった量子暗号や量子通信の新潮流を研究者のみならず、省庁・民間企業関係者にも分かりやすく紹介し、今後の課題や分野連携戦略を議論することを目的としています。会議初日の午前のセッションでは、NICTと委託先企業(日本電気株式会社、三菱電機株式会社、日本電信電話株式会社)が協力して光テストベッドJGN2plus(小金井-大手町-白山)上に構築した量子鍵配送ネットワーク(Tokyo QKD Network)を用いて世界初となる都市圏敷設環境(45km)での動画の完全秘匿通信(量子鍵配送により共有した鍵によるワンタイムパッド暗号化)のライブデモンストレーションに成功し感嘆の声があがりました。この実証デモンストレーションには、東芝欧州研究所などEUの5つの機関も優れた技術を持ち込み協力しています。同日午後のセッションでは特別講演と2件の基調講演が行われ、最初の特別講演において慶應義塾大学青山友紀教授(NICTプログラムコーディネータ)から新世代ネットワークのビジョンが紹介されました。続く基調講演ではRSA暗号の発明者の一人であるワイツマン科学研究所のシャミア教授より量子暗号技術の現状分析と今後の課題が提示され、ジュネーブ大学ジザン教授により量子暗号の現状と今後の方向性についての講演が行われました。フォトニックネットワークと現代暗号の専門家との白熱した議論から量子暗号の発展のための主たる課題として以下の3点が指摘されました。 1. 単なる性能改善のみならずシステムの簡素化、安定動作化に向けた開発が極めて重要 2. 暗号システムの安全性を高めるためには装置そのものの安全性だけではなく周辺環境(サイドチャネル攻撃)を考慮したシステム設計が必要 3. ネットワーク上で活用するためには装置間インターフェースの標準化が急務 これらの指摘に対し、委託先企業が開発してきた量子鍵配送装置と量子ネットワーク管理技術は、都市圏敷設ファイバを通した安定動作、TV会議システムとの融合と完全秘匿TV会議の実施、欧州参加機関の装置との相互接続をライブデモンストレーションにおいて実証し、高い性能と先見性を示すことが出来ました。なお日本電気株式会社と日本電信電話株式会社の量子鍵配送装置の単一光子検出器には、NICTが開発した超伝導単一光子検出器が使用され、高い性能と安定動作を有することが実証されました。今後の量子暗号の開発について会議内で指摘された標準化のみならず、装置の高度化及びネットワーク展開に向け、総務省とNICTによる更なる牽引への期待が国内外の関係者より寄せられました。 この会議開催とその後の成果紹介に関しては、多くの省庁関係者、スポンサー企業の方々に多大なご支援、ご協力を賜りました。  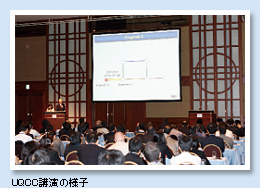   |
||||||||||