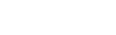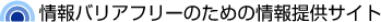「NTTクラルティ」が「ウェブサイトのアクセシビリティ診断」サービスを始められたきっかけと、近年におけるアクセシビリティの重要性について教えてください。
田中:当社が設立されたのは2004年7月1日で、ちょうど日本工業規格(現:日本産業規格)、いわゆるJIS規格( JIS X8341-3-2004)が制定された年でもあります。当時、初代社長が事業の方向性を検討していた際、就職活動中の視覚障がい者の方から「ウェブアクセシビリティ」という考え方を知ったことがサービスをスタートするきっかけでした。
当社の親会社であるNTT株式会社(当時は日本電信電話株式会社)は情報通信企業ですので、「ウェブを通じて障がい者にも情報を届けることはグループとしての使命だ」という想いから、アクセシビリティ事業を象徴的な取り組みとしてスタートさせたと聞いています。私自身も事業開始と同時に入社し、約20年間当社の歴史とともに歩んできました。サービス開始当時は、まだパソコンでインターネットを利用して情報収集するのが一般的でしたが、この20年で状況は大きく変わりました。ウェブサービスに加え、ネット通販、SNS、動画配信サービスなど、多種多様なコンテンツが登場し、今では日常生活に欠かせない存在となっています。
一方で、これらの便利なサービスを「利用できない人」がいるのも事実です。私自身を含め、視覚障がいや聴覚障がい、その他の障がいのある方々にとって、アクセシビリティが確保されていなければ、その利便性を享受できません。だからこそ、ウェブにおけるアクセシビリティの向上は非常に重要だと感じています。本来、情報発信者やサービス提供者は、障がい者や高齢者も含め「誰にとっても使えること」を大前提として配慮すべきです。「アクセシビリティ」と聞くと特別な取り組みに思われがちですが、実際は“サービスをより多くの人に使ってもらうための基本”であると考えています。近年ようやくその意識は高まりつつありますが、まだまだ十分とはいえません。今では多くの方がスマートフォンを持ち、日々の生活に欠かせないツールとなっています。
ウェブサービスの先には必ず「利用者」がいる。その人たちがきちんと使えるかどうかを念頭においてサービスを提供することが何よりも大切です。シンプルに言えば、“誰もが情報にアクセスできること”。企業ごとにアプローチは異なっても、その一点を大切にしてサイトを構築していただきたいと思っています。