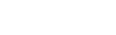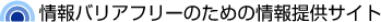現在、スマートフォンでウェブサイトを閲覧する方が多い中、パソコンとは異なる課題もあると思います。どのような点に注意が必要でしょうか。
田中:2024年4月に障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が改正され、前年の2023年には新しい国際的なアクセシビリティガイドラインである「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)」が示されました。
最新版は「WCAG 2.2」で、障がいのある方や高齢の方を含むすべての人が、ウェブサイトから平等に情報を得られるための方法がまとめられています。その中で大きなポイントとなっているのが、「スマートフォンのタッチ操作に関する対応」の項目です。今回の改正により、法律上の合理的配慮の提供が一般事業者にも義務化されました。つまり、ウェブサービスでアクセシビリティに配慮が不足している場合、事業者は代替手段を提供しなければならなくなったのです。
法改正のたびに部分的に対応するよりも、最初からバリアフリーを前提にしたサイトを構築しておくことが望ましい、という流れに変わりつつあります。当社でもNTTグループからの問い合わせはもちろん多いのですが、それ以外の事業者からのお問い合わせも着実に増えていると感じます。スマートフォンは今や生活の中心にある欠かせないツールです。「WCAG」が「スマートフォンでの閲覧を前提とした配慮」を求めているのは、まさに時代の流れに沿ったものだと思います。例えば、これまで「検索」「送信」「登録」といったアイコンの大きさについて明確な規定はありませんでした。しかし、新しい基準では一定の大きさの確保や、サイズが小さくてもアイコン同士の間隔を十分に空けることが求められるようになりました。このように、スマートフォン特有の操作性を踏まえたルールが新たに定義されており、「WCAG」自体が、より「モバイル視点」で設計されていると感じます。とはいえ、スマートフォンは基本的にタッチ操作を前提としています。そのため、手が不自由な方や、私たち視覚障がい者にとって操作が難しい場面も少なくありません。中にはキーボードを接続して操作するユーザーもいますが、現状はそこまで配慮が行き届いていない印象です。もちろん、スマートフォンというデバイスの特性上、タッチ操作が中心になるのは仕方のないことです。しかし、それでもキーボード操作などを必要とするユーザーにまで目を向けたガイドラインが設定されれば、さらにアクセシビリティは一層向上するのではないかと感じています。
アクセシビリティ診断で見受けられる共通の課題やミスには、どのような傾向がありますか。
田中:大きく分けて2つあります。
1つ目は「コントラストの問題」です。企業にはコーポレートカラーがあり、その色味をウェブサイトに反映させる傾向があります。しかし、コーポレートカラーをそのまま使うと、コントラストが弱くなり、視認性が低下してしまうケースが多いのです。実際に診断を行うと「コーポレートカラーなので変更できない」と言われることもあります。その結果、修正が難しくなるケースも少なくありません。こうした状況を避けるためには、サイトの設計段階からアクセシビリティを意識し、コーポレートカラーをそのまま使用するかを含めて検討を行い、十分なコントラストを確保した色合いやデザインを選ぶことが重要だと考えています。
2つ目は「動画コンテンツに対する配慮不足」です。近年、企業がウェブサイト上で動画を活用することが増えていますが、字幕や代替情報が不足しているケースが目立ちます。例えば、動画のセリフに字幕がなければ聴覚障がい者には内容が伝わりません。また、CMなどでテロップが表示されていても、BGMや効果音が情報の一部を担っている場合、それが聴覚障がい者に伝わらないままになってしまいます。“イメージ重視”で情報を伝えてしまうと、一部の人にしか届かない情報になりかねません。動画に限らず、すべての人にきちんと情報が伝わるような工夫が求められていると感じています。