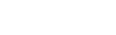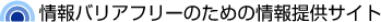ウェブ上では「技術だけでは見えにくいバリア」も存在していると思います。これらに対し、どのように診断されていますか。診断時の工夫があれば教えてください。
田中:ウェブのソースコードのチェックのような技術的な確認や、アクセシビリティチェックツールだけでは見つけられない課題が多いと感じています。ウェブの技術は日々進化しており、読み上げソフトなどの支援ツールが対応していないことがあるからです。
私自身、目が見えなくなって20年以上経ちますが、診断をしていると「画面上では便利そうに見えるものの、実際には使いづらい」ケースによく出会います。たとえば、動画の埋め込みやモーダルウィンドウ画面の操作です。あるボタンを押すと新しい画面が表示され、入力後に閉じると元の画面に戻る——こうした挙動は裏側でどのような仕組みになっているのかが分かりにくく、読み上げソフトも追従できていないケースがあります。エンジニアが「こう動くはず」と設計しても、実際に利用すると想定通りに動作しないこともあります。
見えている人なら画面を見ながら直感的に理解できますが、視覚障がい者の場合は読み上げ機能の順序が乱れたり、情報が正しく伝わらなかったりして操作が難しくなります。だからこそ、ツール診断に加えて、私たちのような障がいのある当事者が実際にチェックすることがとても大切だと思っています。技術的な正しさだけではなく、「実際にユーザーに伝わるかどうか」を確認することが当社の診断の特徴であり、重要な役割だと考えています。
「NTTクラルティ」では、田中さんの周囲にも障がいのある方が勤務されていると思います。診断に迷った際に相談される場面もあると思いますが、どのようにアドバイスされていますか。
田中:最近はメンバーに任せることが多いので、基本的には各自で判断してもらっています。ただし、どうしても迷ったときには「まずはガイドラインに立ち返って、どう書かれているかを確認しましょう」と伝えています。そのうえで、「この判断で良いのでは?」と補足する形ですね。
とはいえ、技術の進歩はガイドラインの更新よりも早いので、記載されていないことが実装されているケースも少なくありません。その場合は、どう判断すべきか悩むこともあります。お客様の考えもあるため、「これはロゴなので変更できません」といったご要望もあれば、逆にたとえご要望があっても、「ダメなものはダメ」と判断しなくてはならない場面もあります。診断は一応「誰がやっても同じ結果になるもの」とされていますが、実際にはグレーゾーンも多いのです。したがって、そのような場面ではメンバー同士で意見を出し合い、会話を重ねて「この判断で行こう」と目線を合わせるようにしています。チームで仕事をしている以上、判断のすり合わせはとても大切です。多少の認識の違いはあっても、可能な限り共通の基準を持てるよう意識しています。
今はインターネットが普及し、さまざまな人が情報にアクセスできる時代です。単に「ガイドラインに沿って診断すること」が目的ではなく、「情報をきちんと届けるためにガイドラインがある」という視点を忘れずに診断していくことが重要だと、私は考えています。