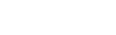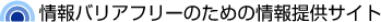さらなるアクセシビリティ向上のために、未来を見据えた「あるべき姿」とは、どのようなものだとお考えですか。
田中:やはり、アクセシビリティを意識したサイト設計が“当たり前”になることだと思います。極端に言えば、診断をしても「問題ありませんでした」となるような世の中が理想ですね。
認知は広がりつつありますが、「アクセシビリティは必要」という意識がまだ十分に浸透していないのが現状です。例えば、ウェブデザインを学ぶ人たちが必ずアクセシビリティを学び、それを前提に設計するようになれば大きな変化が生まれるのではないでしょうか。昨今よく耳にする「UX(ユーザーエクスペリエンス)」の前に、まずは「情報がきちんと伝わっているか」を問いかけたいですね。
ウェブサイト以外でもアクセシビリティは重要です。今は銀行や飲食店、スーパーなどでもタッチパネル操作が主流になっています。しかし、私たち視覚障がい者にとって、タブレットを自分で操作できる場面はまだまだ少ない。結局、店員さんを呼んで代わりに操作してもらわなくてはならず、結果的に「手間のかかるお客さん」となっていると感じ、私はそのような店舗の利用を避けることもあります。それは店舗としては、知らず知らずのうちにお客さんが離れていくことにつながっているのです。
本来なら、アプリ開発も含めて障がい者や高齢者にも使いやすいように設計されていることが、真の意味でのアクセシビリティの向上だと思います。先進的な取り組みは素晴らしいですが、まだまだバリアフリーの配慮が欠けている場面も多い。だからこそ、設計段階からマイノリティにも目を向けた開発が不可欠です。私自身も診断や講演を通じて、その向上の一助になれるよう、これからも努めていきたいと考えています。
取材協力:NTTクラルティ株式会社
取材日:2025年8月