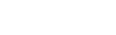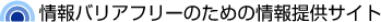「COCRE HUB」に関わる人たちやデータ作成のプロセスの全体像を教えてください。
林:「COCRE HUB」は、様々な人の協力で成り立っています。まず、自助具の設計にデザインや構造の知識が必要不可欠で、3Dプリンターにおける形づくりを「モデリング」と呼びます。デザインを考えたり、図面を描いたりする「設計担当者」が欠かせません。
ICTリハビリテーション研究会は、自助具のデザインを公募する「3Dプリント自助具デザインコンテスト」を毎年開催しており、幅広い人達が参加されています。ここでモデリングの事例を集めています。
例えば、デザインを学ぶ大学生や工業に関する授業を受けている高校生は、3Dプリンターを用いて社会課題解決に取り組む学習の一環として、コンテストを活用するケースが増えています。
また、作業療法士やデザイン会社の方、障害のある当事者の参加も多いです。作業療法士は支援の現場で培った経験をもとに、使いやすく実用的なデザインを追求してくれます。デザイン会社の方はプロとして、見た目や機能性を考慮したアイデアを提案してくれますし、障害のある当事者は実際に使用する際の感覚や利便性に基づいた意見を出してくれます。
さらに、コンテストを通じて生まれたデザインのうち、有用性が高いと判断したものを「COCRE HUB」に掲載します。このように「COCRE HUB」とデザインコンテストが互いに補完し合うことで、全国に自助具が普及し、障害者支援が広がっています。「COCRE HUB」は単なるデータ共有の場ではなく、支援者同士が知見や技術を共有し合う「共創の場」として機能しているのです。

濱中:通信やネットワークは、この取り組みに欠かせない基盤です。もともと、3Dプリンターを使ったものづくりやデジタル工作のオープンな市民工房ネットワーク、いわゆる「ファブラボ」という活動は、アメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)の授業から生まれたものなんですね。ファブラボは「デジタル市民工房のネットワーク」として定義されていて、離れた場所でも同じデータがあれば同じ製品を作れることを目指しています。
この「データを移動させる」仕組みが重要です。通信ネットワークを通じてデータを共有し、離れた場所でも同じように自助具を作れるようになることで、「必要な人が、必要な場所で、必要な数を自分で作る」という理想のものづくりが実現します。そうした理想の実現に向けて、私たちは販売を前提とせず、データや作る場所を提供するという形で取り組んでいます。