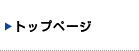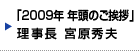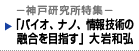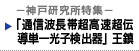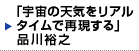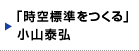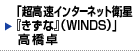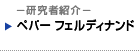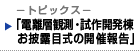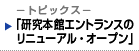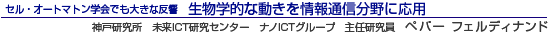
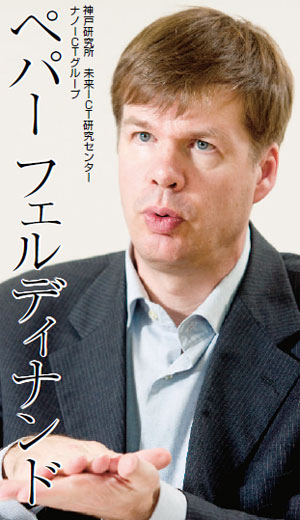 生物が持つシステムの情報通信への応用を目指す
生物が持つシステムの情報通信への応用を目指す
「生物からいろいろなことを学べます」と語るのは、ペパー主任研究員。ナノテクノロジーやバイオテクノロジーなど新しい技術を利用したコンピュータと通信のアーキテクチャ構築を目的とした研究に携わっています。
ペパー主任研究員はオランダ、デルフト大学でコンピューターサイエンスを学んだ後、1990年にSTAフェローとして来日、1993年にNICTの正規研究員として採用されました。コンピューターの並列分散処理やパターン認識といった研究を経て、1990年ころから現在のナノ、バイオを利用した研究を手がけています。
ペパー主任研究員は、分子の相互作用を利用し、これまでよりも優れたアーキテクチャを構築することを目指していますが、これを実現するためには生物が持つシステムがヒントになるのではないかと考えました。「生物の分子的メカニズムは、ナノテクノロジーと似たような特徴があるからです。そこで、なぜ生物の活動は効率が良いのかに着目しました」。そして、生体内での分子のブラウン運動が、結合できる相手を探す探索のプロセスだということに気づいたのです。
ブラウン運動を取り入れるアイデアに大きな反響
ブラウン運動とは、非常に微少な粒子が不規則に動くことをいいます。このブラウン運動を数学的な抽象モデル、デバイスモデル、回路モデルに取り入れれば、より単純な回路ができることを見つけました。そして、セル・オートマトンにブラウン運動回路を実装するというアイデアを学会で発表しました。セル・オートマトンは、コンピューターのアルゴリズムなどをあらわす際に用いられる数理モデルの1つで、小さなセル(非常に単純な有限オートマトン)が時間とともに変化していきます。生物学的な動きを取り入れるという新しい考え方に大きな反響があり、その学会のベストペーパーアウォードを受けたのです。
「この考え方を推し進めて、情報通信、コミュニケーションの分野へ応用することを考えています。特に分散ネットワークにおいて、お互いの相互作用で統合的な行動を行う生物学的なシステムを応用できるかを研究したい」と、ペパー主任研究員は語っています。
Profile
 ペパー フェルディナンド
ペパー フェルディナンド
神戸研究所 未来ICT研究センター ナノICTグループ 主任研究員
デルフト工科大学大学院 理論コンピュータサイエンス課程修了後、STAフェローを経て、1993年通信総合研究所(現NICT)に入所。ナノメートルスケールによる情報通信アーキテクチャなどに関する研究に従事。博士(工学)。