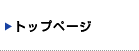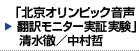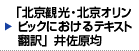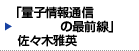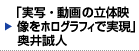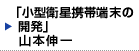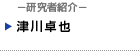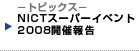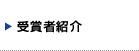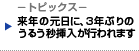最先端技術としての「立体映像」
立体映像は古くて新しい技術といえます。
映画や小説で描かれる未来図には古くから立体映像が登場し、おなじみの技術となっていますし、立体表示方式の基本原理には、考案されてから既に100年以上を経ているものも少なくありません。一方で、実用性の高い動画再生を実現するには、最新のディスプレイ技術と映像技術をふんだんに盛り込む必要があり、方式によっては更に今後の研究開発に負うところが大きい、という最先端技術としての側面があります。
立体映像は、テーマパークやイベントでのアトラクションとして人気を集めています。また最近、立体映画は3Dシネマとして制作、配給、上映の一連の体制や設備がこれまでになく整備されてきており、家庭への普及も視野に入れた新たなビジネスの動きとしても注目されています。これらの立体映像は二眼式と呼ばれ、視覚的には両眼視差(※)を再現する、主にメガネを用いる方法です。
二眼式は実用的な方式ですが、将来のさまざまなシーンにおける利用を考えると、自然さ・リアルさの点で十分とはいえません。総務省では将来の情報通信技術として、遠隔地とのコミュニケーション、知識の伝達、種々のインターフェースなどに立体映像を活用するための研究開発を推進することを掲げています。この目的を達成するには、単に鑑賞するだけでなく、目の前の再生像をいろいろな方向から眺める、他の感覚(たとえば触る感覚)と組み合わせて操作する、などこれまでにないリアルさが要求されます。
※両眼視差:両目で同時にものを見ると、左右の眼の網膜上の像には遠近に応じたずれが生じます。これを両眼視差といい、奥行きを感じる主要な要因となります。
リアルな再現方式として注目されているホログラフィ
視覚を通じて奥行きを知覚する手がかりは、前述の両眼視差以外にも複数あり、これらをどれだけ再現できるかが再生像のリアルさ、自然さに大きくかかわるといえます。視覚的な奥行き手がかりをほとんどすべて再現でき、将来想定される多くの用途においても実物感を十分に再現できる方式としてホログラフィがあります。
通常の映像が、たとえばカメラのように被写体からの光を明暗の強度で記録するのに対して、ホログラフィは光が波である性質を使って干渉縞と呼ばれるものを発生させ、これを記録します。干渉縞は通常の被写体からの光の明暗に加えてどの方向からやって来たかの情報も合わせて記録・再生することができ、この情報によって立体像をリアルな再現方式として注目されているホログラフィ再生できることになります(図1a)。
この干渉縞は、通常の撮影では1マイクロメートル程度あるいはそれ以下の非常に細かい縞となります。これを記録するため1mmの間隔に何千本も縞が描けるような特殊な乾板(記録材料)が用いられてきました。また、光の波としての性質を利用する関係上、撮影、表示には特殊な光(レーザー光)が用いられます。静止画のホログラフィは、このほかカラー化や普通の光でも像が再生できるように、さまざまな研究が行われてきました。この結果、静止画のホログラフィ立体写真は他の立体映像方式にない非常にリアルな再生像が得られています。
ホログラフィはこのように理想的な立体像が得られるため、コミュニケーションのための技術や立体テレビとして将来の情報通信分野に生かそうという期待が高まっています。そのためには、(1)撮影や表示、記録・伝送が電気的に行え、(2)さらに実写の動画像が入力できる、などの性質を持つ電子的なシステム(電子ホログラフィ)として実現する必要があります。しかし干渉縞により波面を再生するという特殊性があるため、他の立体映像方式と比べると本格的な研究開発に至っておらず基礎的レベルに留まっているのが現状です。NICTはこの中で、電子ホログラフィの実現のための課題に先導的に取り組む研究を開始しています。
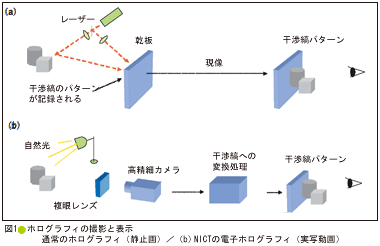
電子ホログラフィ実現に向けて
電子ホログラフィには、図2に示すように多くの課題があります。特に、視域が狭いこと、実写動画像の入力に制限があること、は実用化への大きなハードルと考えられ、NICTでもこれらを主要課題と捉えて研究を進めています。これまでの主な成果をご紹介します。
ホログラフィには前述のように1マイクロメートル以下の縞が描ける微細さが必要になります。現在、これに応えられる電子デバイスはまだなく、画素サイズが10マイクロメートル前後の表示デバイスが用いられます。これは必要とされる微細さより1桁大きいものです。この場合でも撮影・表示の条件を工夫することにより立体像を再生することができますが、それを見ることができる領域(視域)が非常に狭くなります。
NICTでの当面の目標は、再生像に近づいて見ても両目で見ることができる(すなわち立体視できる)視域の確保です。これを実現するためには、高密度なデバイスの使用、複数のデバイスの組み合せ技術、そのための種々の信号処理、がポイントとなります。これらを駆使することにより40cmまで近づいて両目で見られる立体像の再生に成功しています。
次に取り組んでいるのが実写動画像の撮影です。本来であれば被写体は、レーザー光を当てて(かつ余分な光が入らないよう暗室内で)撮影することになりますが、さまざまな対象を動画で撮影することは非常に困難です。そこで私たちは通常照明下で撮影できるインテグラルフォトグラフィと呼ばれる、複眼状のレンズを用いた立体映像方式によって撮影を行い、それをホログラフィ用のデータに変換することで制約のない撮影を行えるようにしました(図1b)。NICTでは最近、この方法を用いて撮影し、そのままリアルタイムで変換してホログラフィのカラー再生像を表示することに成功しました(図3)。
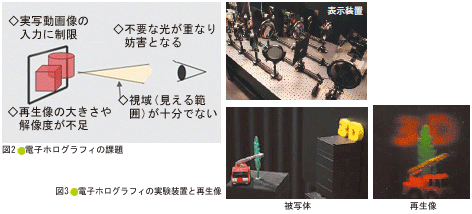
今後の課題をクリアするために
ご紹介した成果は、それが直ちに実用に結びつくというものではありませんが、将来の種々の応用に向けた着実な一歩を示せたと考えています。今後も視域の拡大、像サイズの改善、画質の改善など多くの課題をクリアしていく必要があります。
一方、立体映像が今後広く利用されていくには、ホログラフィだけでなく立体映像全体についてその魅力や効果がより多くの人に知られ、その技術的可能性が広く研究されることが今後も重要であると考えます。また、コンテンツの研究も不可欠となります。このために超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム(URCF)の活動のサポートなど、産学官の連携にも努めていきます。
Profile
 奥井誠人(おくい まこと)
奥井誠人(おくい まこと)
ユニバーサルメディア研究センター 超臨場感基盤グループ グループリーダー
大学院修士課程修了後、1980年日本放送協会入局。立体テレビなどの研究に従事。2006年よりNICTにおいて、超臨場感コミュニケーションのための立体映像の研究に従事。博士(工学)。